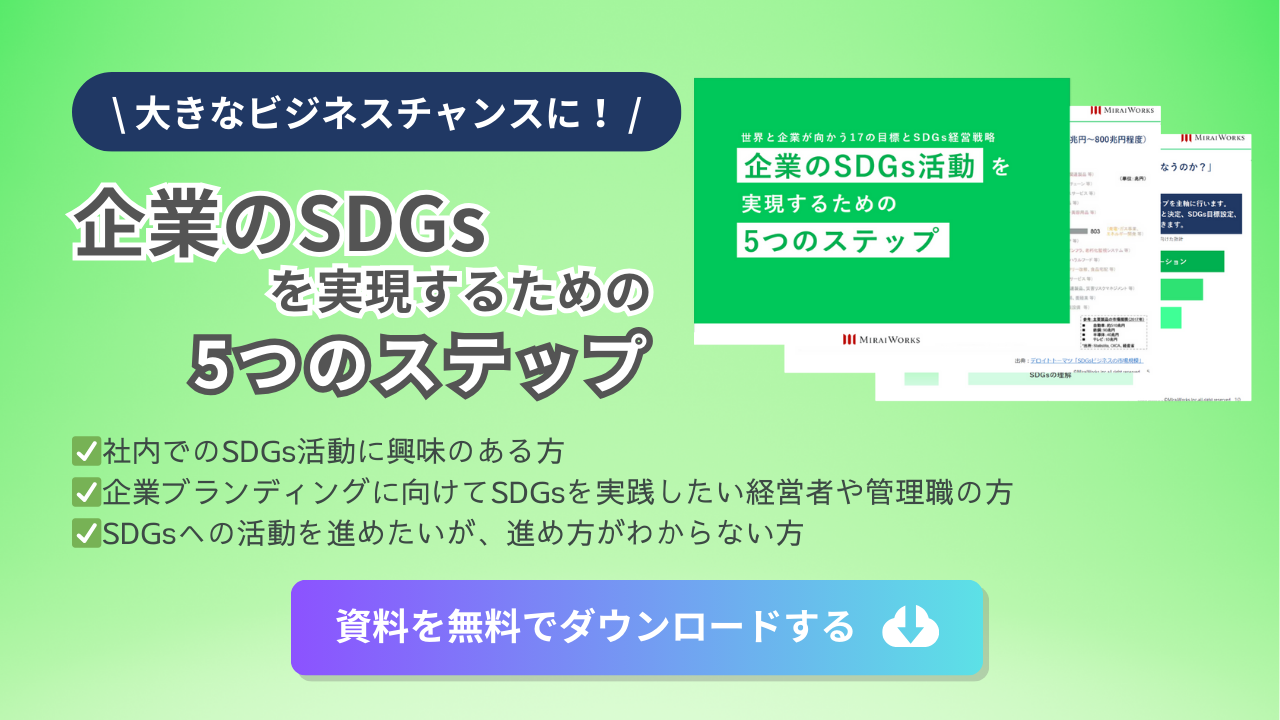ESG経営は、企業が持続的に成長し、社会に貢献するための重要な経営手法です。企業がESGの課題に積極的に取り組むことで、新たな価値の創造につながるなど、持続可能な社会の実現に貢献できます。
ただし、ESG経営にはデメリットや注意点も多く、リスクマネジメントも欠かせません。本記事では、ESG経営について解説しながら、メリット、デメリット、成功事例について幅広く紹介します。
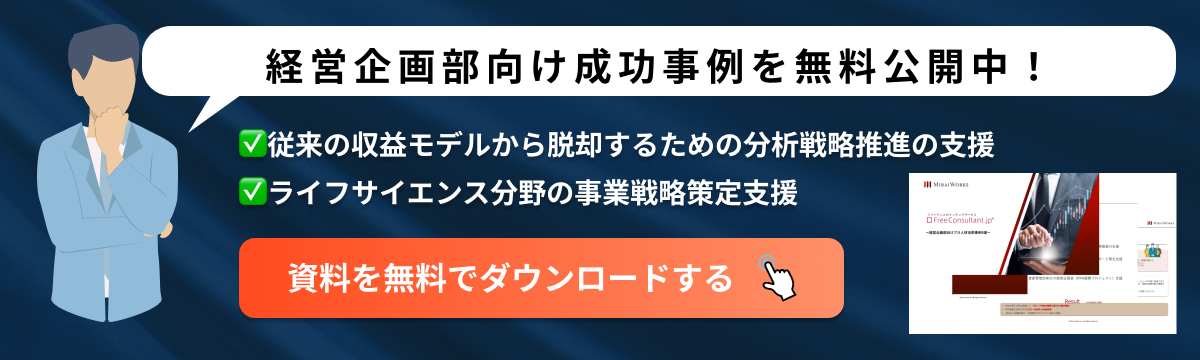
ESG経営とは?
ESG経営とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の3つの要素を重視する経営手法のことです。従来の企業経営は売上や利益などの財務諸表を重視していましたが、近年では企業の持続的な成長のために環境や社会への配慮も不可欠であるという考え方が広まっています。
ここでは、ESG経営で重視される3つの要素について解説します。
企業の事業活動が環境に与える影響を最小限に抑え、持続可能な社会の実現に貢献するための取り組みが問われます。具体的には、温室効果ガスの排出量削減、再生可能エネルギーの利用、カーボンオフセット、廃棄物の削減やリサイクルなど、環境問題への取り組みとなることが多いです。
Environment(環境)について考える際は、原材料の調達から製品の製造、販売、廃棄に至るまで、サプライチェーン全体で環境負荷を低減する取り組みが必要です。環境負荷の低い製品やサービス、技術の開発を推進することで、持続可能な社会の実現に貢献できます。
Social(社会)
Social(社会)では、企業の事業活動が社会に与える影響を考慮し、持続可能な社会の実現に貢献するための取り組みが問われます。具体的には、多様な人材の雇用と活躍推進、従業員の健康と安全の確保、ワークライフバランスの推進など、労働環境に関する取り組みとなることが多いです。
従業員、顧客、地域住民など、様々なステークホルダーとの対話を通じて、社会課題を把握し、解決策を検討することが重要です。また、近年は性別、年齢、国籍、障がいの有無にかかわらず、多様な人材が活躍できる職場環境を整備することも求められています。
Gavernance(ガバナンス)
Gavernance(ガバナンス)では、企業が健全な経営を行い、持続的な成長を実現するための組織体制や仕組みが問われます。具体的には、徹底した法令遵守、経営状況やリスク情報の開示、リスクマネジメント体制の構築、内部統制の強化など、倫理的な企業文化の醸成に関する取り組みとなることが多いです。
近年、ガバナンス体制は投資家が企業を評価する際の重要な指標となっています。健全なガバナンス体制は企業の不正や不祥事を防止し、リスクを低減することにも貢献するので十分な対策が必要です。
ESGとSDGsの違い
ESGと似た言葉に「SDGs」がありますが、厳密には意味合いが異なるので注意しましょう。
SDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2015年9月に国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17の目標と169のターゲットで構成され、より良い世界を目指すためのより具体的な目標設定がされています。
ESGは企業や投資家を主体として主に企業の活動を評価しますが、SDGsは国連が主体で社会全体の課題を扱います。このように、ESGは企業の持続可能性を高めるための「企業の評価基準」であり、SDGsは社会全体の持続可能性を目指す「国際目標」です。
ESG経営の取り組みが必要とされる社会背景
ESG経営の取り組みが必要とされる社会背景として、地球規模での課題の深刻化が挙げられます。地球温暖化による異常気象や自然災害は数多く発生しており、ひとつの国、政府や少数の個人の努力だけでは改善に限界がきています。
人口増加や経済成長に伴う資源の消費拡大、プラスチックごみ問題や大気汚染など問題は数多く、環境問題は企業の事業活動にも大きな影響を与えているのです。そのため、企業には持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められています。
日本と海外のESG経営への温度差
日本でも年々ESGへの関心が高まりつつありますが、欧米と比較するとまだ意識の差が見られます。各企業により、ESG情報の開示に関するガイドラインなどが整備されつつあるものの、まだ発展途上と言えるでしょう。日本企業では従業員や取引先などステークホルダーとの関係性を重視する傾向があり、企業の社会的責任(CSR)は二の次となっているのも現状です。
しかし、2022年4月、東京証券取引所がプライム市場上場企業に対し気候変動開示を求めるようルールづくりをするなど、少しずつ日本の環境も見直されています。今後さらにESG経営へ取り組む日本企業が増えていくでしょう。
ESG経営の4つのメリット
ここでは、ESG経営のメリットを解説します。なぜ多くの企業がESG経営に着手し始めているのか、理由を探ってみましょう。
①投資家からの評価向上
近年、環境、社会、ガバナンスに配慮した企業を重視する「ESG投資」が世界的に拡大しています。短期的な利益だけでなく、長期的な視点で企業の持続可能性を評価する投資家が増えたことで、ESG経営が加速化しました。
結果、ESG評価の向上が企業の株価上昇につながったり、ESG投資家からの資金調達が容易になったりするケースも珍しくありません。
また、ESGへの積極的な取り組みは、投資家だけでなく消費者、取引先、求職者などのステークホルダーからの評価向上にも役立ちます。この先10年20年と続く持続可能な企業発展を目指したいときにこそ、ESG経営がメリットとなるのです。
②労働環境の整備、改善
ESG経営の一環として労働環境の整備、改善に取り組む企業は多く、結果的に自社に利益をもたらしています。働きやすい環境は従業員の仕事への意欲を高め、エンゲージメントを向上させます。
また、安全で健康的な職場環境は従業員の心身の健康を維持するのに貢献し、集中力や創造性を高めることにもつながるでしょう。多様な働き方を支援する制度は、従業員のワークライフバランスを改善し、ストレスを軽減するのもポイントです。
こうした「従業員を大切にする企業」は、離職率を低下させ、優秀な人材の定着を促します。今いる社員だけでなく採用市場からの評価も高くなり、優秀な人材を積極的に採用しやすくなるのです。
③経営リスクの軽減
ESG経営は、経営リスクの軽減にも貢献します。たとえば、Social(社会)の部分に力を入れるESG経営にした場合、人権問題、労働問題、地域社会のトラブルなど、企業の評判やブランドイメージを損なうリスクを軽減できるのがメリットです。
その他、法令違反、不正行為、情報漏洩など企業の信頼性を損なうリスクを軽減したり、資源の枯渇や環境汚染による原材料の調達リスクを予防したりするESG経営も可能です。
ESG経営は、企業が持続的に成長し、社会からの信頼を得るために不可欠な要素です。リスクを事前に把握し、予防的な対策を講じることで、損失を最小限に抑えていきましょう。
④自社ブランド力の向上
ESG経営は、企業のブランド力向上に大きく貢献します。現代の消費者は、単に製品やサービスの機能性や価格だけでなく、企業の社会的責任や環境への配慮を重視する傾向が強まっています。ESGに積極的に取り組む企業は、倫理的で信頼できる企業として評価され、消費者の支持を得やすくなるでしょう。
また「従業員のエンゲージメントが高い会社」「投資家から評価されている会社」としてブランド力を上げることもでき、市場での信頼を獲得することにつながります。環境問題や社会問題への貢献は企業のイメージアップになるからこそ、コストをかけてでもESG経営に着手する企業が増えているのです。
ESG経営の2つの課題とデメリット
ESG経営には多数のメリットがある一方で、デメリットも存在します。以下で代表的な課題とデメリットを紹介するので、事前にチェックしておきましょう。
①短期間での効果は得られない
ESG経営は、短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点で企業の持続可能性を高めることを目的としています。そのため、効果が現れるまでに時間がかかる点に注意しましょう。
また、ESGに関する取り組みには、設備投資、システム導入など初期投資も必要です。投資コストを回収し、利益につなげるためにはある程度の期間がかかります。企業の組織文化や従業員の意識改革が必要で、短期間で成果を出すことは難しい場合も多いです。
②明確なゴールがない
ESG評価は、様々な機関が異なる基準で評価しており、統一された評価基準が存在しません。そのため、企業はどの評価基準を重視すべきか判断に迷うことがあります。また、環境問題、労働問題、ガバナンス問題は、時代ごとに必ず何かしらの課題が発生するので、100%解消されることはほとんどありません。
よって、ESGに関する取り組みをアピールしながら、実際には環境や社会に配慮していない「グリーンウォッシュ」と呼ばれる活動になってしまうことも懸念されます。
ESGスコアの評価機関とは
ESGスコアの評価機関は、企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する取り組みを評価し、スコアとして投資家や利害関係者に提供する機関です。自社を評価してもらえる他、投資家がより良い投資判断を行うための情報提供も手がけています。
代表的なESG評価機関としてMSCI(モルガン、スタンレー、キャピタル、インターナショナル、FTSE Russell、日本経済新聞社(日経NEEDS)などが挙げられます。ESGの重要課題を評価したドラフトレポートや企業からのフィードバックも得られるので、ESG経営の参考として活用しましょう。
企業はESGスコアを開示する必要がある
ESGスコアの評価機関を活用する場合、評価スコアが年に1回開示されます。ESGスコアを開示することによって企業の透明性が向上し、ステークホルダーからの信頼を得やすくなるので、ぜひ活用しましょう。
始めは低いスコアであっても、年々改善している様子や自社独自の取り組みが評価され始めている様子を開示できれば、決してネガティブな情報になることはありません。実際に、ESG経営に自信のある企業が積極的にスコアを開示し、投資家やステークホルダーからの評価を高めるケースもあります。
上場企業を中心にESGスコアの開示を求める動きが強まっていますが、現時点では全ての企業に対してESGスコアの開示が義務付けられているわけではありません。自社の状況に応じて判断しましょう。
ESG投資を受けるために企業が行うべきESG経営のポイント3つ
ここでは、ESG投資を受けるために企業が行うべきESG経営のポイントを解説します。資金調達のためにESG経営を検討している方は、以下をご参考ください。
①目標や目的を明確にする
投資家は企業の長期的な成長と可能性に投資を行います。目標や目的を明確にして、成長過程を公開して評価を得ることによってESG投資が受けやすくなるでしょう。
目標と目的が明確であれば企業全体のESG戦略の方向性が定まり、各部門が連携しながら効率的にESG活動を推進できます。反対に、目標や目的が明確でないEGS経営の場合、行き当たりばったりな戦略になりやすく、ステークホルダーが企業を信頼できなくなるかもしれません。
目標や目的を明確にすることはESG経営を成功させるための第一歩と捉え、課題意識の見直しから始めてみましょう。
②投資家の視点になり、透明性の高い情報公開を行う
投資家が企業のESGへの取り組みを評価する際は、単に表面的な情報だけでなく、具体的な目標、実績、リスク管理体制などを重視します。投資家がどのような情報を求めているのかを理解し、開示内容に反映させていけば、投資家がリスクを評価しやすくなるでしょう。
また、短期的な成果だけでなく、長期的な目標や戦略などを開示するのもポイントです。第三者機関による保証や認証を取得することで情報の信頼性を高めるなど「見てもらいやすい」「信じてもらいやすい」透明性の高いデータ作成を行いましょう。
③実施施策の評価、検証は定期的に行う
設定したESG目標に対する進捗状況は定期的に確認し、目標達成に向けた軌道修正を行いましょう。実施した施策が期待通りの効果を生み出しているかを評価し、効果が低い場合は改善策を検討できるのがポイントです。
反対に、ESG経営における実施施策の評価、検証が定期的でない場合、施策の進捗状況や効果を把握できず、目標達成が遅れるかもしれません。効果の薄い施策を繰り返してしまったり、リスクが顕在化したりする可能性もあるので注意しましょう。
ESG経営の3つの事例
ここでは、ESG経営の事例を紹介します。ESG経営はありとあらゆる業種で導入できる手法なので、以下を参考に、自社でもできることがないか検討してみましょう。
①Canon
Canonは「共生」という企業理念のもと、ESG経営を推進しています。環境(Environment)分野では、製品の企画、開発から、生産、販売、使用、リサイクルに至るまで各段階で環境負荷低減に取り組んでいるのが特徴です。その他、取引先から収集した部品原材料CO2の実データを活用し、LCA(ライフサイクルアセスメント)に組み込むなど、独自の対策も実施しています。
すでにグローバル企業としても有名なCanonは、国際的な人権規範を尊重し、事業活動における人権尊重に取り組んでいるのもポイントです。従業員の安全と健康を確保し、働きやすい職場環境づくりを推進しています。
②トヨタ自動車
トヨタ自動車は「幸せの量産」をミッションに掲げ、ESGを経営の重要な柱として位置づけています。2050年までに車両のライフサイクル全体でのCO2排出量ゼロを目指し、電動車の開発や再生可能エネルギーの導入を推進するなど、カーボンニュートラルに貢献しているのが特徴です。3R(リデュース、リユース、リサイクル)やダイバーシティ&インクルージョンなど活動の幅も広く、ESGに関する情報も積極的に開示しています。
また、交通事故ゼロを目指し、先進安全技術の開発や普及を推進するなど自動車メーカーならではのESG経営にも着手しています。今後の自動運転やセールティコントロールなど、技術発達との両立も期待されます。
③日本郵政
日本郵政グループは、郵便、貯金、保険という全国ネットワークを活かし、ESG経営を推進しています。サステナビリティを経営の重要な柱として位置づけていて、郵便局ネットワークを活用した地域のカーボンニュートラル化に貢献しているのが特徴です。具体的には、輸送における環境負荷の低減や、郵便局における環境配慮型の取り組みを進めています。
また、自然災害発生時の郵便、貯金、保険サービスの提供や、地域社会との連携による防災、減災活動も実施しています。全国47都道府県に展開する郵便ネットワークだからこそできるESG施策も多く、今後も安定した役割が期待されているので注目しておきましょう。
ESG経営を考えている方は「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください
ESG経営は、企業の持続的な成長と社会への貢献を両立させるための重要な経営戦略です。しかし、ESG経営の導入や推進には専門的な知識や経験が必要となる場合も多く、自社だけで取り組むには限界を感じることもあるでしょう。
ESG経営を考えている方は「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください。
「フリーコンサルタント.jp」には、大手コンサルティングファーム出身者など、経験豊富なプロフェッショナルが多数登録しています。多様な業界、分野の専門家が在籍しているため、企業の課題やニーズに合った最適なコンサルタントを見つけられます。ESG経営だけでなく、経営戦略、マーケティング、IT、人事など、幅広い分野のコンサルティングに対応可能です。
まとめ
企業が持続可能な成長と社会への貢献を両立させるために、ESG経営はもはや不可欠な手法となりつつあります。従来の財務情報だけでなく、ESGスコアなど非財務情報も考慮することで、企業の持続的な成長と社会への貢献を目指しましょう。
「フリーコンサルタント.jp」では、ESG経営に関する戦略立案、施策考案、評価、改善まで一気通貫型でサポートできます。プロのコンサルタントを採用し、専門性の高いアドバイスやフィードバックを得ながら、自社オリジナルのESG経営にしていきましょう。