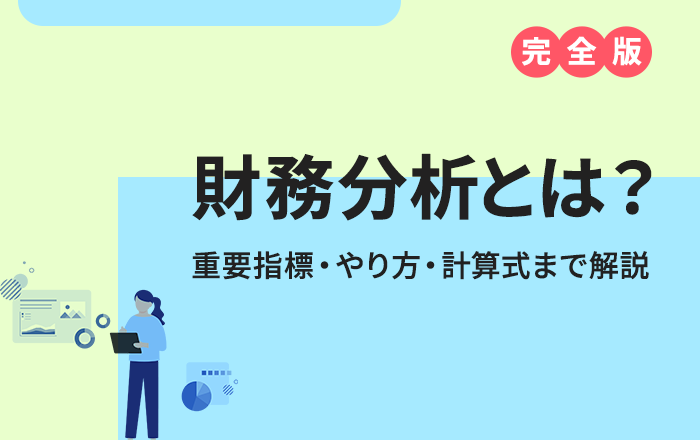
財務分析を行うことで、経営状態を客観的に評価することができます。企業が安定した経営を続けるためには、適切な財務分析が欠かせません。
本記事では、財務分析の基本、具体的なステップ、実践的なポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。財務分析の基本を理解できれば、自社の経営改善、さらには未来の成長戦略策定への第一歩を踏み出せるでしょう。
■目次
財務分析とは?
財務分析とは、企業の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)の数字を用いて、経営状態を客観的に評価する手法です。収益性、安全性、効率性などを分析し、問題点や改善点を見つけ出します。
たとえば、売上が増加しているのに利益が減少している場合、コスト構造に問題がある可能性が高いです。また、借入金が多額であれば、将来の金利負担が経営を圧迫するリスクも考えられるでしょう。これらの問題は財務諸表を通じて分析を行えば早期に発見できるため、適切な対策を講じることが可能です。
財務分析は企業の健康状態を把握し、未来の成長戦略を立てるための重要な手法と言えるでしょう。
財務分析に生成AIを活用することもできる
財務分析に生成AIを活用すると、データの入力や収集、検証、報告といった定型作業を自動化し、従業員の負担軽減や人的ミスの削減ができます。
たとえば、生成AIを活用することで、以下のような業務が代替可能です。
- 問い合わせ対応の自動化
社内からの会計処理や財務データに関する質問に対し、AIが自動で回答できる - レポート作成の自動化
財務報告書や決算説明会資料などの作成をAIが支援し、業務効率化と品質向上に貢献する - 予測とシミュレーションの強化
過去のデータや外部環境の変化を基に、複数のシナリオを生成し、最適な戦略を提案する
ただし、生成AIの活用には注意点もあります。具体的には、データの品質とセキュリティ、生成AIの理解と評価、倫理と社会的責任といった点に注意が必要です。特に、生成AIは事実と異なる情報や嘘(ハルシネーション)を生成する可能性があるため、出力結果を鵜呑みにせず、人間が最終的に確認、判断することが重要です。
財務分析に必要な財務諸表(必要書類)3つ
財務分析を行うには、企業の財務状況を把握するための資料を用意する必要があります。主に使われるのが「財務三表」と呼ばれる、以下の3つの書類です。
1.貸借対照表(B/S)
貸借対照表は、決算日時点での企業の財政状態を示す書類です。 バランスシート(英:Balance Sheet)とも呼ばれており、略してB/Sと表記されることもあります。
財務分析に貸借対照表が必要な理由は、企業の資産、負債、純資産のバランスを見ることで、企業の安定性や健全性を評価できるからです。資産、負債、純資産には、以下のようなものがあります。
- 資産:企業が持つ現金や預金、土地、建物など
- 負債:借入金や買掛金など、将来支払うべきお金
- 純資産:資産から負債を差し引いたもので、返済義務のない自己資本
たとえば、流動資産(1年以内に現金化できる資産)と流動負債(1年以内に支払うべき負債)を比較することで、短期的な支払い能力を判断できます。また、自己資本比率(純資産÷総資産)を見ることで、企業の財務的な安定性を評価可能です。
2.損益計算書(P/L)
損益計算書は、一定期間における企業の経営成績を示す書類です。 英語ではProfit and Loss Statementと呼ばれていることから、略してP/Lと表記されることもあります。財務分析に損益計算書が必要な理由は、企業の収益、費用、利益の関係を見ることで企業の収益性や効率性を評価できるからです。
損益計算書では、以下の項目を確認できます。
- 売上高総利益率(粗利率):商品の収益性を評価できる
- 営業利益:本業での稼ぐ力を把握できる
損益計算書は、企業の収益力を示す成績表であり、どれだけ儲けているか、何に費用を使っているかを把握するために重要な基礎資料となっています。
3.キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は、一定期間における企業のお金の流れ(収入と支出)を示す書類です。 英語ではCash Flow Statementと呼ばれていることから、略してC/Fと表記されることもあります。
キャッシュフロー計算書では、損益計算書ではわからない、実際のお金の動きを把握することが可能です。具体的には、以下の区分で現金の流れを把握します。
- 営業活動:本業でどれだけ現金を生み出しているかを確認できる
- 投資活動:設備投資など将来への投資状況を確認できる
- 財務活動:借入や返済など資金調達の状況を確認できる
キャッシュフロー計算書を通して資金繰りの状況や将来の成長性を判断することができるため、資金ショートの防止や円滑な資金調達が実現できます。また、今後の収益が見込めない事業を早い段階で発見することもできるため、無駄なコストを削減できるでしょう。
決算書の見方
決算書を見る際は、以下のポイントを意識すると企業の経営状況や財務状態をより深く理解できます。
- 全体像を把握する
貸借対照表(資産、負債、純資産)、損益計算書(収益、費用、利益)、キャッシュフロー計算書(お金の流れ)の役割と主要項目を把握し、企業の規模感をつかむ - 個別項目を確認する
・貸借対照表:流動比率(短期支払い能力)、自己資本比率(財務安定性)を確認する
・損益計算書:各利益の推移、売上総利益率(商品収益性)、営業利益率(本業収益力)を確認する
・キャッシュフロー計算書:営業CF(本業の現金創出)を確認する - 指標分析を行う
主要な財務指標を計算し、同業他社や過去と比較する - 継続的に比較、分析する
複数年度や同業他社と比較し、成長性や変化、強みや弱みを評価する
これらのステップで進めることで、決算書の数字が示す意味を多角的に捉え、企業の現状と将来性をより深く理解できます。

【計算式付き】財務分析の5種類の手法とみるべき指標
財務分析は、企業の経営状態を把握し、課題を改善するための様々な分析手法があります。ここでは、代表的な5つの分析方法と、それぞれで見るべき主要な指標を見ていきましょう。
1.収益性分析
収益性分析とは、企業がどれだけ効率的に利益を上げているかを評価する分析手法です。
具体的には、以下の指標を用います。
- 売上高総利益率(粗利率)20%
売上高に対する売上総利益(売上高 – 売上原価)の割合で、商品の収益性や、製造、仕入れの効率性を表す
・計算式:売上総利益 ÷ 売上高 × 100 - 売上高営業利益率6%以上
売上高に対する営業利益(売上総利益 – 販売費及び一般管理費)の割合で、本業での収益力を表す
・計算式:営業利益 ÷ 売上高 × 100 - 総資本経常利益率(ROA)5.1&
総資本(自己資本 + 他人資本)に対する経常利益(営業利益 + 営業外収益 – 営業外費用)の割合で、企業全体の収益性を表す
・計算式:経常利益 ÷ 総資本 × 100
売上高総利益率は20%以上、売上高営業利益率は6%以上、総資本経営利益率は5.1%位以上であれば、収益性が高いと判断できます。
2.安全性分析
安全性分析とは、企業の支払い能力や財務的な安定性を評価する分析です。 企業が短期、長期の負債を返済する能力があるか、倒産のリスクが低いかなどを把握できます。
安全性分析に活用する指標は、以下の通りです。
- 流動比率
流動資産(1年以内に現金化できる資産)に対する流動負債(1年以内に支払うべき負債)の割合で、短期的な支払い能力を表す
・計算式:流動資産 ÷ 流動負債 × 100 - 自己資本比率
総資本に対する自己資本(返済義務のない資本)の割合で、長期的な財務安定性を表す
・計算式:自己資本 ÷ 総資本 × 100
流動比率は一般的に120%以上が望ましいとされ、自己資本比率は一般的に30%以上であることが目安とされています。
3.生産性分析
生産性分析とは、企業が投入した経営資源(ヒト、モノ、カネ)から、どれだけ効率的に付加価値を生み出しているかを評価する分析です。以下の指標を用いることで、企業の経営効率を評価できます。
- 労働生産性
従業員一人当たりの付加価値額(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)を計算し、労働の効率性を表す
・計算式:付加価値額 ÷ 従業員数 - 労働分配率
付加価値額に対する人件費の割合で、付加価値の分配の適正さを表す
・計算式:人件費 ÷ 付加価値額 × 100
以上の指標を適切に評価することで、生産性向上のための施策を検討できます。
4.成長性分析
成長性分析とは、企業の売上高や利益などが、時間の経過とともにどの程度伸びているかを評価する分析です。以下の指標を用いることで、企業の将来性を予測できます。
- 増収率
前期と比較した売上高の増加率を計算します
・計算式:(当期売上高 – 前期売上高) ÷ 前期売上高 × 100 - 増益率
前期と比較した経常利益の増加率を計算します
・(当期経常利益 – 前期経常利益) ÷ 前期経常利益 × 100
増収率は6%~20%、増益率は8.6%程度であれば、成長性が高いと判断できます。
5.効率性分析
効率性分析とは、企業が資産をどれだけ効率的に活用して、売上や利益を生み出しているかを評価する分析です。資産の利用状況を評価できるため、財務分析に必要とされています。
効率性分析には、以下の指標を活用しましょう。
- 総資本回転率
売上高に対する総資本の割合で、総資本が1年間に何回転して売上高を生み出したかを表す
・計算式:売上高 ÷ 総資本 - 棚卸資産回転率
売上高に対する棚卸資産(在庫)の割合で、棚卸資産が1年間に何回転して売上高を生み出したかを表す
・計算式:売上高 ÷ 棚卸資産
以上の指標を適切に評価することで、資産の有効活用に向けた施策を検討できます。なお、総資本回転率は1.0以上、棚卸資産回転率は11回以上が目安とされており、それよりも多い場合は売り上げや利益を十分に生み出せていると言えるでしょう。
財務分析を活用するための3つのステップ
財務分析は、単に指標を計算するのではなく、段階を踏んで進めることで、より効果的な経営改善が可能です。ここでは、財務分析を最大限に活用するための3つのステップを紹介します。
1.決算書の準備
財務分析の第一歩は、分析に必要な決算書を準備することです。 決算書は企業の「健康診断書」であり、財務分析の基礎データとなります。
具体的には、以下の書類を準備しましょう。
- 貸借対照表:企業の財政状態(資産、負債、純資産)を示す書類
- 損益計算書:企業の経営成績(収益、費用、利益)を示す書類
- キャッシュフロー計算書:企業のお金の流れ(収入と支出)を示す書類
最低でも、直近2期分(今期と前期)の決算書を用意しましょう。過去のデータと比較することで、企業の変化や傾向を把握できます。
2.基本項目の分析
決算書が準備できたら、まずは基本的な項目を分析し、企業の全体像を把握します。これは、健康診断でいうところの、身長、体重測定や血液検査のようなものです。
具体的には、以下の項目を確認します。
- 損益計算書
売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益の金額と、それぞれの増減を確認します - 貸借対照表
流動資産と流動負債のバランスを確認し、短期的な支払い能力(流動比率)を把握します
以上の基本的な項目を分析することで、企業が抱える問題点やさらなる詳細な分析が必要な箇所を特定できます。
3.応用項目の分析
基本項目の分析で企業の全体像を把握したら、より詳細な分析(応用項目の分析)を行います。 これは、健康診断でいうところの、精密検査のようなものです。
具体的には、以下のような分析を行います。
- 収益性分析
売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本経常利益率などを計算し、企業の収益性を評価します - 安全性分析
流動比率、自己資本比率、固定比率などを計算し、企業の財務的な安定性を評価します - 生産性分析
労働生産性、労働分配率などを計算し、企業の経営効率を評価します - 成長性分析
増収率、増益率などを計算し、企業の成長性を評価します - 効率性分析
総資本回転率、棚卸資産回転率などを計算し、企業の資産の活用状況を評価します
これらの応用項目の分析を通じて企業の強みと弱みをより深く理解することで、具体的な経営改善策の立案につなげられます。

財務分析を正確に行うためのポイント4つ
財務分析は、企業の経営状態を把握し改善するための重要な手段ですが、その分析結果が正確でなければ、誤った経営判断につながる可能性が高いです。ここからは、財務分析を正確に行うためのポイントを4つ解説します。
1.財務諸表を正確に作成する
財務分析の基本は、正確な財務諸表を作成することです。 財務分析は財務諸表の数字を基に行われるため、その数字が間違っていれば、分析結果も誤ったものになってしまいます。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
- 日々の取引を正確に記録する
- 仕訳や転記ミスがないか確認する
- 計上漏れがないか確認する
- 会計基準の変更など、最新の会計ルールに則って処理する
- 内部統制の仕組みを構築し、不正や誤りを防ぐ体制を整える
例:複数人によるチェック体制、会計システムの活用
上記を意識して財務諸表を作成することで、財務分析の質が向上するでしょう。
2.経営戦略や目的に沿って手法を選択する
財務分析には様々な分析手法がありますが、全ての手法を活用する必要はありません。企業の規模や成長段階、業種などによって重視すべきポイントが異なるため、企業の経営戦略や分析の目的に合わせて、適切な分析手法を選択することが重要です。
各ケースごとに活用するべき分析手法を以下にまとめました。
- 設立間もないベンチャー企業:収益性や安全性よりも、成長性を重視する
- 成熟した大企業:収益性や安全性が、より重要な指標となる
自社の状況や目的に合わせて適切な手法を選択し、分析することが効果的な財務分析につながります。
3.複数年にわたる財務データを比較する
財務分析は、単年度のデータだけでなく複数年にわたるデータを比較することが重要になってきます。なぜなら、単年度のデータだけではその数値が良いのか悪いのか、一時的なものなのかを判断することが難しいからです。
複数年のデータを比較することで、以下のような情報を把握でき、より正確な現状分析が可能になります。
- 売上高や利益の増減傾向
- 財務体質の変化
例:自己資本比率の推移 - 特定の指標の長期的なトレンド
たとえば、売上高が前年比で増加していても、過去3年間で見ると減少傾向にあるかもしれません。このような場合、単年度のデータだけでは見過ごしてしまうリスクを複数年のデータ比較によって発見できます。
4.専門家のサポートを受ける
財務分析は、専門的な知識や経験が必要となる場合があります。 財務分析には様々な手法や指標があり、分析結果の解釈には専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることが有効です。特に経営改善への活用については、自社の状況を客観的に評価し適切なアドバイスを受けるためにも、外部の専門家の視点は重要とされています。
税理士や公認会計士、経営コンサルタント、金融コンサルタントなどの専門家は、財務分析の知識だけでなく、豊富な経験に基づいたアドバイスを提供してくれます。それぞれの専門分野を活かし、多角的な視点からサポートを受けることで、より効果的な財務分析と経営改善につなげられるでしょう。
財務分析にお困りの方は「フリーコンサルタント.jp」にご相談ください
財務分析でお困りの企業の方は、フリーコンサルタント.jpの活用がおすすめです。23,000名以上のプロ人材から、財務分析の経験豊富な専門家を最短即日でご紹介致します。
なお、フリーコンサルタント.jpの強みは、以下のとおりです。
- 高いマッチング力:丁寧なヒアリングで、最適なスキルや経験を持つ人材を選定
- 幅広い対応領域:財務分析はもちろん、経営戦略、事業企画など様々な分野に対応
- 柔軟な契約形態:短期〜長期、プロジェクト規模に合わせて柔軟に契約可能
- 徹底サポート:専門コーディネーターが貴社とコンサルタントの間に入り、円滑なプロジェクト推進を支援
財務分析の専門家のサポートを受けることで、自社の経営状況を正確に把握し、より効果的な経営戦略の立案、実行に繋げることができます。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、財務分析の基本から応用、実践的なポイントまでを解説しました。財務分析は、企業の「健康診断」であり、経営状態を客観的に把握し、問題点や改善点を見つけ出すための重要なプロセスです。
■この記事のまとめ
- 財務分析の目的
企業の収益性、安全性、成長性などを評価し、経営判断の材料とする - 財務諸表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つが基本 - 分析の種類
収益性、安全性、生産性、成長性、効率性の5つが代表的 - 財務分析の活用ステップ
決算書準備、基本項目分析、応用項目分析の3段階で進める - 財務分析を行うポイント
正確な財務諸表作成、目的に合った指標選択、複数年比較、専門家活用がポイント
財務分析は、企業の持続的な成長に欠かせません。
本記事を参考に、ぜひ自社の財務分析に取り組み、経営改善に役立ててください。専門的な知識が必要な場合は、「フリーコンサルタント.jp」など、外部の専門家への相談も検討しましょう。







