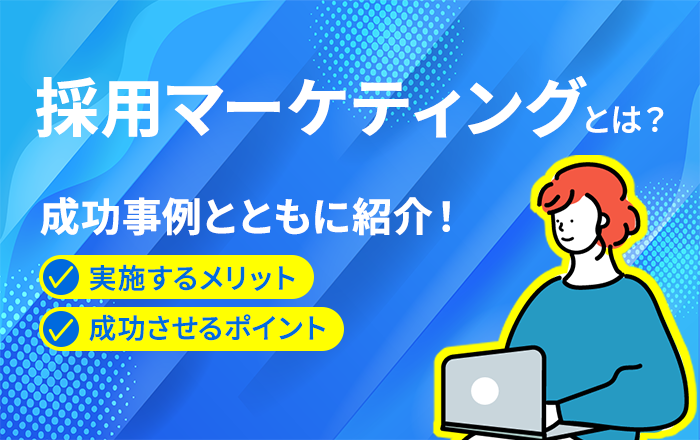
近年、採用市場は売り手優位の状態が続いており、従来のように求人広告や人材紹介だけで優秀な人材を確保することが難しくなっています。そんな中で注目されているのが、「採用マーケティング」です。採用マーケティングは企業が自社の魅力をマーケティングの視点から戦略的に発信し、求職者の関心を高めていく採用手法として確立しました。
この記事では、採用マーケティングを行うメリットはもちろん、生じる課題や成功させるためのポイントまで丁寧に解説していきます。自社の採用活動に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
■目次
採用マーケティングとは?
採用マーケティングとは、マーケティング手法を取り入れた採用活動のことです。単に求人広告を出すだけでなく、企業の魅力、ビジョン、社風を明確に打ち出し、求職者との接点を増やして関係性を築きながら応募を促します。

採用マーケティングは従来の「応募を待つ採用」と異なり、適切なチャネル、タイミング、メッセージでアプローチする「攻めの採用」である点も特徴です。
Web広告、SNS、オウンドメディアなどを活用しながらブランディングや情報発信に力を入れ、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらう仕組みづくりを行います。
採用マーケティングと採用ブランディングの違い
採用マーケティングと採用ブランディングの違いは、主に以下の通りです。
| 項目 | 採用マーケティング | 採用ブランディング |
| 目的 | 応募を増やし、採用の成果につなげる | 企業の魅力や価値観を伝え、好印象、信頼感を築く |
| アプローチの範囲 | 求職者に向けた情報発信や応募促進のための施策全般 | 長期的な企業イメージの構築と浸透 |
| 具体的な手法 | Web広告、SNS運用、オウンドメディア、採用イベントなど | 採用サイトの世界観設計、動画、コンテンツ制作、社内発信 |
| ゴール | 応募数や採用率の向上 | 「この会社で働きたい」と思ってもらうブランド価値の確立 |
| 期間的な視点 | 比較的短期(採用活動期間中など) | 長期的、継続的に構築していくもの |
採用マーケティングは「今まさに採用したい」というニーズに応える短期的な施策であり、応募者の獲得に直結する戦術として確立しています。一方、採用ブランディングは「この会社で働きたい」と思ってもらえるように長期的な魅力づけを行う戦略であり、会社の採用力そのものを底上げする役割を担っています。
簡単に言えば、採用マーケティングは「応募してもらうための戦術」であり、採用ブランディングは「魅力を伝えるための土台づくり」です。

企業が求める人材を確保するためには、どちらか一方ではなく両方をバランスよく取り入れることが欠かせません。
採用マーケティングが注目されている背景
採用マーケティングが注目されている背景として、以下が挙げられます。
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 求職者の情報収集行動の変化
- 企業ブランディングの重要性の高まり
- 採用活動のデジタルシフト
- 中小企業や地方企業の採用課題の深刻化
採用マーケティングが注目されている背景には、社会的、構造的な変化と求職者の価値観の変化が大きく影響しています。日本では少子高齢化による労働人口の減少が続いており、企業間の人材獲得競争はかつてないほど激化するようになりました。売り手市場の中で求職者は「自分に合った企業」を主体的に探すようになり、情報収集の方法もSNSや口コミなど多様化しています。

つまり、単に求人票を出すだけでは人材を集めることが難しく、企業には「選ばれる側」としての姿勢が欠かせない時代になりつつあるのです。
自社の魅力を戦略的に伝える採用マーケティングの手法を取り入れることで、認知を広げたり共感を得てからの応募を得やすくなるなど、高い効果が得られます。
採用マーケティングを行う3つのメリット
ここでは、採用マーケティングを行うメリットを解説します。
- 自社にあった優秀な人材の確保ができる
- 採用コストを削減できる
- 採用のミスマッチを減らせる
なぜコストをかけてでも採用マーケティングをするのか、理由を探ってみましょう。
①自社にあった優秀な人材の確保ができる
単にスキルや学歴だけで人材を選ぶのではなく、自社のビジョン、価値観、働き方、社風などを積極的に発信することで、共感してモチベーション高く働いてくれる人材の応募を促せます。
たとえば、SNSやオウンドメディアで社員の働き方やリアルな声を伝えることにより「この会社なら自分らしく働けそう」と感じてもらうきっかけを作ることが可能です。他社との差別化にもつながり、入社辞退や早期退職を防ぐ効果も期待できるでしょう。

入社後の定着率やパフォーマンスにも良い影響を与える傾向があるからこそ、採用マーケティングへの注目度が上がっています。
②採用コストを削減できる
従来の採用では、求人媒体への掲載費や人材紹介会社への紹介料など多くの外部コストがかかっていました。しかし、採用マーケティングでは自社のSNS、オウンドメディア、動画コンテンツなどを活用することで、継続的に自社だけで応募者との接点を作れる仕組みを構築できるのがポイントです。

また、企業の魅力を発信し続けることで潜在的な求職者が自然と関心を刺激するなど「応募したくなる」状態が作れることもメリットとして広がりました。
一時的なコスト削減だけでなく「広告に頼らず人材が集まる仕組みを作る」という点で、採用マーケティングは中長期的に非常にコストパフォーマンスの高い手法と言えるでしょう。
③採用のミスマッチを減らせる
職場のリアルな雰囲気、社員のインタビュー、日々の業務の流れなどを可視化して伝えることで、表面的な情報だけでは分からない「働く現場の空気」を伝えられます。結果、入社後に「思っていた会社と違った」というようなミスマッチを減らし、早期離職のリスクも抑えられるでしょう。
採用のミスマッチが減ると、企業の採用コストを抑えることができるほか、早期退職や内定辞退による求職者への損害も防げるようになるため、双方にとってメリットの高い施策となります。

長期的に活躍する人材を確保する上でも、採用マーケティングは非常に効果的な手法といえるでしょう。
採用マーケティングで生じる課題
採用マーケティングで生じる課題として、主に以下が挙げられます。
- 自社にあった求職者像を正確に定めるのが難しい
- 多様なチャネルを使うため、どの施策が効果的か測定しづらい
- 継続的に魅力的な情報発信を行うためのリソースが必要
- 採用マーケティングの重要性が社内で浸透していない場合、連携が難しい
- 採用ブランディングとマーケティングが分断され、メッセージの一貫性が保てない
- 世代や価値観の違う複数層に向けた柔軟な戦略が求められる
- デジタル施策や外部パートナーの活用に伴うコストがかかる場合がある
採用マーケティングは自社に合った優秀な人材を効率的に獲得し、採用コストの削減やミスマッチの防止を図るなど大きなメリットをもたらします。一方、ターゲット設定の難しさ、効果測定の複雑さ、継続的なコンテンツ制作の負担など、実践にはさまざまな課題も伴うので注意しましょう。

特に社内の理解不足やブランディングとの連携不足が発生すると、施策の効果が十分に発揮されません。
採用マーケティングを成功させるには、起こり得る課題を的確に把握し、戦略的かつ継続的に取り組む姿勢が求められます。
採用マーケティングを成功させるポイント
ここでは、採用マーケティングを成功させるポイントを解説します。
- 継続的にPDCAを回す
- 採用したいターゲット層を深堀する
- 自社の魅力を明確化する
注意点や課題をどうクリアしていくかのヒントにもなるため、ぜひご覧ください。
①継続的にPDCAを回す
採用マーケティングを成功させるためには、PDCA(計画、実行、評価、改善)サイクルを継続的に回すことが不可欠です。採用活動は一度行って終わりではなく、市場環境、求職者のニーズ、社内の状況が変わるたびに柔軟に変えていかなくてはなりません。
具体的には、どのチャネルからどの程度の応募があり、どの施策が効果的だったかを定期的に分析し、改善策を立てて実施する流れを繰り返します。

PDCAサイクルを回すことで限られた予算やリソースを最大限に活かせるようになり、効果的な採用活動がおこなえます。
②採用したいターゲット層を深堀する
採用マーケティングを成功させるためには、単に年齢、性別、職種、スキルセットを絞るだけでなく、以下のような視点をもとに人物像を描きだすことが求められます。
- ターゲットの価値観
- ライフスタイル
- キャリア志向情報の接触経路
たとえば、20代の若手エンジニアをターゲットにする場合、彼らがどのような働き方や職場環境を求めているのか、どんな情報媒体を活用しているのか、またどんな悩みや不安を持っているのかを把握しましょう。

効果的なメッセージや採用チャネルを選定しやすくなり、相手が求める情報を効果的に伝えられます。
③自社の魅力を明確化する
採用マーケティングで成功するためには、自社の魅力を具体的に洗い出し、求職者が共感できるストーリーとして発信できれば、応募者の理解と興味が深まるでしょう。
求職者は数多くの企業の中から働く場所を選ぶため、単に条件面や給与だけでなく企業文化、働き方、成長機会、社風など「自社ならではの特徴」に強く惹かれます。魅力を明らかにしておくことで、より自社の社風に合った人材の確保を行うことが可能です。
また、自社の魅力を明らかにしておくと、応募者の母集団形成だけでなく入社後のミスマッチ軽減や社員のエンゲージメント向上にもつながります。魅力をしっかり打ち出すことで競合他社との差別化ができ、より質の高い人材獲得が期待できるのがポイントです。

採用マーケティングはターゲットや欲しい人材に合わせた施策作りが重要
ターゲットや欲しい人材の特徴に合わせて柔軟かつ戦略的に施策を設計、実行することで、採用の成功確率は飛躍的に高まります。
たとえば、若手の技術者と中堅の管理職では求める情報や接触チャネルが大きく異なるため、一律の方法では効果が薄れてしまうので注意しましょう。若年層にはSNSや動画を活用した親しみやすい情報発信が効果的ですが、経験豊富な管理職には業界専門誌やセミナーでの直接的なアプローチが効果的かもしれません。また、働き方や価値観にマッチしたメッセージを発信しながら応募者の共感を得やすくして、入社後のミスマッチも減らすなど複合的な施策が求められます。

企業の成長を支える優秀な人材を効率的に獲得するためには、ターゲットに合わせた採用マーケティングの重要性をしっかり認識し、実践することが欠かせません。
採用マーケティングに欠かせないフレームワーク4つ
ここでは、採用マーケティングに欠かせないフレームワークを解説します。代表的なフレームワークであり、採用だけでなく一般的なマーケティングにも役立つのでチェックしてみましょう。
- STP分析
- 3CE分析
- AIDMAモデル
- SWOT分析
①STP分析
採用マーケティングにおけるSTP分析では、以下の3項目を主軸に考えます。
1. Segmentation(セグメンテーション)
採用市場を細かく分けること。求職者の属性やスキル、経験、志向、業界などの観点でグループ化します。
例:
- 新卒、中途
- ITエンジニア、営業、マーケティング
- 地域別(東京、大阪など)
- 経験年数別(未経験、5年以上など)
- 働き方の志向(リモート希望、裁量労働希望など)
2. Targeting(ターゲティング)
セグメントの中から、自社が採用したい、または優先的に採用すべきターゲット層を選びます。
例:
- 経験3年以上の営業職
- 20代後半〜30代のITエンジニア
- 新卒で積極的に採用したい大学群の学生
3. Positioning(ポジショニング)
選んだターゲットに対して、自社の魅力や採用ブランドをどう伝えるかを考えます。

ターゲットに響くメッセージや働く環境の特徴を明確にし、他社との差別化を図ります。
例:
- 「最先端技術に携われる環境」
- 「ワークライフバランス重視の職場」
- 「若手が裁量を持つ成長企業」
採用におけるSTP分析は、効果的に欲しい人材を見極めて狙い撃ちし、ターゲットに響くメッセージや環境を作るための戦略設計です。STP分析は求人広告の出し方、面接や選考の進め方、採用ブランディングなどが効率的かつ効果的になります。
②3C分析
採用マーケティングにおける3C分析では、以下の3項目を主軸に考えます。
1. Company(自社)
- 自社の採用ブランド力や魅力、社風、働く環境、福利厚生、教育制度、採用実績などを分析
- 他社と比べてどんな強み、特徴があるかを整理
- 自社の採用課題(例えば、応募数不足、離職率の高さなど)もここで把握する
2. Customer(求職者、ターゲット候補者)
- 採用したいターゲット層(職種、経験、年齢、価値観など)のニーズや志向を分析
- 彼らがどんな働き方やキャリアを求めているのか、どんな情報に触れているのかを理解
- 求職者が重視するポイント(給与、待遇、働きがい、成長機会など)を把握する
3. Competitor(競合企業、他社採用市場)
- 同じターゲット層を狙っている競合企業の採用状況や採用戦略、魅力(給与水準、ブランド力、職場環境など)を調査
- 競合との差別化ポイントや勝ちやすいポジションを探る
上記3つの要素をしっかり理解してバランスをとることで自社の市場でのポジションを強化し、効果的な戦略を立てやすくなるのがポイントです。

3CE分析は「自社の強みを活かしつつターゲットに響くメッセージを作り、競合に勝てる採用戦略」を設計する手法として確立しています。
③AIDMAモデル
採用マーケティングにおけるAIDMAモデルでは、以下の5項目を主軸に考えます。
1. Attention(注意)
- 求職者に自社の求人や情報を認知してもらう段階
- 求人広告、SNS投稿、採用イベントなどで「まずは知ってもらう」ことが目的
2. Interest(関心)
- 求職者が求人情報や企業に興味を持ち、詳しく調べ始める段階
- 会社の魅力、仕事内容、社風や福利厚生の情報を提供し、関心を深めてもらう
3. Desire(欲求)
- 求職者が「この会社で働きたい」と感じる段階
- 社員インタビューや職場の雰囲気紹介、成長できる環境のアピールなどで応募意欲を高める
4. Memory(記憶)
- 求職者の頭の中に企業の魅力や特徴をしっかり印象づける段階
- 他社と比較しても覚えてもらえるよう、独自の強みやメッセージを繰り返し伝える
5. Action(行動)
- 求職者が実際に応募や問い合わせ、説明会参加などの行動を起こす段階
- 応募しやすい環境整備や、スムーズな応募フローが重要
消費者の購買プロセスを表すマーケティング理論を「求職者の採用プロセス」に当てはめた手法として確立しています。

ターゲットとなる人材が今どのフェーズにいるのか、何が不足していて応募につながらないのかを可視化したいときに役立ちます。
④SWOT分析
採用マーケティングにおけるSWOT分析では、以下の4項目を主軸に考えます。
1. Strengths(強み)
自社の採用における強みや優位点。
- 例)魅力的な社風、充実した教育制度、福利厚生の良さ、安定した経営基盤、知名度の高さなど
2. Weaknesses(弱み)
自社の採用活動における課題や不足点。
- 例)採用ブランドが弱い、求人媒体の露出不足、選考プロセスが長い、競合に比べて給与水準が低いなど
3. Opportunities(機会)
外部環境で採用にプラスになる要因。
- 例)特定の業界での人材不足、若手層の増加、テレワーク普及による遠隔地からの採用チャンス拡大など
4. Threats(脅威)
外部環境で採用にマイナスの影響を与える要因。
- 外部環境で採用にマイナスの影響を与える要因。
基本的に「強みを最大限に活かし、弱みを改善、補完しつつ、機会を捉えてチャンスを拡大し、脅威に備えた戦略を立てる」ための分析手法として活用されることが多いです。

自社の強み、弱みだけでなく市場も丸ごと分析できる便利な手法なので、ぜひ活用してみましょう。
効果的な採用マーケティングを実施するなら、フリーコンサルタント.jpにお任せください
「フリーコンサルタント.jp」は、採用マーケティングのプロフェッショナル集団とマッチングできるプラットフォームです。効果的な採用マーケティングを実施したいときは、お気軽に「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください。
企業の強みや魅力をしっかり分析し、最新のマーケティング手法を駆使しながら効果的に理想の人材を引き寄せてくれます。

ターゲットに合わせた戦略設計から実行までをワンストップでサポートできるフリーランスコンサルタントが多数在籍しているのも特徴です。
さらに、コストや社内リソースの課題にも柔軟に対応でき、経験豊富なフリーコンサルタントが企業規模、業界、採用ニーズに応じたカスタマイズ提案も行ってくれます。「良い人材が採れない」「応募が少ない」「採用コストがかさむ」など、採用に関するお悩みをお持ちの企業様にこそおすすめの依頼先であり、SNSやデジタルツールを使った採用マーケティングも実現するのがポイントです。

採用マーケティングの成功事例3つ
最後に、採用マーケティングの成功事例を解説します。
- サイバーエージェント
- マクドナルド
- 株式会社ユーティル
採用マーケティングをどう取り入れてどんな効果があったのか、具体的な事例を知りたい方はチェックしてみましょう。
サイバーエージェント
サイバーエージェントは、若手の優秀な人材を積極的に採用する目的で採用マーケティングを戦略的に活用しています。特徴的なのは「働く環境の魅力」を前面に押し出したブランディングと、デジタルを駆使したターゲットへの情報発信です。
たとえば、同社は自社の社風や社員のリアルな声を動画やSNSで発信し、求職者が働くイメージを具体的に持てるように工夫しています。

オンラインイベントやウェビナーを活用し、場所や時間に縛られず多くの候補者と接点を持つことで応募者数の増加と質の向上を実現しました。
また、社内の成長環境やチャレンジ精神を強調することで「成長したい」「裁量を持ちたい」と考える若手人材の共感を得ています。サイバーエージェントは自社の強みを明確に打ち出し、ターゲットに響くメッセージを届けることで採用マーケティングの成功を収めているのがポイントです。
マクドナルド
マクドナルドは、多様な人材を広く採用するために採用マーケティングを展開しています。特にアルバイトやパートタイマーの採用における「働きやすさ」と「柔軟なシフト制度」を強調したブランディングが特徴です。
大きな特徴として、テレビCMやSNSを活用しながら「学生、主婦、シニア層など誰でも働きやすい職場」というメッセージを分かりやすく伝えていることが挙げられます。また、応募、面接、採用までのプロセスをシンプルかつスピーディーにすることで求職者のストレスを減らし、応募意欲を高める工夫も同時並行で採用しました。
結果、短時間しか働けない主婦層や夕方以降しか出勤できない学生などの取り込みに成功し、人手不足時代であっても豊富な人材を確保できています。

「親しみやすく安心感のある職場環境」というイメージも根付き、紹介による採用も増えているのが特徴です。
株式会社ユーティル
株式会社ユーティルは、IT業界での人材獲得競争が激化する中、採用マーケティングを駆使して自社の魅力を効果的に伝えることに成功しました。
同社は「働きやすさ」と「成長機会の提供」を軸に採用ブランディングを展開し、特に社員インタビューや社内の働く環境を紹介するコンテンツを自社ウェブサイトやSNSで積極的に発信しています。求職者にリアルな職場イメージを届けることで、ミスマッチのある採用や内定時代を徹底的に防ぐことに貢献しました。
また、ターゲット層に合わせたデジタル広告の活用やオンライン説明会を開催し、地理的な制約を超えて幅広い応募者を集めることに成功しているのも特徴です。

選考フローの透明化やスピーディーな対応も求職者から高評価を得ています。
まとめ
採用マーケティングとは、自社に最適な人材を効率的に集めるために、マーケティングの考え方や手法を採用活動に応用する手法です。
- ターゲットの明確化
- 自社の強みを活かした差別化
- 効果的なチャネル選定
- 求職者視点の情報発信
- 選考プロセスの最適化
これらを意識した採用マーケティングにすることで、ミスマッチのない採用と効果的な母集団形成が実現します。
採用の競争が激しい今、自社に合った採用マーケティングを戦略的に導入することは欠かせません。外部のプロフェッショナル人材を頼りたいときや人事コンサルティングを検討しているときは、お気軽に「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください。



-300x189.png)




