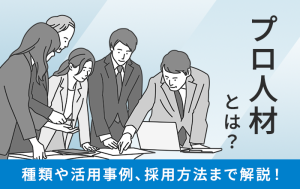企業が外部の専門家に業務を委託する際は「業務委託契約書」が欠かせません。業務委託契約書とは、委託者(自社)と受託者(業務を依頼する企業やフリーランス)の権利義務関係を明確にし、円滑な協業を実現するための重要な法的文書です。理想的な業務委託契約書にできればトラブルを予防できますが、契約に不備があると後々予期せぬトラブルに発展する恐れがあるので注意しましょう。
本記事では、業務委託契約書を作成する際の注意点を解説します。実際のトラブル事例や契約書に盛り込むべき内容にも触れているので、ぜひご参考ください。
■目次
業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、企業が業務を外部の企業や個人に委託する際に作成する契約書です。業務内容、委託期間、報酬、権利義務、責任範囲などを明確にするために使われるのが一般的で、委託前に締結まで完了させる必要があります。
業務委託契約書を用いて委託者と受託者の間で合意した内容を文書化することで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。円滑な業務遂行を促進する他、双方の認識のずれを防いで責任の所在を明らかにできるので、必ず活用しましょう。
業務委託契約書の種類
業務委託契約書の種類は、以下の通りです。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
請負契約とは、成果物の完成に対して報酬を支払う契約です。ウェブサイト制作、システム開発、建築作業など、明確な成果物を作る目的で契約を締結したいときに使われます。
委任契約とは、法律行為に関する業務を委託するときの契約です。弁護士や税理士への法律相談や訴訟代理など、専門性の高い契約を締結したいときに使われます。成果の完成ではなく、業務の遂行自体が報酬の対象となります。
準委任契約とは、法律行為以外に関する業務を委託するときの契約です。システム運用や保守、コンサルティング、デザイン制作、事務代行など、適用範囲が幅広い特徴があります。業務の遂行時間や内容に応じて報酬を支払うのがポイントで、成果物の完成自体を求めるものではありません。
業務委託契約書に記載するべき事項
業務委託契約書に記載するべき事項は、以下の通りです。
- 委託業務の内容
- 委託期間
- 報酬
- 権利義務
- 再委託の可否
- 契約解除
- 損害賠償
- 紛争解決
上記は一般的な項目であり、業務の内容や契約当事者の状況に応じて調整する必要があります。また、契約の種類によっては、成果物の有無や知的財産権の扱い、瑕疵担保責任など、追加で明確にしておくべき事項もあります。
業務委託契約書を作成する際の注意点9つ
ここでは、業務委託契約書を作成する際の注意点を解説します。テンプレート通りに作成するだけでは不足するケースもあるので、以下の基準で業務委託契約書の内容をチェックしていきましょう。
- 契約形態と依頼内容を正確に把握する
- 業務委託契約書の有効期限を事前に確認する
- 報酬の支払い期限を確認する
- 経費の支払い範囲を確認する
- 納品や検収の期間を確認する
- 受託者が不利になる条項がないか事前にチェックする
- 契約解除の要件を確認しておく
- 再委託について確認しておく
- 禁止事項を事前に記載しておく
①契約形態と依頼内容を正確に把握する
業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の形態があり、契約形態に応じて法的性質や責任範囲が異なります。万が一トラブルが起きた際にどのように対処するのか、責任はどちらにあるのかを明確にするためにも、契約形態と依頼内容は明記しておきましょう。
依頼内容については、委託する業務の範囲や内容、作業範囲を曖昧にせず、詳細に記述します。「〇〇に関する業務全般」といった抽象的な表現は避け、具体的な作業内容を列挙したり、別紙で仕様書などを添付したりすることが望ましいです。
また、成果物の納品を伴う場合は、仕様、形式、品質基準などを具体的に定義しておきましょう。認識のずれを防ぐために、可能な限り詳細な情報を盛り込んでおくとトラブルを予防できます。
②業務委託契約書の有効期限を事前に確認する
業務委託書の有効期限を明確に定めておくことで、納品までのタイムリミットが明確になります。そのため、取引が滞るのを防止することが可能です。また、契約上の義務の存続期間が明確になるため、取引中に契約違反が起きた際の責任の所在も明白になります。
業務委託契約書の有効期限を記載する際は「〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで」のように明記しましょう。加えて、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるかどうか、更新される場合の期間や条件を明記しておくことも大切です。「双方からの異議申し立てがない場合に更新」「同一条件で〇年間更新」などわかりやすく記載しておくことで、継続的な業務も依頼しやすくなります。
なお、継続的な契約を前提としていた場合でも、社会情勢の変化や自社の収益状況によって途中終了となってしまうことも多いです。契約を取りやめるときの項目についても盛り込み、トラブルを予防しましょう。
③報酬の支払い期限を確認する
報酬面は特に揉めやすいポイントでもあるため、業務委託契約書に必ず盛り込んでおきましょう。特に、支払い期限を明確に定めることは、金銭トラブルを未然に防ぐことにつながります。「毎月末日」「納品月の翌月末日」など具体的な日付を決める他「月払い」「一括払い」「分割払い」など報酬が支払われる頻度も記載しておくのがおすすめです。
また、銀行振込、現金払いなど具体的な支払い方法を指定し、振込先口座情報なども収集しておきましょう。
④経費の支払い範囲を確認する
業務を遂行する上で、交通費や通信費、材料費、宿泊費などの経費が発生する可能性があります。経費の負担範囲が曖昧な場合、どちらが費用を負担するべきかで意見の対立が生じて金銭トラブルに発展する可能性が高いです。
具体的には、経費をどちらが負担するのか、どこまでの範囲の経費が支払われるのかを明確にしておきましょう。経費の精算方法や申請方法、支払い上限額、支払い時期も盛り込んでおくとわかりやすくなります。
双方が安心して業務に集中できる環境を作るためにも、経費の支払い範囲を確認しておくことが欠かせません。
⑤納品や検収の期間を確認する
納品や検収の期間が不明瞭だと、希望納期までに成果物が届かなかったり、支払いトラブルに発展したりしてしまう可能性があります。請負契約のように成果物の納品を伴う業務委託においては、納品期限と検収期間を明確に定めておきましょう。いつまでに、どのような形式で納品するのか、具体的な日付や時間で明記します。段階的な納品がある場合は、各納品物の期限と内容をそれぞれ記載しておきましょう。
同様に、検収期間も明確に定め「納品後〇日以内」のように具体的な日数で記載します。どのような基準で成果物が合格と判断されるのか、どのように検収を行うのかまで盛り込んでおけば、双方の認識相違も避けやすくなります。
⑥受託者が不利になる条項がないか事前にチェックする
受託者が不利になる条項がないかも、事前にチェックしておきましょう。業務委託契約を締結する際は、どうしても委託者が強くなりがちです。自社の要望ばかりを通そうとして業務委託契約書の内容を受託者にとって不利なものにしていた場合、契約書が原因で取引に進まなかったり、知らず知らずのうちに法に抵触していて後々トラブルに発展してしまったりする可能性があります。
安心して取引を進めるためにも、特に以下の項目には注意することをおすすめします。
知的財産権
知的財産権とは、知的創造活動によって生み出された著作物について保護する権利のことです。「著作権」と似ていますが「著作」が文章やデザイン、音楽など具体的な著作物を指すのに対し「知的財産」はアイディアや商標、発明を含む幅広い著作物を指します。
受託者が提供した知的財産を正当な対価なしに委託者に一方的に帰属するような条項は、受託者にとって大きな不利益となる可能性があるので注意が必要です。知的財産が委託者と受託者のどちらに帰属するのか明確に定める他、利用方法や知的財産を委託者に帰属させる場合の報酬についても明確に取り決めておきましょう。
損害賠償
損害賠償とは、相手に損害を与えた企業や者が、被害者に損害を補填するために支払う料金です。契約不履行や業務遂行上のミスなどによって相手方に損害を与えてしまった場合、どのような範囲で、どの程度の賠償責任を負うのか取り決めましょう。「直接的な損害」に限定されているか「逸失利益」や「弁護士費用」など間接的な損害まで含まれるのかによって、賠償額が大きく変わります。
また、損害賠償の金額に上限が設定されているか、賠償額が相場から大きく逸脱しすぎていないかもチェックしましょう。受託者の故意または重過失による場合に限定する、など責任範囲を狭めるのもおすすめです。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、成果物が理想の状態に到達していないとき、受託者に追求できる責任のことです。まずは、契約不適合責任の対象となる範囲が広すぎないか確認しましょう。
受託者の責めに帰すべからざる事由による不適合まで責任を負わされるような条項は不当であり、自社が損害賠償によるダメージや契約解除のリスクを抱えることになるため注意が必要です。
また、受託者の責任を免除する条項が全くない、または免責範囲が極めて狭い場合、契約提携が難しくなってしまう恐れがあります。受託者は不当に高い損害賠償を支払うなど、過大な責任を負う可能性があるため、契約時の条項を詳細にチェックする方も多いです。契約不適合責任に関する条項を明確に定め、委託者、受託者双方のリスクを適切に管理しましょう。
⑦契約解除の要件を確認しておく
予期せぬ事態が発生した場合に備え、契約解除の要件を確認することも大切です。どのような場合に契約を解除できるのかを具体的に列挙したり、契約を解除する際の手続きや契約解除料について取り決めを交わしておきます。債務不履行の場合、直ちに解除できるのか、それとも相当の期間を定めて履行を催告するのかなど、細かな点を盛り込むのも良いでしょう。
契約解除の要件を確認しておいた場合、委託者は、受託者に問題があった場合に早期に契約を解除し、代替の依頼先を探せるようになるメリットがあります。受託者にとっては、委託者の都合による一方的な解除から身を守るための規定となるため、双方のためにも必ず業務委託契約書に盛り込んでおきましょう。
⑧再委託について確認しておく
再委託とは、業務の全部または一部を第三者(再委託先)に委託することを指します。自社の情報が第三者に渡る可能性も考えられるため、事前に再委託の可否を取り決めておくことが重要です。
具体的には、受託者が自由に再委託できるのか、原則として禁止するのか、または委託者の事前の承諾を必要とするのかを明確に記載しておきましょう。再委託を認める場合、再委託先の行為については受託者が責任を負うとされることが多いです。再委託が禁止される業務範囲や、特定の事業者への再委託を禁止する場合があれば、こちらも業務委託契約書に盛り込んでおきましょう。
⑨禁止事項を事前に記載しておく
委託業務の遂行にあたり、受託者が行ってはならない行為や、遵守すべき事項を明確に定めておきましょう。禁止事項を明確にしておくことで、反社会的勢力との関わりや個人情報、機密情報の漏洩など、様々なリスクを回避できます。
予期せぬトラブルを未然に防ぎ、事業の継続性を確保する意味でも効果的です。
業務委託契約を締結する際の注意点3つ
ここでは、業務委託契約を締結する際の注意点を解説します。本格的に業務委託契約を締結する前に、以下の項目について確認しましょう。
- 信頼できる取引相手か見極める
- 法律を遵守できているか意識する
- 偽装請負や下請法に抵触しないよう注意する
①信頼できる取引相手か見極める
誠実で責任感のある相手を選ぶことで、長期的なパートナーシップを築き、業務委託を成功させることができます。逆に信頼できない相手と業務委託契約を締結した場合、取引期間中も不安を感じながら業務を進めることになるほか、業務の進行が遅くスケジュールに影響が出る可能性もあるため、健全な状態とは言えないでしょう。
信頼できる取引相手か見極めるためには、受託者の過去の業務実績や顧客からの評価、業界内での評判などを確認するのがおすすめです。ポートフォリオや推薦状の提出を求めたり、面談やヒアリングを通じて判断したりする方法もあります。特に長期にわたる契約や高額な報酬が発生する場合は、受託者の財務状況が安定しているかを確認することも検討してよいでしょう。
②法律を遵守できているか意識する
業務委託契約書が法律を遵守できているか、受託者の事業活動を不当に制限するような条項がないか、意識してチェックしてみましょう。委託者の優越的な地位を利用して不当に低い報酬で業務を委託したり、不利益な条件を一方的に押し付けたりする行為は、独占禁止法に違反する可能性があります。
また、業務委託において個人情報を取り扱う場合、委託者、受託者双方に適切な安全管理措置を講じる義務があります。個人情報の取り扱いに関する明確な条項を盛り込むなど工夫し、双方による情報保護に努めましょう。
③偽装請負や下請法に抵触しないよう注意する
実質的に労働者を指揮命令して働かせているにもかかわらず、雇用契約ではなく業務委託契約を締結する「偽装請負」は、労働基準法や職業安定法などに違反する違法行為です。実態として指揮命令関係を伴う労働契約になっていないか確認し、そもそも本当に業務委託契約で良いのか検討しましょう。
下請法が適用されるかどうかは、親事業者と下請事業者の資本金によって異なります。下請法が適用される場合は、下請法の規定を遵守した契約内容にすることが重要です。違反した場合、公正取引委員会からの指導や勧告、さらには罰則が科される可能性もあるので注意しましょう。
業務委託契約書に収入印紙と割印は必要?
ここでは、業務委託契約書に収入印紙と割印が必要か解説します。法的効力を持つ業務委託契約書にするためにも、以下のポイントを抑えておきましょう。
- 収入印紙は契約金額によって必要になる
- 特に重要な書類には割印が必要
収入印紙は契約金額によって必要になる
収入印紙は、紙で作成された業務委託契約書であり、かつ契約内容が印紙税法上の課税文書に該当する場合に貼付が必要です。請負に関する契約書であれば、契約金額が1万円の場合は不要、1万円以上100万円以下であれば200円、100万円以上200万円以下であれば400円、と収入印紙の税額が変動するので注意しましょう。
なお、委任契約や準委任契約であれば、原則として収入印紙は不要です。また、電子で作成、締結された業務委託契約書の場合も、収入印紙代はかかりません。
特に重要な書類には割印が必要
割印とは、収入印紙の再利用を防ぐため、貼り付けた収入印紙と契約書にまたがるように押印することです。印紙税法第8条において収入印紙を消印することが定められており、その方法として印章または署名による割印が認められています。
収入印紙を貼り付けただけで割印(消印)がない場合、印紙税を納付したと認められず、過怠税が課される可能性があるので注意しましょう。契約書に収入印紙の貼付が必要であるにもかかわらず貼付しなかった場合も、過怠税が課されます。
業務委託契約のよくあるトラブル
業務委託契約のよくある代表的なトラブルとして、以下が挙げられます。
- 業務範囲、内容の不明確さによるトラブル
- 報酬の支払いに関するトラブル
- 成果物、納品物に関するトラブル
- 権利、義務に関するトラブル
- 偽装請負に該当するトラブル
- 再委託に関するトラブル
トラブルを未然に防ぐためには、契約書を明確かつ詳細に作成することが最も重要です。業務内容、納期、報酬、権利義務、契約解除の条件などを具体的に記載し、双方が内容に合意したうえで作成しましょう。また、契約締結前に取引相手の信頼性を確認することや、業務遂行中のコミュニケーションを密に取ることもトラブル回避に繋がります。
以下の記事では、業務委託のトラブルについて具体例をもとに詳しく解説しているので合わせてチェックしてみてください。
業務委託のトラブル事例5選|トラブル回避のための注意点や対策を解説
業務委託契約書の作成する方法とポイント
業務委託契約書を作成する際のポイントとして、以下をご参考ください。
- 曖昧な表現を避ける
- 予期されるリスクを考慮する
- 対等な立場で協議する
- 必要に応じて専門家の意見を求める
- 締結前に確認を徹底する
- 関連資料を添付する
- 契約期間と業務内容に見合った内容にする
- 下請法を意識する
業務委託契約書を作成する際は、必須項目を網羅した内容にする他、双方が納得できる条件になるよう、気持ちに配慮して作成することが大切です。一方的にどちらかに不利な条件ではなく、双方が納得できるバランスの取れた内容にすることで、相手からの信頼を得やすくなります。気持ちよく契約を締結できれば、その後の業務遂行におけるコミュニケーションも円滑に進むでしょう。短期的な利益だけでなく、長期的な視点で良好な関係を築くことができれば、継続的な協業や新たなビジネスチャンスに繋がる可能性が高まります。
コンサルティング人材をお探しの場合「フリーコンサルタント.jp」にお任せください
「フリーコンサルタント.jp」はフリーランスコンサルタントを紹介するマッチングサービスです。
専門スキルや実務経験を持つフリーランス人材と直接コミュニケーションを取れるため、自社のニーズに合致した専門性を持つ人材を見つけやすいのがメリットです。プロジェクト単位、時間単位など、業務の量や期間に応じて柔軟な契約形態を選択できるので、フレキシブルに活用することもできます。
また「フリーコンサルタント.jp」を通してマッチングした専門的な人材に仕事を任せることで、トラブルを未然に防げるのもポイントです。自社だけでは気づかなかった落とし穴やリスクを指摘してもらうこともでき、より柔軟で多様な仕事ができるようになります。業務委託できる人材をお探しの方は、ぜひ「フリーコンサルタント.jp」をご活用ください。
まとめ
業務委託契約は、委託者と受託者双方のリスクを低減し、気持ちよく仕事ができるようにする道具として活用できます。契約期間の始期や終期、自動更新の有無などを明確にする他、秘密保持、競業避止、不正行為など遵守すべき事項を定めておきましょう。
なお「フリーコンサルタント.jp」では、業務委託できる専門人材をご紹介しています。その他、業務委託の管理をできるフリーランスも多数在籍しているので、業務委託の数が多い企業にもおすすめです。お困りの方は、以下からお気軽に「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください。