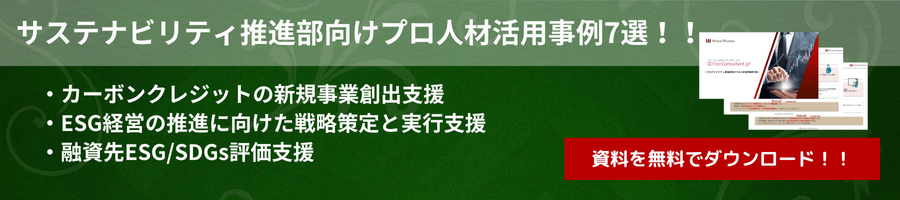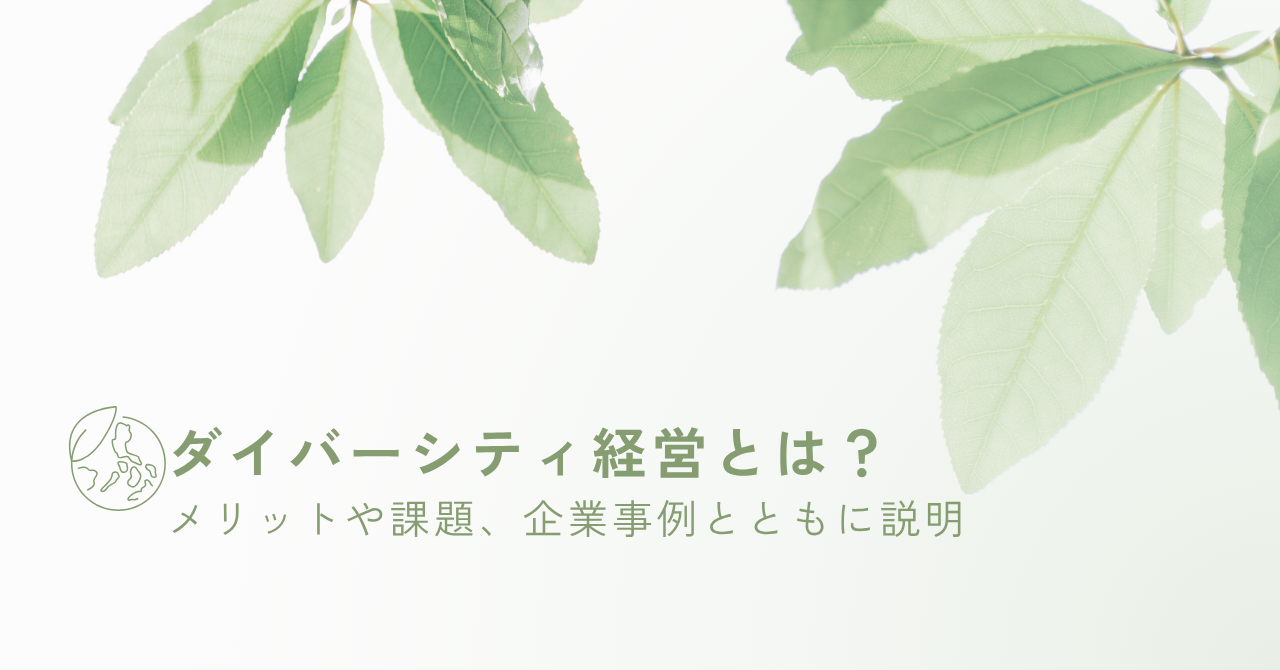
今、多くの企業でダイバーシティ経営が求められています。
ダイバーシティ経営とは、多様な人材を活かし、イノベーションを生み出す経営方法です。ダイバーシティ経営に取り組むことで、人材確保や企業価値の向上など、さまざまなメリットをもたらします。日本政府もダイバーシティ経営を推進しており、今後ますます取り組む企業は増えるでしょう。
本記事では、ダイバーシティ経営のメリットや課題について解説しながら、企業の取り組み事例について紹介します。
■目次
ダイバーシティ経営とは?
まずは、ダイバーシティ経営の意味や定義をみていきましょう。
ダイバーシティとは「多様性」「相違」
ダイバーシティ(diversity)は、日本語で「多様性」や「相違」を表す言葉です。性別、年齢、価値観など、さまざまな属性を持つ人々が共存することを指します。
ダイバーシティの考え方は、1960年代のアメリカで起きたアフリカ系アメリカ人の公民権運動をきっかけに広まりました。当時、ダイバーシティは性別や国籍などの特定の差別に対する多様性として知られていましたが、現在ではライフスタイルや価値観、趣味なども含む幅広い多様性を表す言葉として定着しています。
また、ビジネスにおいてダイバーシティは、性別、年齢、国籍、職業歴(キャリア)、価値観など集団間の多様性を指します。
経済産業省による定義
経済産業省は、ダイバーシティ経営を以下のように定義しています。
”多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営”
引用:ダイバーシティ経営の推進|経済産業省
企業が年齢や性別、障害の有無、キャリア、働き方などあらゆる多様性を尊重しながら、その人が持つ潜在的な能力・特性などを活かした経営を行うことで、生産性の向上や社内の競争力強化につながるとしています。ダイバーシティ経営は、持続的な会社経営において、重要な考え方といえるでしょう。
ダイバーシティ経営が注目される理由
ダイバーシティ経営が注目されるようになった主な理由は、次の2つです。
近年、市場のグローバル化が急速に進み、海外企業との競争もますます激化しています。こうした環境の中で企業が持続可能であるためには、社内にさまざまな価値観を取り入れ、イノベーションを起こしていくことが重要です。
また、日本では少子高齢化が加速しており、労働力不足が大きな経営課題となっています。この課題を解決するためには、年齢や国籍を問わず人材を受け入れ、労働力の総数を増やす必要があります。その方法の一つがダイバーシティ経営です。
ダイバーシティ経営によるメリット・効果
企業がダイバーシティ経営に取り組むと、以下のようなメリットや効果が期待できます。
優秀な人材を確保できる
一つ目のメリットは「優秀な人材を確保できる」ことです。
性別や年齢、人種、国籍、働き方などの多様性を受け入れることで、労働人口を増やすことが可能です。労働人口が増えれば、その中から優秀な人材を確保しやすくなります。
また、多様性を重視することで、若手人材の確保にもつながります。例えば、ミレニアル世代(1981年から1996年頃の生まれ)やZ世代(1990年代後半から2012年頃の生まれ)は、多様性や公平性を重視する傾向です。そのため、ダイバーシティ経営への取り組みをアピールすることは、若者へのアプローチとして非常に有効といえるでしょう。
グループシンクによるリスクの分散
ダイバーシティ経営は、グループシンクによるリスクの分散にも効果的です。
グループシンク(集団思慮)とは、集団での意思決定時に批判的な意見を避けたり、自分の意思とは異なる意見に賛同したりしてしまう現象のことです。その結果、判断能力が損なわれ、不合理な結論となる場合があります。
しかし、ダイバーシティ経営を導入すると、社内に多様な価値観や視点が生まれるため、グループシンクを防ぎやすくなり、多面的な議論が可能となります。
生産性の強化・向上
さまざまな知識や経験、価値観が掛け合わさることで、新たなアイデアが出やすくなります。製品やサービスの開発・改良だけでなく、製造や物流、販売手段といった分野でもイノベーションが起こりやすくなることを意味します。また、働き方やライフスタイルの尊重により、長時間労働などの職場環境の問題も改善されるでしょう。
これらの改革により効率性や創造性が高まれば、企業は生産性をより強化・向上させることができます。
企業価値の向上
ダイバーシティ経営は、企業価値の向上につながります。
個性の尊重や多様な価値観の受け入れは、社会のニーズに応えることであり、投資家や顧客はそのような経営をする企業を評価します。また、事業を継続し、収益を維持するためにも、ダイバーシティは必要不可欠といえるでしょう。
さらに、「社員一人ひとりの個性を重視する」という経営方針は、社員の満足度向上にも効果的です。
ダイバーシティ経営における課題・対策
ダイバーシティ経営にはさまざまなメリットがありますが、一方で課題も存在します。
ここでは、ダイバーシティ経営を進める際に企業が抱えやすい課題とその対策を紹介します。
経営者・社員のダイバーシティ経営への理解
ダイバーシティ経営は、取り組んだからといってすぐに効果が出るものではありません。また、直接的な利益につながりにくいため、経営者や株主からの理解を得るのが難しい場合が多いでしょう。
しかし、経営者が意欲的に取り組まなければ、ダイバーシティ経営は実現できません。長期的な視点でどのようなメリットがあるのか、社会のニーズを交えながら説明し、理解してもらうことが大切です。
さらに、これまで組織の統一性を重視してきた企業では、ダイバーシティへの理解が進んでいない場合があります。社員一人ひとりの意識をすぐに切り替えるのは簡単ではありません。そのため、まずはダイバーシティについての研修や勉強会を行うなど、理解を深めるところから始めるとよいでしょう。
多様性を活かすための社内環境づくり
多様性を受け入れづらい社内環境になっている企業も少なくありません。
ダイバーシティ経営とは、多様な人材を採用し、個人の特性を活かした経営方法です。そのためには、採用した人材がパフォーマンスを発揮しやすい人事制度や働き方を整備することが必要です。例えば、リモートワークやフレックスタイム制度の導入、多言語への対応、バリアフリー化などが挙げられます。
どのような人材を採用し、どのような働き方や制度が必要なのかを考えることが大切です。また、現場で働く社員にも配慮しつつ、社内環境を整えていくことが重要です。
心理的安全の確保
心理的安全性とは、自分の意見や考えを集団の中で安心して表現できる状態のことです。たとえ周囲と異なる意見を述べた場合でも、拒絶されたり非難されたりする心配がないと確信できることも、同じく大切です。
ダイバーシティ経営によって多様な価値観が集まると、さまざまな角度からの意見が出やすい反面、特定の価値観に対して批判が集まる場合もあります。
心理的安全性を高めるには「社員全員が安心して発言できる雰囲気をつくる」「失敗が許容される風土を育てる」「豊富なコミュニケーションの機会を設ける」などが重要なポイントです。
経済産業省による取り組み
日本政府は、企業の競争力を強化し、最終的には日本経済が持続的に成長するために、ダイバーシティ経営の推進が不可欠だと考えています。
ダイバーシティ経営推進のため、経済産業省ではさまざまな取り組みを行っており、ここではその中から2つの主な取り組みを紹介します。
「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」の公表
「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」は、企業の取締役会、社長・CEOなどの経営層、そしてダイバーシティ経営担当者に向けたレポートです。このレポートは、2024年11月より実施されている「多様性を競争力につなげる企業経営研究会」での議論を踏まえ、取りまとめられています。
本レポートでは、「企業の競争力を強化するための手段として多様性を推進する」という観点で、国内企業がダイバーシティ経営に取り組む際に直面する課題と必要となるアクションを提示しています。また、ダイバーシティ経営の基本的な考え方や導入事例、必要なアクションが分かりやすくまとめられているのが特徴です。
参考:企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)|経済産業省
なでしこ銘柄
「なでしこ銘柄」とは、女性の活躍を積極的に推進している上場企業を選定する取り組みです。平成24年度から、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施しています。
この「なでしこ銘柄」は、中長期的に企業価値の向上を重視する投資家にとって、魅力的な投資先として紹介されます。これにより、各企業が女性の活躍をさらに進めることを目指しています。
選考では「『採用から登用までの一貫したキャリア形成支援』及び『共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援』に関する取組・成果が、どちらも優れていること」「経営戦略と女性活躍を含む人材戦略との結びつき、それによる企業価値向上が自社独自の
ストーリーとして語られていること」の2点を重視。これらの基準をもとに、最大30社選出されています。
参考:女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」|経済産業省
経産省による「企業がすべき具体的アクション」
ダイバーシティ経営に取り組もうと思っても、何から始めていいか分からない企業もあるでしょう。そのような場合には、経済産業省が公表している「企業に求められる具体的アクション(ダイバーシティ2.0行動ガイドライン)」が参考になります。
このガイドラインは、前章で紹介した「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」に付属する資料です。ここには、企業がダイバーシティ経営を実践する上で必要なアクションをまとめています。
参考:ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン
企業に求められる具体的アクション(ダイバーシティ2.0行動ガイドライン)新旧対照表|経済産業省
他にも、ダイバーシティ経営を理解するためのワークショップ「ダイバーシティ・コンパスワークショップ」や「リーフレット」「ダイバーシティ経営診断ツール」なども利用できます。
参考:ダイバーシティ経営の推進|経済産業省
企業によるダイバーシティ経営の取り組み事例
最後に、企業が実践しているダイバーシティ経営の具体的な取り組み事例を紹介します。
BIPROGY株式会社
BIPROGY株式会社(旧日本ユニシス株式会社)は、企業理念を実現していくための基本的な考え方の一つとして「多様性の受容と獲得」を掲げています。
2024年には、社内から初めて女性取締役が登用されました。また、法定以上の産休・育休、短時間勤務、テレワーク制度、フレックスタイム制度なども整えられています。加えて、これらの制度では同性パートナーも配偶者と同じように扱われます。
参考:WORK STYLE 変化に柔軟な働き方|BIPROGY株式会社
大橋運輸株式会社
大橋運輸株式会社は、社員一人ひとりの特性を活かす経営を目指し、10年にわたって制度の整備や組織づくりを取り組んできた企業です。
同社では、女性をはじめ外国人、障害者、LGBTQなど、さまざまな人材を積極的に雇用しています。また、日本語に不慣れな海外出身の社員には、通訳となる社員をつけてコミュニケーションをフォローしたり、年に1回、里帰りのための渡航費用の補助なども行ったりしています。
カンロ株式会社
のど飴やグミのメーカーとして知られるカンロ株式会社は、2018年に「ダイバーシティ推進室」を立ち上げ、社員のニーズに合わせたさまざまな取り組みを実施しています。
例えば、フレックスタイム制度やテレワーク制度、リモート転勤制度などを導入し、時間と場所にとらわれない働き方を実現しました。また、育児休業を希望する社員が100%取得できるよう「育休サポート100」というスローガンを掲げ、子育てと仕事の両立を目指す社員を積極的に支援しています。
ダイバーシティ経営に取り組むなら「フリーコンサルタント.jp」へご相談ください
ダイバーシティ経営は、多様な人材を活かすことでイノベーションを生み出します。しかし、どのような取り組みが必要かは、社員の特性や今後どのような社員を採用していくかによって異なります。
「何から取り組めばよいか分からない」「今の取り組みが正しいのか知りたい」などのお悩みは、「フリーコンサルタント.jp」へお任せください。
「フリーコンサルタント.jp」には、大手コンサルティングファーム出身者をはじめ、経験豊富なプロフェッショナルが多数登録しています。多様な業界や分野の専門家が在籍しているため、企業ごとの課題やニーズに合った最適なコンサルタントを見つけられます。カーボンネガティブの推進だけでなく、経営戦略、マーケティング、IT、人事など、幅広い分野のコンサルティングにも対応可能です。
まとめ
投資家や顧客は、企業がダイバーシティ経営に取り組んでいるかどうかに注目しています。ダイバーシティ経営は、企業と社会の持続可能な成長のために、必要不可欠といえるでしょう。
企業がダイバーシティ経営を進める際には、社内外の理解を得られるように説明し、社員一人ひとりのニーズに合わせた社内環境を整えることが重要です。
「フリーコンサルタント.jp」には、ダイバーシティ経営に関する専門家が多数在籍しています。これからダイバーシティ経営を始めたい方はもちろん、すでに実施されている内容の見直しや改善についてもサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。