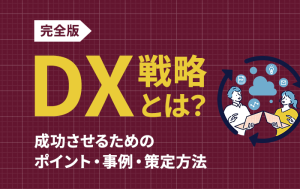「DX人材」とは、デジタル技術とビジネスへの深い造詣を武器に、企業の変革を推進する専門人材です。変化の激しい現代で企業が競争優位性を確立するためにはDXが不可欠であり、企業が成長するかはDX人材の確保にかかっていると言っても過言ではありません。
しかし、多くの企業でDX人材が不足しているのが現状です。この記事では、DX人材に求められるスキルやマインドセット、DX人材確保方法などを解説します。自社に最適なDX人材を採用するための具体的なヒントとなれば幸いです。
■目次
DX人材とは

DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、IT技術を用いて生活やビジネスを変革していくことを指します。DX人材は、このDXを推進するために必要なスキルやマインドセットを備えた人材のことです。
DXは企業の一部署だけではなく、社全体を巻き込む事業です。そのため、単にデジタル技術に精通した人材を確保するだけでは不十分です。部署をまたいでスムーズにDXを推進するには、事業・技術・経営の3つの観点に通ずるDX人材が求められます。
ただし、すべての素養を満たすDX人材を確保・育成するのは難しいため、3つの役割を1つのチームで分担している場合がほとんどです。
DX人材が求められる背景
近年、あらゆる産業で、デジタル技術を利用した新しいビジネスモデルが生まれています。このような環境下で競争力を維持・強化していくためには、DXをスピーディーに進めていかなければなりません。
DXを推進することで、業務の効率化や顧客満足度の向上を図れるほか、企業の競争力も高められるでしょう。
しかし、IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2021」によると、DXに取り組んでいる企業は調査に回答した企業のうち約56%にとどまっています。DXが進まない背景として挙げられるのは、ITやDXに詳しい人材を確保・育成できる環境が整備されていない現状です。
継続的なDX推進には、一定の内製開発力(社内開発力)を備えることが望ましいとされています。DXが求められる環境下で、DXを担えるDX人材が求められているのです。
出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX 白書 2021」
各業界で採用、育成するべきDX人材一覧表
一言でDX人材といっても、求められるスキルや役割は企業の目的や業界によって大きく異なります。なぜなら、既存業務の効率化を目指すのか、新しいビジネスモデルの開拓するのかなど、目指すゴールによって必要なDX人材が変わるからです。
各業界ごとに採用、育成するべきDX人材を、以下の表にまとめました。
| 業界 | DXの主な目的 | 求められるDX人材 |
|---|---|---|
| 製造業 |
|
|
| 小売業 |
|
|
| 金融業 |
|
|
| 建設業 |
|
|
※BIM/CIMとは、3次元モデルに様々な情報を紐づけて管理する手法
このように、自社の事業内容とDXのゴールを照らし合わせることが、最適な人材を確保するために重要です。
IPAが定義しているDX人材の7つの職種とサポート内容

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、企業がDXを強力に推進できるよう、専門的な役割を持つ7つの職種を定義しています。
上記の職種は、デジタル技術を扱うだけでなく、ビジネスの変革を主導し、企業全体のデジタル化をサポートする重要な役割を担います。それぞれの専門性を持つ人材が連携することで、DXを成功させるための基盤が整備されるのです。ここからは、7つの職種について詳しく見ていきましょう。
①プロダクトマネージャー
プロダクトマネージャーは、デジタル事業の実現を主導するリーダー格の存在です。
プロダクトとは、企業が販売する製品やサービスを指します。プロダクトマネージャーの役割は、このプロダクトの管理です。具体的には、市場分析やターゲット選定、商品開発といった上流工程から、実際にプロダクトを販売するためのマーケティング戦略立案やブランド管理といった下流工程まで、幅広く担ってくれます。
プロダクトに関する幅広い事項に携わるため、プロダクトマネージャーには課題設定力や実行力、調整力などを兼ね備えた人材を採用すると良いでしょう。
②ビジネスデザイナー
ビジネスデザイナーは、デジタル事業(マーケティングを含む)の企画・立案・推進などを担う人材です。
製品やサービスの質がどれだけよくても、それが顧客に伝わらなければ利益にはつながりません。製品やサービスを販売するためのビジネスモデルを設計するのが、ビジネスデザイナーのおもな役割です。ビジネスデザイナーは、ビジネスの成否を左右する存在といえるでしょう。
ビジネスデザイナーには、ビジネスと技術の両方に関する知識や発想力、ファシリテーション能力が求められます。ビジネスへの深い理解が必要なビジネスデザイナーには、自発的に行動して仕事ができる人が向いています。
③テックリード
テックリードは、デジタル事業に関するシステムの設計から実装までを担い、他の部署との窓口にもなってチームをリードする人材です。エンジニアリングマネージャー、アーキテクトとも呼ばれます。
また、テックリードはエンジニアのまとめ役でもあるため、社内のエンジニアから登用したり、外部から経験者を雇用したりして確保されます。
④データサイエンティスト
データサイエンティストは、事業・業務に精通したデータ解析・分析ができる人材です。IT業界だけでなく、あらゆる業種で必要とされるデータサイエンティストの存在は、事業の正しい運用・改善にも欠かせません。
データサイエンティストには、統計学の知識やプログラミングスキル、ビジネススキルなどが必要です。
⑤先端技術エンジニア
先端技術エンジニアは、機械学習やブロックチェーンなどの先進的なデジタル技術を持った人材です。
企業を取り巻く環境は常に変化しているため、DXで変革をしたあとも、常に環境に合わせた変革が求められます。最先端の技術は未発達で変化も大きく、先端技術に対応するためには専用の知識を持ったエンジニアが必要です。
先端技術エンジニアには、先進技術を自ら学び取り入れる能力が求められます。好奇心旺盛な人や、新しい技術を抵抗なく吸収できる人が、先端技術エンジニアに向いているでしょう。
⑥UI/UXデザイナー
UI/UXデザイナーは、デジタル事業に関するシステムのユーザー向けデザインを担当する人材です。
UIはユーザーインターフェース、UXはユーザーエクスペリエンスのことを指し、これらは相互に結びついています。この2つの質を向上させることで、より快適かつ魅力的なサービスをユーザーへ提供できるようになるのです。
UIデザイナーは機械やソフトウェアなどUIをデザインし、UXデザイナーはユーザーの体験をデザインするのが役割です。
UI/UXデザイナーには、デザインに関する知識やスキル、コミュニケーションスキル、ブランディングの知識が求められます。
⑦エンジニア/プログラマー
エンジニアとプログラマーは、デジタル事業に関するシステムの実装やインフラ構築、保守・運用、セキュリティなどを担う人材です。
DXの技術面の根幹を担う職種であるため、エンジニア/プログラマーには高度なプログラミングやエンジニアリングの能力が求められます。
企業がDX人材に求めるべきマインドセットとは?

DXを推進する人材には、専門スキル以上に、変化を恐れずプロジェクトを前進させるマインドセットが重要です。DXは計画通りに進むとは限らないため、予期せぬ事態にも粘り強く対応する姿勢が欠かせません。
IPAの調査でも、DX人材には以下のようなマインドセットが重要視されています。
- 全職種共通:状況に応じて計画を変更できる「臨機応変な対応力」
- リーダー層:社内外の関係者をまとめる「巻き込み力」や未来を描く「創造力」
- 技術職:困難な課題に直面しても解決策を探る「突破力」
役割によって求められる要素は異なりますが、共通して言えることは失敗を恐れずに挑戦し続ける主体性です。
DX人材に必要なスキル
企業がDX人材を採用、育成する際、高度なITスキルに目を向けがちですが、それだけでは不十分です。DXの本質は、デジタル技術を「活用して」ビジネスを変革することにあります。そのため、技術力に加えて、ビジネスへの深い理解と組織を動かす力を兼ね備えた人材が欠かせません。
企業が求めるべきスキルは、以下の3つです。
- デジタルリテラシー:先端技術を自社の課題解決や価値の創造に応用する力
- ビジネス理解力:デジタル化すべき課題を発見する力
- 推進力:部署の垣根を越え、プロジェクトを最後までやり遂げる力
DXを成功させるには、3つのスキルをバランス良く持っている人材の確保、育成が重要です。
DX人材に対する各企業の課題
多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、担い手であるDX人材の確保に頭を悩ませています。実際、IPAの調査では、約9割の企業がDX人材の「量」または「質」に不足感を抱いていると回答しました。
DXにおける深刻な人材不足を解消するには「採用」「育成」「外部活用」の3つのアプローチを、自社の状況に合わせて戦略的に組み合わせることが重要です。
次項より詳細に解説していきます。
出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX 白書 2021」
DX人材を確保する3つの方法

ここからは、それぞれの方法における具体的な課題と解決策を解説します。
①DX人材を採用する
DX推進の即戦力として外部からの人材登用は魅力的ですが、採用の難易度は年々高まっているのが現状です。全業界でDX化が叫ばれる中、優秀な人材の獲得競争は激化しており、経済産業省は2030年に最大約79万人のIT人材が不足すると予測しています。
特に、ビジネスとデジタルの両面に精通したDX人材は希少な存在です。多くの企業が以下のような現実に直面しており、候補者が企業を選ぶ「売り手市場」になっています。
- 高い報酬を提示しても応募がない
- 経験豊富な人材が見つからない
- 内定を出しても辞退される
このような状況でDX人材を確保するには「待ち」の姿勢では通用しません。自社の魅力を効果的に伝え、DX人材に積極的にアプローチする「攻め」の採用活動が重要になります。
外部からDX人材を採用するメリット・デメリット
外部から人材を採用するメリットは、即戦力となる人材を確保できる点にあります。自社が求めるスキルを持った中途社員を採用できれば、すぐにDXに取り組めるだけでなく、社内での人材育成の手間も省けるでしょう。
一方、外部人材の採用にあたってのデメリットは、採用活動が難航する可能性の高さです。IT人材が不足する昨今、DX人材の需要は高まっています。中途社員を採用するには、同様にDX人材を求める競合他社との人材獲得競争に勝たなければなりません。必然的に採用コストは高くなり、最悪の場合、採用可能な人材が見つけられないケースも考えられます。
DX人材を外部から採用するポイント
DX人材を外部から採用する場合は、自社にとっての課題を明確にしてから採用活動をおこないましょう。先述のとおり、DX人材にはいくつかの職種があり、それぞれ担う役割が異なります。必要な人材を見極めず闇雲に人材を求めても、DX推進にはつながりません。
また、DXは社全体を変える事業であり、外部の人材が改革しようとすると社内で反発が出るおそれがあります。外部の人材を迎える前に社内の体制を整えておき、社としてどのような姿勢でDXに取り組むのかを明確にして、採用者に安心感を持ってもらいましょう。
DX人材を外部から採用する手順
DX人材の獲得競争が激化する中、漠然とした求人では優秀な人材に響かず、応募すらしてもらえません。以下の3ステップで、計画的な採用活動を進めましょう。
- 「どの部門で」「どんなスキルを持つ人に」「何を任せたいか」などターゲットをを具体的に定義して、採用後のミスマッチを防ぐ
- 高い報酬だけではなく「裁量権の大きさ」や「挑戦できる環境」「最新技術を学べる」など、候補者の成長意欲を刺激するメリットを打ち出す
- 書類や人事担当者との面接だけではなく、現場のDX推進担当者や技術者を面接に同席させ、スキルレベルを確認する
「計画的な準備」と「攻めの姿勢」で採用活動を行うことで、DX人材の獲得競争に勝ち抜けるでしょう。
②DX人材を育成する
即戦力となるDX人材の採用が難しいため、多くの企業が社内での「育成」に活路を見出しています。特に、自社のビジネスや文化を深く理解している既存社員に、デジタルスキルを習得させる「リスキリング」の注目度が高いです。
時間とコストはかかりますが、社内育成には以下のような大きなメリットがあります。
- 業務を熟知しているため、より自社の実態に即したDXを実現できる
- 育成プロセスを通じて、社内のデジタルリテラシーが底上げされる
- 新しいプロジェクトや事業に挑戦する風土が生まれやすくなる
しかし、ただ研修を受けさせるだけではDX人材は育ちません。育成を成功させるには、知識のインプットと実践を組み合わせた、実践的なプログラム設計が必要です。
社内でDX人材を育成するメリット・デメリット
社内で人材を育成する場合、まず採用活動の必要がないため費用や手間を減らせる点がメリットです。また、社内の事情に精通している人材がDX推進業務を進めることから、意思疎通が比較的楽であり、社内での反発も抑えられます。
他方、デメリットとして挙げられるのは、DX人材の育成には時間がかかるため、長期的な体制を整える必要がある点です。特にDXを初めておこなう企業では、社内でDX人材を育成するのは難しいと考えられます。
DX人材を育成するポイント
DX人材を育成するポイントは、知識学習、実践機会、挑戦を後押しする組織文化を作ることです。具体的には、以下の3つのポイントが重要になります。
- eラーニングや研修で、DXの基礎知識やマインドセットを体系的に学習する
- 学んだ知識を試す場として、PoCを企画、実行する
※PoC(Proof of Concept)は新しいアイデアや技術が実現可能かを検証する試み - 明確な評価基準を設定し、顧客課題の解決など大きなテーマに挑戦させることで、当事者意識と周囲を動かす力が育む
3つのポイントを押させることで、自社のDXを牽引する人材育成につながるでしょう。中でも、PoCの実行は、失敗を恐れず、小さな挑戦を繰り返す経験が成長を促します。社員に基礎を学ばせるのはもちろん、評価基準を設けたうえで実践の機会を与えることが重要です。
DX人材を育成する手順
DX人材を育成する際は、以下の手順で進めることで、より効果を得やすいです。
- 社内環境を整える
- 実践の機会を設ける
- 長期的な視点でリーダーを育成する
- 育成計画に柔軟性を持たせる
DXの基礎を学ばせることは非常に重要ですが、座学だけでDX推進を成功させることは難しいです。若手が実践できる機会を設けつつ、リーダー育成を進めていくことで将来的にDX推進の中心となってくれる人材を確保できます。また、DX人材に必要なスキルは外的要因で変化することもあるため、柔軟に計画を策定しましょう。
③外部のDX人材を活用する
DX推進のスピードを加速させるための手段として、外部人材の活用がおすすめです。特に、以下のような状況では、外部の専門家の力を借りることが大きな効果を発揮します。
- 短期的な成果が求められるプロジェクト
- AIやデータ分析など、社内では保有していない高度な専門性が必要な場合
- 新規事業立ち上げなど、特定の期間だけ専門家を確保したい時
最近では、フリーランスのコンサルタントやエンジニア、専門スキルを持つ企業など、外部人材を活用できる選択肢が増えています。自社だけでは難しい課題解決や迅速なプロジェクト推進を実現するため、外部リソースを戦略的に活用していきましょう。
外部のDX人材を活用するメリット、デメリット
外部人材の活用は、多くのメリットがある一方で、注意しなければならないデメリットもあります。以下の表に、メリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 即戦力人材を迅速に確保できる | ノウハウが社内に蓄積しにくい |
| 社内にはない高度な専門性を補える | 外部に依存しすぎてしまう |
| 客観的な視点を取り入れられる | コストが高くなる可能性がある |
| 必要な期間だけ活用できる | 自社の文化や業務の理解に時間がかかる |
外部人材の活用はコストと引き換えに、時間と専門知識を迅速に確保する施策と言えます。メリット、デメリットを考慮した上で、自社の目的や状況に応じ、最適な活用方法を見つけましょう。
外部のDX人材を活用するポイント
外部人材の効果を最大限に発揮するには「外注先」として考えるのではなく「パートナー」として迎え入れ、社内にノウハウを吸収する仕組みを作ることが重要です。「丸投げ」では外部人材の能力を引き出せず、自社の成長にもつながりません。
DX人材を迎え入れる際は、以下の3つのポイントを意識しましょう。
- 任せる業務範囲や具体的な役割、目標とする成果物を事前に定義し、共有する
- 外部人材と連携する社内担当者を決め、コミュニケーションと業務理解を促進させる
- 定例会などでノウハウを共有してもらい、社員が積極的に学べるような環境を作る
従業員が主体的に関わり、一緒にプロジェクトを進める姿勢が、外部のDX人材を活用した成果を大きく左右します。
外部のDX人材を活用する手順
外部人材の活用を成功させるには、以下の4ステップで進めましょう。
- 自社の課題や依頼したい業務、達成目標を具体的に定義する
- プラットフォームなどを活用し、実績や専門性に加え、自社の文化や風土との相性を比較検討する
- 業務範囲、成果物、費用、期間、機密保持などの項目を詰め、双方合意の上で契約する
- プロジェクト開始後は密に連携し、終了後には成果を評価して次につなげる
このように手順を踏んで活用することで、外部人材の能力を最大限に引き出し、自社のDXを効果的に加速させられます。
DX人材のために企業が取り組むべき5つのこと
優秀なDX人材を採用、育成できたとしても、彼らが能力を最大限に発揮できる環境がなければ、DXの価値は半減してしまいます。DX人材が活躍するためには、スキルの習得と並行して、企業文化や組織体制そのものを変革していかなければなりません。
経済産業省も、経営者の意識改革と具体的なアクションの重要性を指摘しています。ここからは、DX人材を活かすために企業が取り組むべき5つのポイントを解説していくため、ぜひ参考にしてください。
①行動指針を現場に落とし込む
経営層はDXのビジョンだけでなく、社員一人ひとりが何をすべきかを示す具体的な「行動指針」まで現場に落とし込むことが重要です。「全社でDXを推進しよう」というスローガンだけでは、現場の社員は何から手をつけていいか分からず、DXが形骸化してしまう可能性があります。
たとえば「定例会議では必ずデータに基づいた議論をする」など、日々の業務に直結する行動レベルまで落とし込むことで、社員は迷わずアクションを起こすことが可能です。経営層の想いを具体的な行動につながるように伝えることが、全社一丸の体制を築くことに繋がります。
②DXの目的を再認識する
DXの目的を、全社で共有することが重要です。多くの日本企業では、デジタル投資の約8割が既存システムの維持、運営に使われ、守りのIT投資に偏る傾向があります。これでは、本来の目的である「競争優位性の確立」にはつながりません。
ペーパーレス化などの効率化も重要ですが、データを活用した新サービスの開発や顧客体験の向上など、事業成長に直結する「攻めのDX」にこそ注力すべきです。DX人材が能力を最大限に発揮するためにも、企業は収益向上という目的を再認識しましょう。
③企業間での連携を強化し、DX人材同士の交流を活発にする
企業内の取り組みだけでなく、企業間の連携を強化しDX人材同士の交流を活発にすることで、新たな知見やノウハウが共有され、業界全体のDXレベル向上に繋がります。
異なる企業からの参加者が集まることで、異業種間の交流が生まれ、多様な視点や成功事例を学ぶことが可能です。また、以下のような効果も期待できます。
- 担当者同士が抱える課題や成功体験を共有することで、実践的な解決策を見出せる
- 業界内外のDX人材との繋がりを構築し、将来的な協業や情報交換の基盤となる
- 孤立しがちなDX推進担当者が、同じ志を持つ仲間と出会うことで、モチベーションを維持、向上させることができる
社内だけでなく、外部のイベントや研修、コミュニティへの参加を積極的に促し、DX人材が交流できる機会を増やしていきましょう。
④組織設計を見直す
DXを推進し、DX人材がその能力を最大限に発揮するためには、組織設計の見直しが不可欠です。従来の縦割り組織では、部門間の連携が滞り、DXの目的達成を阻害する可能性があります。
DX推進においては、部門横断的な協力体制を築き、柔軟な組織構造を持つことが重要です。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- 全社横断的なDX戦略の立案、実行を担う部署を設け、DX人材を集約する
- 特定のDXテーマに対し、複数の部門からメンバーを集め、知識やスキルを共有しながら推進する
- 迅速な意思決定と柔軟な開発を可能にするため、アジャイルチームを編成する
上記の組織設計の見直しを通じて、DX人材がより働きやすい環境を整備することで、DX推進を加速させることができます。
⑤研修など教育の機会を設ける
DX人材の育成には、企業が積極的に研修や教育の機会を設けることが不可欠です。急速に進化するデジタル技術に対応し続けるためには、既存の知識やスキルを常にアップデートし続ける必要があります。
AI、IoT、クラウドコンピューティングなどの新技術が次々と登場する中で、DX人材にはこれらの技術を理解し、自社のビジネス課題解決に応用できる能力が欠かせません。企業が継続的な学習機会を提供することで、DX人材は最新のトレンドや技術を習得し、変化の激しいビジネス環境に適応できるようになるのです。
たとえば、座学だけでなく、実践的なワークショップやOJTを取り入れることで、従業員が実際の業務に活かせるスキルを効率的に身につけることができます。また、外部の専門家を招いた研修や、オンライン学習プラットフォームの活用も有効な手段です。継続的な学習機会を提供することで、DX人材のスキルアップと定着を促進し、企業のDX推進力を高めることにつながります。
DX人材の確保に取り組んでいる企業の事例3選
DX人材の確保、育成は、多くの企業にとっての課題です。理論だけでなく、実際にDX人材の確保に成功している企業の取り組みを知ることで、DX人材を有効活用するヒントになるでしょう。
ここからは、採用や育成において先進的な取り組みを行っている企業の事例を3つご紹介します。
①東京ガス株式会社
東京ガスは、採用ターゲットの明確化と、学生時代から戦略的なアプローチを組み合わせることで、データ分析を担うDX人材の獲得に成功しています。
同社はデジタル基盤やデジタルマーケティングの強化を目的として、22卒の新卒採用から「DX/データアナリスト採用」の募集を開始しました。「データ分析で価値創造に取り組む人材」とターゲットを具体化したことで、適切な人材のみを確保できる仕組みの構築をしています。
また「東京ガスでDX/データアナリスト人材」が活躍する、というイメージが定着していない学生に対し、データ活用の魅力を伝えるため、実際にデータ活用を体験できる「超実践型」インターンシップを開催しました。結果として、インターンシップは倍率10倍越えの人気枠となり、早期からDXに強い学生の興味を引くことに成功しています。実際に入社したDX人材は「早速活躍してくれている」と担当者からの声も届いており、DX人材の早期採用に成功した事例と言えるでしょう。
②株式会社IHI
重工業メーカーのIHIは、専門家任せではなく、製品や顧客を熟知した事業部門の社員が、自らデータを活用することが重要だと考えています。そのため、現場社員が主体となるDX推進のため「ツールの提供」と「人材育成」を両軸で進めているのが特徴です。
具体的には、以下のような取り組みを行っています。
- プログラミング知識がなくても高度な分析ができるノーコードツールを全社に導入し、データ活用のハードルを下げる工夫をした
- データ分析の基礎から実践までを学ぶ研修を実施し「社内データアナリスト」を育成
- 社内コンペやコミュニティを運営し、学習意欲の向上と育成後のフォローアップを促進
特にデータ分析に関する研修には、2021年度までに650名以上が受講しており、DX人材の育成が急速に進んでいます。
AIを使いやすい環境の整備と人への投資を組み合わせることで、現場からDXを生み出す体制を構築した事例です。
③株式会社ニチレイ
総合食品企業のニチレイは、体系的な育成と、社員が主体的に学び交流できる「コミュニティ」を組み合わせることで、自律的なDX推進文化を形成しています。同社はレベル別の研修で「デジタルリーダー」を育成し、DX人材を核とした社内コミュニティ「DIG!LAB(デジラボ)」を設立しました。
「DIG!LAB(デジラボ)」を中心として、以下のような様々な取り組みを展開しています。
- Excelの便利機能から各部署のDX事例まで、実践的な情報を共有し、誰もが学べる環境を整備した
- 外部講師を招いたセミナーを月1回程度開催し、全社員のデジタルリテラシーとマインドを向上させている
- 意欲の高いメンバーが集う「デジラボキャンプ」で、新しいツールのテストなど先進的な取り組みを実践している
計画的な育成と社員の自発的な学びを促す「場」を作ることが、組織全体のDX推進力を高めることにつながった一例です。
DX人材の育成、活用なら「フリーコンサルタント.jp」にご相談ください
DX人材の確保には、採用、育成、外部活用と様々な方法がありますが、どれを採用すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。そのような企業には、即戦力となるプロ人材活用サービス「フリーコンサルタント.jp」がおすすめです。
国内最大級の24,000名を超えるプロ人材の中から、貴社の課題に最適な専門家を最短即日でご紹介します。DX戦略の立案から実行支援、特定の技術導入まで、採用や育成にかかる時間とコストをかけずに、必要な期間だけ即戦力のスキルを活用することが可能です。
専門コーディネーターが貴社の課題に寄り添い、ミスマッチのない最適な人材を提案するため、外部人材の活用が初めての企業様でも安心してご利用いただけます。DX推進の第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
8.まとめ
DX人材の確保は、企業の競争力を左右する重要な経営課題です。しかし、IPAの調査によれば、約9割の企業が人材の「量」または「質」に不足を感じており、多くの企業が採用や育成に苦戦しています。
DX人材を確保するには「採用」「育成」「外部活用」の3つのアプローチがありますが、それぞれにメリット、デメリットがあるため注意が必要です。採用は即戦力を期待できる反面、獲得競争が激しく、育成は自社に最適化できる一方で時間がかかります。また、外部活用は迅速に専門知識を補えますが、ノウハウが社内に蓄積しにくいという課題があります。
どの方法が最適かは企業の状況によりますが、戦略的に組み合わせることも重要です。たとえば、即戦力となるプロのコンサルタントを「フリーコンサルタント.jp」のようなサービスで活用し、プロジェクトを推進しながら社内人材を育成していくハイブリッド型のアプローチも有効でしょう。
外部人材の活用を考えている方は、ぜひ一度「フリーコンサルタント.jp」へお問い合わせください。
(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)