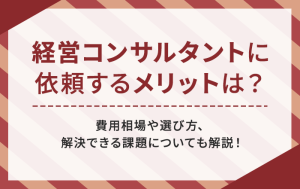『予実管理とは具体的にどういうものか?』『正しい予実管理をどのようにおこなうと良いか?』など疑問を抱えている役員や管理職の方々は多いのではないでしょうか。予実管理は企業や事業部門の予算と実績を管理することで、経営目標の数値等を達成できるかどうかを確認する際に使われます。
この記事では、予実管理を行うメリットや失敗しないためのポイントを解説いたします。実際に予実管理を行う手順も説明しているため、経営目標の達成度合いが知りたい方は、この記事で予実管理について確認して参考にして下さい。
■目次
1.予実管理とは?
予実管理とは、企業や部署などにおいて予算と実績を管理することです。一般的に、企業は経営計画を立案したうえで「売上高」「利益高」などの予算と期間を区切って数値化し、1年間の収支見積もりに合わせて活動を行っていきます。予算に対して実績が伴ってきているかどうかを確認することで、経営目標が順調に進んでいるか否かを確認することができます。もし、うまくいかなかった場合、軌道修正するチャンスを逸してしまうでしょう。
しかし、予実管理を行うことによって、設定した予算に対する実績の進捗度合いが見える化できるようになります。予算を予定どおりに達成できそうか、達成が難しく軌道修正が必要かなどを把握することで、その後の活動も変わってくるでしょう。
予実管理は、予算達成の重要な役割を担っているのです。
2.企業が予実管理を行う目的
予実管理の目的は、予算に対する実績の進捗状況を見える化することで、企業の経営目標を達成していくことです。予算さえ設定すれば、達成に向けて活動できると思っている方もいるかもしれません。しかし、予実管理をしていない場合、最終的な結果が出るまで活動を評価できません。その結果、予算を達成できる確率が下がってしまいます。
たとえば、実績不振で予算達成が見込めないことが想定される場合、実績不振の原因を特定し、実績回復に向けた対策をリアルタイムに実施することが可能です。その結果、予算と実績の乖離が小さいうちに軌道修正できるので、経営目標を達成する可能性が高まります。
予実管理することを目的とせず、データに基づいた改善を図り、経営目標達成を確実なものにしていくことが大切です。

3.予実管理と経営管理の関係性
予実管理と経営管理は、予実管理が経営管理の各項目が計画通りに進捗しているかをモニタリングする関係にあります。
経営管理とは、企業の経営目標を達成させるために「ヒト、モノ、カネ」といった経営資源の活用状況を適切に管理することです。経営管理には、以下のような機能が求められています。
| 経営管理の機能 | 具体的内容 |
| プランニング機能 | 経営目標やミッションの策定 |
| コーディネート機能 | 事業間における利害関係の調整 |
| コントロール機能 | 経営目標やミッションの達成に向けた進捗管理 |
| モニタリング機能 | 課題分析とアクションプランの立案 |
企業の限られた経営資源を有効に活用するためには、各項目の予算を策定し、実績の進捗状況をモニタリングする必要があります。
そこで、予実管理を行うことで経営が目標に沿って進んでいるかのモニタリングが可能です。予実管理を通して資源が適切に活用できているかを判断することができ、目標達成に向けて無駄なく動くことができます。
上記の理由から、広範囲に及ぶ経営管理を適切に機能させるためには、予実管理が必要不可欠と言えるのです。

4.予実管理の4つの手順
実際の予実管理は、以下のような手順となっています。
ここからは、4つの手順について順を追って解説します。
①自社に合った適切な予算目標を設定する
予実管理を行うために最初に行うことは、自社の現状や中期計画を考慮した適切な予算目標の設定です。
予実管理とは、予算に対する実績の進捗状況を見える化することで、経営目標を達成することが目的です。そのため、そもそも予算目標がなければ予実管理は成り立ちません。
予算目標を設定するうえで大切な点は、目標達成実現の可能性です。達成が到底困難な目標水準を設定してしまうと、どれだけ精緻に管理しても達成することができず、改善は期待できません。逆に、目標達成の難易度が低すぎても企業の成長にはつながらないでしょう。
努力や工夫によって達成できるストレッチ目標を設定することで、予実管理が効果的に機能します。
②KPIと具体的なスケジュールを作成する
予算目標を設定したら、具体的なKPIとスケジュールを設定していきます。
KPIとは、日本語で「重要業績評価指標」と呼ばれるもので、目標達成に向けたアクションやプロセスについて、必要となる水準を数値化したものです。予算目標の達成度合いしか指標がないと、実績不振でも原因を見つけることが困難になります。そこで、KPIを設定することにより、どのプロセスに問題があるのかが判断しやすくなるのです。
また、いつまでにKPをI達成させるかスケジュールを決めることも大切です。具体的なスケジュールや数値、それに伴うアクションを具体的に作成しておくことで今やるべきことは何かが明確になるでしょう。
③こまめにチェックを行い、課題の発見と改善に努める
KPIとスケジュールを決定してスタートしたら、こまめなチェックによって課題の発見と改善に努めることが大切です。
予実管理によって予算と実績の乖離は把握できますが、乖離があまりにも大きいと軌道修正は簡単ではありません。小さな乖離を発見して早期に改善策を検討と実施することで、予算達成をスケジュール通りに進めることが容易になります。
なお、予実管理システムなどを活用することで、いつでも簡単に予実管理が行える環境を作ることができるため、上手に取り入れてみましょう。また、月次チェックはもちろん、週次や日々のチェックタイミングをあらかじめ決めておき、ルーティンで実施することをおすすめします。
④予算と実績を比較し、軌道修正を行う
こまめなチェックを続けた結果、予算と実績に乖離が生じるようであれば、軌道修正をしていきましょう。
乖離が発生したら原因を明確に突き止めることが重要です。原因に対応した対策になっていないと、せっかくの改善策が空振りに終わってしまいます。乖離の原因を明らかにするためには、実績そのものだけではなく、構成する要素やプロセスに着目するとよいでしょう。それぞれのKPIに対する達成状況に着目することで、原因が明確になってきます。
また、実績不振の場合だけではなく、数値が順調に推移している場合も原因を探ることは非常に有益です。実績が好調な原因が特定できれば、今後、実績不振に陥ってしまった場合にも、軌道修正を行う方法を考えやすいでしょう。
5.予算管理におけるPDCAサイクルとは
予実管理を行ううえで、PDCAサイクルを回していくことは大切です。予算と実績の乖離がわかっただけでは意味がなく、乖離の解消に向けて改善を繰り返していかないと目標達成できません。
目標を達成するためには、PDCAサイクルによる予実管理が効果的です。具体的には以下のようなサイクルで行っていきます。
| サイクル | 内容 |
| Plan(計画) | 指標となる予算を策定する |
| Do(実行) | KPIやスケジュールに沿って活動する |
| Check(評価) | 定期的に予算と実績をチェックする |
| Action(改善) | 課題の原因、対策を検討して行動に移す |
計画した予算に向けて活動し、予算と実績の乖離をチェックして課題を分析します。分析結果を踏まえた対策を行動に反映することで、目標達成に繋がるでしょう。

6.予実管理の3つの失敗例
予実管理を導入しても、以下のような失敗をしてしまう可能性があります。
ここでは3つの失敗例を紹介しますので、同じ事態にならないように注意しましょう。
①細かな差異の分析を行うことが目的になってしまう
失敗例の1つ目は、細かな差異の分析が目的になってしまうケースです。
確かに予算と実績の差異をチェックすることは大切です。しかし、本来の目的は差異が発生した原因を特定して改善することによる目標達成であり、差異のチェックは手段に過ぎません。チェックの正確さや差異の事実にばかりとらわれるのではなく、原因の分析と対策の検討に時間をかけましょう。
また、せっかく改善策を検討しても、実行しなければ目標達成には近づきません。評価をして検討した内容を行動に移すことで、PDCAサイクルは回っていきます。予実管理の目的を見失わないことが失敗しないコツです。
②予算にこだわりすぎている
失敗例の2つ目は、設定した予算にこだわりすぎてしまうケースです。
予実管理をするうえで、予算目標の達成はもちろん大切です。しかし、目標達成を目指すあまり従業員に無茶な仕事量を押しつけたり、厳しい叱責を繰り返したりすると、従業員が疲弊して逆に目標達成から遠のく可能性があります。また、目標達成にこだわるあまり、不正行為をしてしまう従業員が出てくるかもしれません。
そのため、時には環境変化に合わせた予算変更も対策の1つといえます。予算にこだわりすぎず、冷静に分析する必要があります。
③既存システムとの連携不足
失敗例の3つ目は、既存システムと連携不足となってしまうケースです。
予実管理は、予算と実績をリアルタイムで把握したうえで、乖離の原因を特定することが求められます。しかし、すでに導入しているシステムとの連携が不足していると、予実管理用のシステムに再度データ入力したり、複数のシステムをチェックして分析したりしなければなりません。その結果として、以下のような問題が発生する可能性があります。
- リアルタイムなチェックができない
- 部署間の情報連携ができない
- 現場で予実管理が定着しない
多くの会社では、すでにさまざまな管理システムを導入しており、連携ができないシステムは不便で利用されない傾向があります。既存システムとの連携を踏まえたシステムを導入する必要があることも念頭において進めていきましょう。
7.予実管理で失敗しないためのポイント5つ
予実管理において、失敗を起こさないためのポイントは以下のとおりです。
ここからは、失敗しないための5つのポイントを解説します。
①KPIの設定を行う
予実管理を失敗しないための1つ目のポイントは、KPIの設定を行うことです。
KPIは、目標達成に向けた各プロセスの具体的な行動指標を意味しています。目標達成をする必要があることは周知されていても、実績を高めるために何をすればいいか明確になっていないと活動は進みません。そのため、目標達成に向けて取るべき行動やプロセスを数値化して指標を設定します。
たとえば、営業部門であれば売上高目標達成のためのKPIは、見込客数やアポイント数、成約件数などです。KPIの進捗をチェックすることで、予実管理がより効果的になるでしょう。
②部門ごとに予実管理を行う
予実管理を失敗しないための2つ目のポイントは、予実管理は部門ごとに行うことです。
生産管理や販売管理などで複数の部門が関わっている場合、会社全体の予実管理では原因分析が難しくなります。しかし、部門ごとに細分化して予実管理を行うことで、会社全体が実績不振のときに、どの部門に課題があるのかすぐにわかります。
また、部門ごとに予実管理を行うことで、自分たちの業務による会社の利益が分かるため、従業員たちの達成意欲向上に繋がります。その結果として、会社の目標達成に寄与するでしょう。
③随時進捗状況の確認を行う
予実管理を失敗しないための3つ目のポイントは、進捗状況の確認を随時行うことです。
せっかく予実管理を導入しても、半期や四半期ごとにまとめて確認、分析するのでは意味がありません。なぜなら、数ヶ月前の予算と実績の乖離があっても、後から原因を特定するのは困難なうえ、発生した課題が放置されることにより深刻化したり、ほかの問題と絡み合って複雑化したりするケースがあるからです。
そのため、なるべくリアルタイムに予実管理を行い最新の状況を分析することで、問題が発生する予兆をタイムリーに捉えられるようになります。
④予算との乖離が見られた場合は徹底的分析を行う
予実管理を失敗しないための4つ目のポイントは、予算との乖離が見られた場合に徹底的に分析を行うことです。
なぜなら、分析が十分ではないと誤った改善策に基づいて行動してしまうことで、実績回復につながらないからです。たとえば、販売業で売上実績が不振になった場合に、原因として以下のようなものが考えられます。
- 営業担当のアポイント不足
- 提案時の成約率低下
- 競合他社の新商品投入
アポイント不足が原因であれば、見込客づくりや既存顧客のフォロー不足が考えられます。成約率が原因なら、ロープレなどの研修不足かもしれません。競合他社が原因なら、他社新商品の分析と対抗策の立案が必要になるでしょう。
上記のように原因を深堀りすることで、目標達成に直結する改善策を導き出すことができます。
⑤ほぼ毎日実施する
予実管理を失敗しないための5つ目のポイントは、予実管理をほぼ毎日実施することです。
予実管理により、予算と実績の乖離を確認して改善を図っていきます。ただ、乖離があまりにも大きいと軌道修正するのは困難です。つまり、いかに乖離が小さい段階で早期発見し、改善策を講じるかが目標達成のカギになります。
そのため、予実管理の実施スパンはなるべく短いほうが望ましいです。業種や管理内容にもよりますが、最低でも毎月、可能であれば毎週、日々実績が変動するなら毎日実施するのがよいでしょう。
なお「毎日予実管理するのは大変だ」と思う方もいるかもしれません。最初は面倒かもしれませんが、毎日繰り返すことで習慣化されていくため、ちょっとした実績の変化にも敏感になるでしょう。

8.予実管理表作成におすすめのツール3つ
予実管理を効率的に行っていくには予実管理表が重要です。予実管理表には以下のようなツールがおすすめです。
ここからは、予実管理表作成におすすめのツール3つを紹介します。
①予実管理システム
予実管理システムとは、企業の予算と実績を管理、分析するための専用ツールです。以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット |
|
| デメリット |
|
予算の集計分析に加えて、柔軟な予算管理が可能です。一方で、導入コストや既存システムとの連動、新たなシステム利用の習熟などの課題があります。
②エクセル
エクセルは、ほとんどのパソコンに導入されているツールです。以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット |
|
| デメリット |
|
無料で簡単に利用できるため、小規模のスタートアップ企業などではエクセルでの予実管理が便利です。しかし、管理範囲が広がることで、時間や手間が生じることも覚えておきましょう。
③SFA
SFAとは「Sales Force Automation」の略語で、日本語では「営業支援システム」と呼ばれるツールです。SFAには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット |
|
| デメリット |
|
予算達成と営業活動は密接に関連しています。そのため、予実管理機能があるSFAであれば、効率的に予実管理が行えるでしょう。

9.予実管理に関するよくある質問
予実管理についてよくある質問に回答していきます。
予実管理の知識がないまま導入しても、現場が混乱してしまうかもしれません。これから予実管理の導入を検討している方は、しっかりと理解しておきましょう。
予実管理とは?
予実管理とは、企業や部署などにおいて予算と実績を管理することです。
予実管理を行うことで以下のようなメリットがあります。
- 実績不振の原因を特定できる
- 実績回復に向けた対策をリアルタイムに実施できる
- 予算と実績の乖離が小さいうちに軌道修正できる
そのため、経営目標を達成する可能性が高まります。
予実管理の手順は?
予実管理の手順は、以下のような流れです。
- 自社に合った適切な予算目標を設定する
- KPIと具体的なスケジュールを作成する
- こまめにチェックを行い、課題の発見と改善に努める
- 予算と実績を比較し、軌道修正を行う
自社に合わないような無理な数値を設定してしまうと、どれだけ管理を行ったとしても目標数値に達成できず、実績回復には遠のいてしまいます。そのため、自社に合った数値目標を立てるようにしましょう。
それと同時にKPIと具体的なスケジュールを立てることで、数値の乖離が見えた際に行うべき次のアクションが分かりやすくなりますよ。
10.まとめ
この記事では、予実管理を行うメリットや失敗しないためのポイント、実施の手順などについて解説しました。
予実管理は企業の予算と実績を管理するもので、経営目標の達成には欠かせないものです。導入にあたってはさまざまなツールがあり、メリットとデメリットを踏まえて検討する必要があります。そのため、経営目標の達成度合いが知りたいという方は、予実管理の導入を検討することがおすすめです。
しかし、予実管理の正しい手順がわからない方、初めての取り組みに不安を感じている方もいるでしょう。その場合、プロの人材を頼ってみるのもおすすめです。みらいワークスでは、プロ人材マッチングサービス「Free Consultant.jp」を提供しています。企業の課題に合わせたプロフェッショナル人材をご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。




-300x189.png)