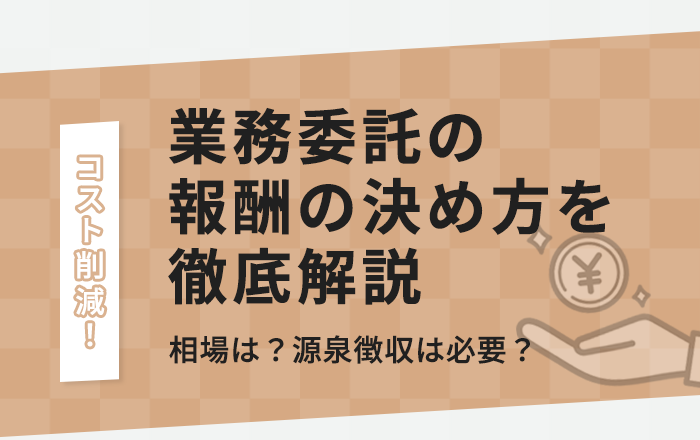
業務委託(アウトソーシング)は、労務コストを削減しながら即戦力となる人材を確保できるのが強みであり、特に専門的な知識が必要な業務やルーティンワークと相性が良いのが特徴です。自社で多数の社員を雇用するより業務委託と使い分けて効率化する方が良いケースもあるので、選択肢のひとつとして覚えておきましょう。
本記事では、業務委託の報酬の決め方について解説します。業務内容ごとの相場や源泉徴収にも触れるので、ご参考ください。
こんな人におすすめ
- 初めて業務委託契約を結ぶことを考えている企業担当者
- 業務委託費の相場が知りたい方
- 人件費を抑えたい方
■目次
業務委託報酬の3つの決め方
まずは、業務委託報酬の決め方について解説します。主に3種類に細分化できるので、業務の性質に応じて決定していきましょう。
- 【固定報酬型】毎月決まった金額を支払う
- 【成果報酬型】成果に対して報酬を支払う
- 【複合型報酬】成果報酬と業務量を組み合わせる
【固定報酬型】毎月決まった金額を支払う
固定報酬型は毎月決まった金額を支払う手法であり、委託する業務内容や期待するパフォーマンスが一定であるときに便利な手法です。成果物の内容を事前に細かく定めることが多いため検品(検収)の手間もかからず、管理の工数も最小限にできます。また、期間内で決められた業務時間分を働いてもらうような形式の際に活用しても良いでしょう。
具体的な活用シーンは、ルーティンワークのアウトソーシングなどが想定されます。「毎月30時間分の経理業務」「毎月の記帳業務」など範囲を限定すれば、固定で支払う方が双方にとって楽です。
【成果報酬型】成果に対して報酬を支払う
成果報酬型は、文字通り成果物に対して報酬を支払う手法です。委託先のスキルや経験、ノウハウによって成果物のクオリティが左右されるような業務や、成果物の品質、効果を重視したいときに向いています。
たとえば、ライティング、Webデザイン、プロダクト開発、プログラミング、コーディングなどの業務をイメージすると良いでしょう。1案件単位で支払うことも多く、1時間かけた成果物であっても10時間かけた成果物であっても、求めるクオリティに達していれば一定の料金を支払います。
【複合型報酬】成果報酬と業務量を組み合わせる
複合型報酬は、成果報酬と業務量を組み合わせて支払い額を決める手法です。取引の金額が大きいときやかなり高いレベルでの業務遂行を求めるときに活用されることが多く、リスクを考慮した手法としても活用されます。
たとえば、基本の委託報酬は固定で支払い、成果次第でインセンティブ給を上乗せする方法が代表的です。特に数値評価しやすい業務内容であれば、インセンティブによるモチベーション向上を期待しても良いでしょう。
業務委託の報酬相場
業務委託の報酬は「成果報酬型」と「月額型」の2つがあり、どちらを採用するかで大きく金額は異なります。そのため、一概に「相場はいくら」と言えません。
また、月額型の場合は稼働日数によっても金額が変わってきます。コストを削減したい場合は、稼働率を調整して報酬を抑えるのが良いでしょう。
なお、月額型と成果報酬型のどちらにおいても、クラウドソーシングサービスやエージェントサービスから発表されている平均相場をチェックすることで「想定していたよりもコストがかかる」といった事態を防止できます。
契約形態で報酬形態が変わる
業務委託報酬は、契約形態に応じて変化するのが一般的です。たとえば請負契約の場合、成果物の納品に対して報酬が支払われます。反対に、成果物が完成しなければ報酬は発生しません。
委任契約や準委任契約の場合、業務遂行そのものに対して報酬が発生するため、明確な成果物を求めないことも多いです。コンサルタント、探偵、弁護士など成果報酬の多い職種でよく採用されています。
なお、委任契約は法律行為を委託する場合の契約、準委任契約は法律行為以外の事務処理を委託する場合の契約に用いられる名称です。依頼する業務内容によって契約形態が異なるため注意しましょう。
業務委託を行いたいと考えている方は、株式会社みらいワークスの運営する「フリーコンサルタント.jp」がおすすめです。24,000人以上のプロフェッショナル人材が、目標達成に向けて伴走してくれます。契約形態も依頼内容によって最適なものをご提案させていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。
業務委託の報酬の内訳
ここでは、業務委託の報酬の内訳を解説します。報酬に何が含まれるか知っておけば、コストカットしやすい部分も探しやすくなります。
- 【外部コスト】フリーランスや企業に支払う費用
- 【内部コスト】採用担当者の人件費や資料作成費
- 業務委託で発生した経費は委託者が支払う
【外部コスト】フリーランスや企業に支払う費用
外部コストとは、文字通り外部のフリーランスや企業に支払う費用です。「業務委託の報酬」と表記したときにまずイメージするのが外部コストであり、業務を委託するのにかかる費用や依頼料が含まれます。
その他、外部ツール費や交通費などの経費全般や、フリーランスエージェントやヘッドハンターに支払う紹介料なども含まれるのが特徴です。
【内部コスト】採用担当者の人件費や資料作成費
内部コストとは、業務委託の発生に伴って社内で生じる費用です。たとえばフリーランスの選定をする採用担当者の人件費、業務委託契約書の作成や管理をする総務部門の人件費、資料作成費、内部での打ち合わせ費などが含まれます。
明確な金額として現れないことも多いため、コストについて考える際の見落としやすい部分ではありますが「意外にもコストが嵩んでいた」という落とし穴のないよう注意しましょう。
業務委託で発生した経費は委託者が支払う
業務委託で発生した経費は、原則として委託者が支払います。業務に直接必要な機材や道具、設備、必須の打ち合わせに対して発生する交通費や宿泊費などは委託者の負担となることがほとんどです。領収書や請求書があれば経費計上できるので、受託者からの回収を忘れないようにしましょう。
反対に、通信費やオーバースペックな機材費など、受託者の裁量で具体的な金額を決められるものについては、受託者負担となることもあります。業務委託契約を締結する際は、発生する可能性のある経費の取り決めについて契約書に盛り込んでおきましょう。
法人との業務委託契約に源泉徴収は必要ない
源泉徴収とは、個人に対する報酬や給与から決められた税額を差し引いて支払い、預かった分は企業側がまとめて納付する制度です。個人事業主やフリーランスなどの個人に対して適用されるもので、法人との業務委託契約に源泉徴収は必要ありません。法人は独立した法人格を持っているため自身で税金の申告、納税ができ、源泉徴収をして委託者が納付を代わりに進めなくて良いとされています。
馬主である法人に競馬の賞金を支払うケースなど、稀に法人に対しても源泉徴収の義務が発生することがありますが、基本的な業務委託契約であればまず源泉徴収はしなくて良いでしょう。
個人事業主と業務委託契約を結ぶ場合は源泉徴収の対象となることも
個人事業主と業務委託契約を結ぶ場合は、源泉徴収をしなくてはいけないことがほとんどです。源泉徴収の対象となる報酬支払いを行う場合は全て源泉徴収義務者となり、自分たちが個人であるか企業であるかは関係ありません。
例外は「従業員の雇用をしておらず、給与支払いを行っていない個人が税理士や弁護士等へ報酬を支払う場合」および「2人以下の家事使用人に対してのみ給与の支払いを行っている個人が、家事使用人に給与や報酬、退職金を支払う場合」に限定されているので注意しましょう。
源泉徴収の対象となる業務は、以下の通りです。
- セミナーなどの原稿料や講演料
- 弁護士や会計士、司法書士など、特定の有資格者への報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う場合の診療報酬
- スポーツ選手、モデル、タレント、保険や不動産外交員などへの報酬
- 映画や演劇、テレビ放送等の芸能人に出演に対する報酬
- 芸能事務所の経営者(個人)への報酬
- 宴会で客への接待を行うホステス、コンパニオンなどへの報酬
- 役務の提供を約束してもらうために一時的に支払う契約金
- 広告効果を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の報酬
源泉徴収の対象は職種ではなく、あくまでも仕事内容である点に注意しましょう。たとえば、職種が弁護士であっても、依頼した内容が原稿の執筆なのであれば原稿料支払いとしてみなされるため源泉徴収義務が生じます。
業務委託にかかるコストを削減!報酬交渉のポイント3つ
ここでは、業務委託にかかるコストを削減する方法を解説します。報酬交渉のポイントにもなるので、以下を押さえておきましょう。
- 報酬の相場をチェックする
- さまざまなサイトで見積もりをとる
- 依頼したい業務を明確にする
1.報酬の相場をチェックする
業務委託の報酬相場を把握しておくと、依頼先の比較や交渉に便利です。業界内での適正価格をもとに交渉できるので、法外な金額で契約してしまったり、安すぎる金額を提示して優秀な人材を逃してしまうリスクを予防できます。
事前に必要なコストの目安を立てておけば予算も確保しやすく、適切なコスト管理もできるでしょう。
2.さまざまなサイトで見積もりをとる
クラウドソーシングサービスや人材マッチングサービスなどのサイトで見積もりを取り、徹底的に依頼先を比較、検討するのも効果的です。成果物のクオリティや確実な業務知識に加えて報酬の比較もできるので「少しでもコストパフォーマンスが良いところに依頼したい」というニーズを満たせます。
また、場合によっては「〇円で受注してくれる候補がある」という交渉材料として使っても
良いでしょう。
3.依頼したい業務を明確にする
依頼したい業務を事前に明確にすることにより、正確な見積りを取得する方法です。業務内容に応じて報酬が変動するのはよくあることで、事前に依頼したい業務が定まっていないと、トータルコストもブレてしまいます。
曖昧な依頼をするより「この分をお願いしたい」と明確に決まっている方が、受託者にとっても業務リソースのイメージがつきやすくなり、場合によっては値下げに応じてくれることもあるのです。
コストを削減しすぎると優秀な人材が集まらなくなるため注意が必要
コストを削減しすぎると、優秀な人材が集まらなくなるため注意しましょう。もちろんコストを抑えられるのは嬉しいメリットですが「安かろう悪かろう」になっては本末転倒です。
成果物のクオリティを担保できる経験や知識があるか、信頼に足る実績があるか、業務内容に関する十分な専門知識を持っているか、など多角的に依頼先を評価していきましょう。
消費税も必要!源泉徴収の計算方法
源泉徴収する金額は、税込金額に10.21%をかけて計算するのが最も手っ取り早い方法です。たとえば依頼価格が2万円、税込価格が2万2,000円(消費税率10%)の場合、税込2万2,000円×10.21%=2,246円を源泉徴収として控除します。
ただし、1回に支払う金額が1人当たり100万円を超える場合、税率が20.42%に変更となるため注意しましょう。
報酬支払月の翌月10日までに納付する必要がある
源泉徴収した所得税は、報酬支払月の翌月10日までに納付する必要があります。毎月業務委託報酬の支払いが発生する場合、年単位でまとめて納付するのではなく、毎月の納付が必要ということです。
一括でまとめて支払う場合でも、翌月10日までに源泉徴収した分を全て納付しなくてはいけません。
業務委託契約の請求書や明細の作成方法
業務委託を締結する際は、当然ながら業務委託契約書の取り交わしが必要です。最低限記載しておくべき項目は、以下の通りです。
- 受託する業務内容
- 支払いタイミングと方法
- 業務に関わる経費について
- 損害賠償
- 知的財産権
- 秘密保持条項
- 納品の期限や検収期間、条件
- 契約不適合期間
- 有効期限と中途解約
- 所轄裁判所
業務委託契約書の記載項目は厳格に定められておらず、双方の話し合いにより決まります。とはいえ、後々のトラブルを避けるためにも、上記で記した項目は記載しておいた方が良いでしょう。
なお、業務委託契約書を作成する際は弁護士のリーガルチェックを受けるのが基本です。リーガルチェックを受けることで、知らず知らずのうちに法を犯してしまうリスクやトラブルが発生するリスクを抑えられます。
「月末締め翌月末払い」はNG
月ごとに成果物の量が変動する場合、業務委託契約書に「月末締め翌月末払い」など締切制度や締切計算式で記載してしまいがちです。しかし「月末締め翌月末払い」という記載では具体的な支払期限の日付を特定したことにならず、双方の間で認識に相違が生まれてトラブルになることがあるので注意しましょう。
たとえば、発注日や受注日、納品日、検収日がそれぞれ異なり、月末月初をまたいでいると「どこからどこまでが今月支払い分なのか」がわかりにくくなります。最悪の場合、支払期限や支払期日を特定したことにならないとみなされて、報酬や料金、委託料の通知に関する下請法に抵触する恐れがあるので注意が必要です。
正確に支払期限を記載したいときは「毎月末日納品締切、翌月末日支払」のように記載しましょう。少し工夫するだけで「納品日を基準とする」など要素を付け加えることができ、認識のズレを防げます。
なお「フリーコンサルタント.jp」なら、数々の業務委託を成功させてきたプロが契約書作成から契約締結までサポートいたします。相談は無料なので、一度お気軽にお問い合わせください。
業務委託を行う際の3つの注意点
ここでは、業務委託を行う際の注意点を解説します。思わぬトラブルにならないよう、契約前に以下をチェックしておきましょう。
- 偽装請負にならないよう業務範囲をあらかじめ固めておく
- 報酬未払いが発生しないようにする
- 成果物の取り扱いや報酬について契約書に記載しておく
1.偽装請負にならないよう業務範囲をあらかじめ固めておく
偽装請負とは、業務委託であるにも関わらず委託者から受託者へ直接的な業務指示がある場合など、実態が労働者派遣と同様の状態である状態を指す言葉です。業務委託の場合、実際に働く労働者への指揮命令権は受託した会社(またはフリーランサー)にあり、委託者に指揮命令権はありません。
一方、委託者から受託者へ直接的な業務指示をしてしまうと実質的な「労働者派遣」とみなされてしまうので注意しましょう。偽装請負にならないよう、あらかじめ依頼する内容は定めておくことが重要です。
2.報酬未払いが発生しないようにする
お互いの信頼性を高めるためにも、報酬の未払いや遅延は厳禁です。やむを得ない事情があっても基本的には報酬の支払いだけは徹底するよう意識する他、どうしても相談しなくてはいけなくなったときは報酬支払日より前に声をかけましょう。
また、支払い期日や分割払いの条件を明確にし、支払い遅延のリスクを減らすリスクマネジメントも重要です。報酬に関するトラブルが発生してしまうと、優秀な人材が次回以降仕事を請け負ってくれなくなってしまう恐れがあるため注意しましょう。
3.成果物の取り扱いや報酬について契約書に記載しておく
成果物の取り扱いや報酬についても、細かく契約書に記載しておきましょう。特に成果物に関する知的財産権が誰に帰属するか明確に示していない場合、検収して報酬が支払われた後であっても権利を主張されてしまうことがあります。
納品後のトラブルを防止するためにも必ず納品物の扱い方についての記載を残し、お互いが同意したうえで業務を進めるようにしましょう。
業務委託先の3つの探し方
最後に、業務委託先の探し方をいくつか紹介します。
クラウドソーシングサービスを活用する
プロ人材紹介サービスを活用する
人脈を活用する
自社にとって使いやすい方法を探し、コストパフォーマンスの高い依頼先を選定しましょう。
1.クラウドソーシングサービスを活用する
クラウドソーシングサイトのほか、スキルマーケット、ビジネスマッチングサイトを使って積極的に人材を発掘する方法があります。相手と直接やり取りできるため仕事内容に関する打ち合わせや報酬交渉がスムーズというメリットがある一方「人材の質やスキルセットがまちまち」「初心者や未経験者が紛れ込んでいてトラブルになった」などの事例も多いので注意しましょう。
原石を探すに近しい手法なので、長い時間をかけてマッチングをしていくイメージで使うのがおすすめです。
2.プロ人材紹介サービスを活用する
プロフェッショナル人材サービスは、その名の通りプロフェッショナル人材を紹介してくれるサービスです。スキルレベルの高い人材が多数登録しており、自社が求める人物像やスキルセットに合う、理想的な人とマッチングできます。業務クオリティの向上や自社成長の促進に貢献するため、単なる業務のアウトソーシングだけでなく、ノウハウを学ぶ機会としても役立てられるのがポイントです。
なお、株式会社みらいワークスが運営している「フリーコンサルタント.jp」では、即戦力となるプロフェッショナル人材を紹介しています。自社にはない人材を獲得したいときや、ハイレベルな業務を委託したいときにご活用ください。
3.人脈を活用する
人脈を活用し、優秀なフリーランスや委託先企業を探す方法もあります。人脈を通じて紹介された委託先は、初対面の相手より信頼できることが多いです。
コミュニケーションもスムーズで、紹介相手からおよその仕事内容を聞いていることも多く、報酬について直接交渉できる可能性もあります。
まとめ
業務委託の報酬は、業務内容により相場が変動します。契約形態により支払方法が変わることも多く、業務委託契約書の作成に悩んでしまう企業も多いでしょう。本記事で紹介した内容をもとに、条件面でトラブルに発展しない業務委託にすることが大切です。
なお、プロフェッショナル人材に業務委託することを検討されている方は、フリーコンサルタント.jpにご相談ください。スキルレベルが高く、希望する業務にコミットする専門職をご紹介します。







