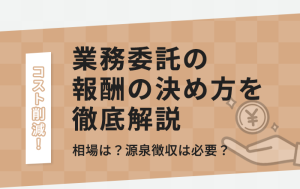「業務委託契約にはどのような種類があるかわからない」「どの契約形態が合うかわからない」こんなお悩みはありませんか?
業務委託とは「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の総称です。契約形態によって業務内容などが異なるため、正しく理解した上で契約することが大切です。適切な契約が締結できれば、リスク回避やコスト削減に繋げられるでしょう。
本記事では、業務委託の種類やフリーランス、派遣との違いなどについて詳しく解説します。ぜひ、参考にしてみてください。
- 社外から人材を導入しようとしている企業の採用担当者
- 契約ごとにどんな違いがあるのか知りたい方
- それぞれの雇用形態のメリットや注意点、コストを理解して、最適な形で人材を確保したい経営者
■目次
業務委託の種類
業務委託には「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3つがあります。各契約形態の概要は、以下の通りです。
| 委任契約 | 準委任契約 | 請負契約 | |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 業務委託契約(委任契約) | 業務委託契約(準委任契約) | 業務委託契約(請負契約) |
| 報酬の対象 | 業務の遂行 | 業務の遂行 | 業務の成果 |
| 完成義務 | なし | なし | あり |
| 主な業務内容 | 法律業務 | 法律業務以外の業務(書類作業や開発業務など) | 成果物の作成(建設工事やプログラム作成など) |
| 指揮命令権 | なし | なし | なし |
| 社会保険への加入 | なし | なし | なし |
| 勤務時間や勤務場所 | 自由 | 自由 | 自由 |
| 再委託の可否 | 委任者の許諾を得た場合、やむを得ない場合に可能 | 委任者の許諾を得た場合、やむを得ない場合に可能 | 可能 |
各契約形態には、報酬の対象や完成義務、再委託の可否などに違いがあります。詳しい内容は次項にて解説しますので、参考にしてください。
- 委任契約
- 準委任契約
- 請負契約
委任契約
.png)
委任契約とは、委任者(発注者)が受任者(受注者)に特定の業務や権限を委託する契約のことです。業務内容の対象は法律行為に限られ、弁護士や司法書士、税理士などと締結する場合が多い特徴があります。
法律行為とは、当事者の意思表示によって法的な効力が生じる行為のことです。たとえば「相続した土地の登記を司法書士に依頼する」といった場合は委任契約に当たります。
委任契約を活用する場合は雇用関係が生じないため、雇用保険や厚生年金、労災保険といった企業の社会保険は必要ありません。また、休暇制度などの福利厚生も対象外です。
準委任契約
.png)
準委任契約とは、特定の業務を委託する契約のことを指します。法律行為に限らず、書類作業や開発業務といったさまざまな業務を対象とする点が委任契約との違いです。そのため、下記のような多様な職種で準委任契約が結ばれます。
- 医師
- コンサルタント
- 美容師
- エンジニア
準委任契約も企業側との雇用関係が生じないため、社会保険や福利厚生は対象外です。
請負契約
.png)
請負契約とは、受任者が依頼された仕事を完成させることを約束し、その成果に対して委任者が報酬を支払う契約のことです。請負契約を結ぶ具体的な職種としては、下記が挙げられます。
- ライター
- デザイナー
- プログラマー
- 営業代行
委任契約、準委任契約と同様に企業側との雇用関係が生じないため、社会保険や福利厚生は対象外です。
委任契約と請負契約の違いは?
委任契約と請負契約の違いは、業務の完成義務があるか否かという点です。委任契約は特定の業務の遂行を目的としており、成果物に対する完成義務はありません。業務の結果に不備があったとしても、委任者は受任者に保証や修正を求められないのが原則です。
一方で、請負契約の場合、受任者は受託した業務を完成させる必要があり、委任者は成果物に対して報酬を支払います。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、企業が行なっている業務の一部を外部の企業または個人に委託する際に締結する契約のことです。一般的に、自社の人材やノウハウが不足している場合や、より高いクオリティを求めて外部のプロフェッショナルに業務を任せたい場合に活用されます。
前述の通り、業務委託には「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類があります。業務内容や完成義務などに相違点があるため、適切な契約形態を選ぶことが大切です。
なお、業務委託契約と派遣、雇用契約の違いは以下の通りです。
| 業務委託契約 | 派遣 | 雇用契約 | |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 業務委託契約 | 労働者派遣契約 | 雇用契約 |
| 報酬の対象 | 業務の遂行 | 業務の遂行 | 業務の遂行 |
| 完成義務 | 委任契約、準委任契約の場合:なし 請負契約の場合:あり |
なし | なし |
| 主な業務内容 | 委任契約:法律業務 準委任契約:法律業務以外の業務 請負契約:成果物の作成 |
指示された業務(一般事務や営業事務など) | 指示された業務(一般事務や営業事務など) |
| 指揮命令権 | なし | あり | あり |
| 社会保険への加入 | なし | あり | あり |
| 社会保険への加入 | なし | あり | あり |
| 勤務時間や勤務場所 | 自由 | 指定あり | 指定あり |
| 再委託の可否 | 委任契約、準委任契約の場合:委任者の許諾を得た場合、やむを得ない場合に可能 請負契約の場合:可能 |
該当しない | 該当しない |
なお、後ほど「業務委託とフリーランスの違い」にて詳しく説明しますが、業務委託は契約方法であり、フリーランスは働き方を指す言葉です。フリーランスを採用する際は業務委託契約に該当するため、混同しないようにしましょう。
業務委託と雇用契約の違い
雇用契約は、労働者が雇用主のもとで働き、労働の対価として雇用主から賃金を受け取ることを約束する契約です。業務委託契約との違いは、指揮命令権と労働法による保護の有無にあります。
業務委託の場合、発注者に指揮命令権はなく、受注者と対等な関係に置かれるのが原則です。一方で、雇用契約は雇用者に指揮命令権があるため、労働者は雇用主の命令や指示に従って働きます。
また、雇用契約で働く人は「労働者」という扱いになり、労働法が適用されるのが特徴です。社会保険や雇用保険、労災保険に加入したり、有給休暇を取得したりといった対応が求められます。なお、業務委託契約における受任者は労働者にはならないため、労働法は適用されません。
業務委託と派遣の違い
業務委託と派遣の違いは、契約形態です。派遣は、企業と人材派遣会社で労働者派遣契約を結びます。労働者派遣契約とは、人材派遣会社と雇用契約を結んだ派遣スタッフを自社で就業させることを約束する契約です。契約の締結後に、派遣スタッフの受け入れができるようになります。
派遣の場合、派遣先企業に指揮命令権があるため派遣スタッフへの指示や命令が可能です。一方で業務委託には指揮命令権がなく、発注者からの指示や命令はできません。また、派遣の受入期間は上限3年である一方、業務委託には期間の上限がなく、契約で定めた期間で依頼できます。
業務委託とフリーランスの違い
フリーランスは「働く方法」、業務委託は「契約の方法」である点に違いがあります。フリーランスとは、特定の企業に所属せず、案件ごとに契約を締結して業務を遂行する働き方のことです。一方で業務委託は、発注者と受注者が契約を結ぶ契約形態のことを指します。
なお、フリーランスでは、発注者と業務委託契約を結んで業務を行うのが一般的です。
おすすめ関連記事「業務委託とフリーランスの違いは?業務委託のメリット、デメリットから委託先の見つけ方まで解説!」
業務委託を活用する5つのメリット
業務委託を活用するメリットは、以下の通りです。
- 人材不足が解消できる
- 人件費が抑えられる
- 自社の人材がコア業務に集中できる
- 繁忙期のみなどスポットで活用できる
- 質の高い人材に依頼することで自社の成長につながる
各メリットについて、詳しく確認しましょう。
①人材不足が解消できる
業務委託には、人材不足解消というメリットがあります。社内に人手が足りず、業務の遂行が困難な場合も業務委託を活用すれば仕事が滞るのを防げるでしょう。
また、人材を確保することによって生産力向上が見込めます。現在働いている社員一人ひとりの負担も軽くなるため働きやすさが向上し、長く勤めてもらえる会社に成長できるでしょう。
②人件費が抑えられる
企業が従業員を雇用する際には、採用や研修、社会保険などさまざまな面でコストがかかります。一方で、業務委託のコストは業務委託費のみです。従業員を1から育成する費用や時間を考えると、適材適所で業務委託を活用した方が人件費の削減に繋げられるでしょう。
加えて、普段の勤務場所を委任者が指定する権利がないため、オフィスコストやエネルギーコストの削減にも繋げられます。
おすすめ関連記事「人件費の計算方法とは?人件費率の基準値や改善方法まで詳しく解説!」
③自社の人材がコア業務に集中できる
売上に直結しないノンコア業務を業務委託で外部人材に任せれば、自社の人材がコア業務に集中できるのもメリットです。問い合わせや事務処理などのノンコア業務は、コア業務よりルーティーン化しやすく、業務委託で十分に対応できるケースが多くあります。
従業員がコア業務に専念できる環境を整えることで、自社の生産性を向上させられるでしょう。
④繁忙期のみなどスポットで活用できる
業務委託は案件ごとの契約になるため「繁忙期のみ」「新しいプロジェクトが始動するときのみ」など、必要な時期にスポットで活用できます。需要に合わせて柔軟に業務を任せられるため、効率的に人材とリソースを確保できるでしょう。
また、閑散期に余剰人材を確保している状況からも脱出できるため、コスト削減にも繋げることができます。
おすすめ関連記事「【企業事例付き】コスト削減ができる4つの項目と方法|実施手順と注意点も解説!」
⑤質の高い人材に依頼することで自社の成長につながる
業務委託では、特定のスキルを備えた人材に業務を依頼できます。たとえば、企業の経営に悩みを抱えている場合は、一流企業の経営層に対して戦略コンサルティングを行なった経験のあるコンサルタントへ業務委託をすれば力強い味方になってくれるでしょう。
また、プログラミングやソフトウェア開発など専門性の高い業務を外部のプロフェッショナルに委託した場合は、高度な知識と技術を活かした成果を得られます。業務のクオリティが上がれば自社の成長にもつながり、経営の安定化を期待できるようになるでしょう。
業務委託を活用する3つのデメリット
業務委託を活用する際のデメリットは、以下の通りです。
依頼する業務内容によっては費用が高くなる
成果物のクオリティにばらつきが出る
情報漏洩のリスクがある
「社内にノウハウが蓄積されない」というのは誤解
どのような点に気をつけるべきか詳しく解説します。
①依頼する業務内容によっては費用が高くなる
業務委託は、専門性の高い仕事ほど費用が高くなる傾向があります。そのため、依頼内容によっては、報酬額が予算オーバーとなってしまうこともあるでしょう。
ただし、専門性の高い分野は社員教育を行う場合でも相応のコストがかかります。内製化した場合のトータルコストと比較して、どちらが最適か吟味しましょう。
おすすめ関連記事「業務委託費とは?|仕訳の注意ポイントや費用を抑えるコツ、報酬の決め方についても解説」
②成果物のクオリティにばらつきが出る
業務委託では、発注者が受注者のスキルを見定めてから仕事を委託することになります。受注者のスキルを精査せずに業務委託契約を結ぶと「想定より業務の質が低かった」となることもあるでしょう。
クオリティのばらつきを防ぐには、事前に実績やポートフォリオを確認し、業務に必要なスキルを備えているか確認することが大切です。
③情報漏洩のリスクがある
業務委託先に企業の機密情報や個人情報を提供する場合は、情報漏洩のリスクがあります。情報が漏洩してしまうと顧客からの信頼を失ってしまうほか、取引先や株主からの印象も悪くなり、最悪の場合業績の悪化や倒産のリスクも考えられます。
契約の際は秘密保持条項などを慎重に検討するのに加え、委託先のセキュリティ対策を確認する必要があるでしょう。
「社内にノウハウが蓄積されない」というのは誤解
「業務委託に任せると社内にノウハウや知見が蓄積されず、専門性を備えた人材を育成できない」という考えは誤解です。ノウハウを蓄積できないのは、業務委託に依存しすぎた結果、社内教育が疎かになったのが原因と言えるでしょう。
業務委託先と綿密にコミュニケーションを取りながら情報を共有し、社員教育も並行して実施することでノウハウの蓄積ができるようになります。
業務委託を行う際の注意点4つ
業務委託をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 偽装請負に注意する
- 持ち出し可能な業務をピックアップする
- 報酬は相場を見て決める
- 商品やサービスの品質を担保できるようにする
注意すべきことを押さえておけば、より効果的に業務委託を活用できるようになります。各注意点について詳しく確認しましょう。
偽装請負に注意する
偽装請負とは、業務委託として契約しているにも関わらず、受任者を派遣と同様に扱うことを指します。偽装請負とみなされるのは以下のような場合です。
- 委任者が受任者の労務時間を管理する
- 業務内容について細かく指示する
- 就業場所を指定する
偽装請負を行うと法律違反による罰則を受けてしまうため、業務範囲は契約書で細かく定めておくなどの対策を講じる必要があります。
持ち出し可能な業務をピックアップする
業務委託は、自社で行なっている業務の一部を切り取って外部に任せるものです。そのため、外部に持ち出しても問題のない業務をピックアップする必要があります。企業の運営に関わる重要な業務は情報漏洩のリスクがあり、業務委託には向かないでしょう。
また、コア業務を社員に任せることによって、生産性が向上したり企業理解が深まったりするなどのメリットが生まれます。すべての業務を委託するのではなく、依頼する業務は精査しましょう。
報酬は相場を見て決める
業務委託の報酬を決める際には、相場を確認することが大切です。業種や業務内容によって金額に幅があるため、適切な相場を把握していないと必要以上に高額あるいは少額の報酬を提案することになります。相場に見合った報酬を設定し、委任者と受任者の両方が納得のいく契約を結びましょう。
また、相場よりも極端に低い報酬で業務委託先を探すと、質の低い企業や個人事業主しか見つからないケースも少なくありません。そのため、業務委託全体の相場を調べるだけでなく、求めているクオリティを担保してくれる業務委託先の相場をチェックすることも重要です。
おすすめ関連記事「【コスト削減】業務委託の報酬の決め方は?相場や源泉徴収についても解説!」
商品やサービスの品質を担保できるようにする
契約書を作成する際には、品質基準や検査手段、報告体制など、商品やサービスの品質を担保するための項目を含めましょう。品質基準を明確にしておけば、クオリティの低い成果物が納品されるのを防げます。
また、受注先と定期的にコミュニケーションを取り、成果物の進捗状況や品質のチェックを行うことも重要です。コミュニケーションを取らないまま業務を進めてしまうと「完成品のクオリティが低いのに納期が近い」「修正に時間がかかりかえってコストがかかった」といった事態も考えられます。スムーズにプロジェクトを進行させるためにも、定期的なコミュニケーションが重要です。
業務委託契約書を作成する際に記載するべき内容一覧
業務委託契約を作成する際の記載内容は、以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 業務内容 | 委託する業務の内容や範囲、成果物の詳細、提供方法などを記載する |
| 報酬 | 報酬の金額や計算方法、支払い時期、支払い手段、業務遂行にかかる諸費用はどちらが負担するかなどを記載する |
| 契約期間・更新・解除 | 報契約期間や更新、解除の手続きについて記載する |
| 発注・受注の方法 | 全ての案件に共通する発注、受注方法があれば記載する |
| 納品・検収の方法 | 納品は発注者に成果物を渡すこと、検収は発注者が成果物を確認することを指す |
| 修正の方法 | 納品物の修正回数や修正範囲などを記載する |
| 権利の帰属 | 成果物の知的財産権が発注者と受注者のどちらに帰属するかを記載する |
| 権利の帰属 | 成果物の知的財産権が発注者と受注者のどちらに帰属するかを記載する 翻訳権、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)を発注者に移転させる場合は、その旨を記載する |
| 損害賠償の範囲 | 損害賠償が発生した際の賠償範囲、補償範囲(賠償金額の限度額や補償する損害の種類など)を記載する |
| 指揮命令権の所在 | 指揮命令権は受注側にあると記載する |
| 再委託の可否 | 委託した業務を第三者に対して再委託できるか否かを記載する 再委託にで生じた損害の責任の所在も定めると良い |
| 秘密保持 | 個人情報や機密情報の漏洩を防ぐため、情報の取り扱いについて記載する |
| 禁止事項 | 禁止事項がある場合は記載する ただし、受注者に服務規定の遵守を課した場合は偽装請負とみなされる可能性があるので注意が必要 |
| 契約の解除事由 | 受注側の業務に問題があった場合、途中で契約を解除できるようにするための解除事由を記載する |
| その他 | 所轄裁判所や瑕疵担保期間、反社会勢力の排除のための条項を記載する |
契約書の内容は、委託する業務によって異なります。自社のみで契約書を作成するのが不安な場合は、業務委託契約に詳しい弁護士や行政書士に相談すると良いでしょう。
収入印紙は契約内容によって変わる
収入印紙とは、租税や手数料などの収納金徴収を目的に政府が発行する証票のことです。収入印紙が必要か否かは、業務委託契約書の内容によって異なります。
請負契約の第2号文書と継続的取引の第7号文書に該当する業務委託契約書は、収入印紙が必要です。第2号文書の場合は、契約金額に応じて非課税〜60万円までの印紙税額が定められています。第7号文書は、一律4,000円です。
ただし、スマートフォンやパソコンなどを使った電子契約や委任契約であれば、収入印紙は必要ありません。
参考:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
業務委託契約を締結する方法と流れ
業務委託契約を締結する流れは、以下の通りです。
委託先を選ぶ
契約条件の交渉を行う
業務委託契約を締結する
業務の委託先は、フリーランスの人材紹介サイトやクラウドソーシングサイトなどで見つけられます。条件交渉では、業務内容や契約期間、報酬金額、支払い方法、禁止事項などを決め、受任者から見積書を出してもらいましょう。お互いに合意できたら業務委託契約書を作成し、契約を締結します。
業務委託に関するよくある質問
業務委託のよくある質問をQ&A方式でまとめました。疑問を解消するために役立ててください。
- 業務委託契約を解除する際はどうすればいい?
- 依頼先の探し方は?
- 業務委託ではどんな仕事が依頼できる?
- どんな行為をしたら法律違反になり得る?
業務委託契約を解除する際はどうすればいい?
委任契約(準委任契約)では、委任者と受任者のどちらからでも契約解除の申し出が可能です。ただし、請負契約の場合は成果物が完成していない場合か、成果物が求めている基準に達しておらず、目的が達成できない場合にしか契約解除ができません。
成果物に問題があるにも関わらず契約解除を申し出ると、契約違反になる可能性があります。事前に、契約形態と契約書に記載した解除事由を確認してください。委任者と受任者で解除に合意できたら業務委託の契約解除合意書を作成し、署名捺印をしましょう。
依頼先の探し方は?
依頼先は、フリーランスの人材紹介サイトや人材マッチングサイト、クラウドソーシングサイトなどで探せます。
なお、フリーランスの優秀な人材をお探しの場合は「フリーコンサルタント.jp」の利用がおすすめです。各分野に特化したプロフェッショナル人材が、目標達成に向けて伴走してくれます。相談は無料のため、ぜひ一度お問い合わせください。
業務委託ではどんな仕事が依頼できる?
業務委託では、さまざまな仕事の依頼が可能です。たとえば、以下の業務が挙げられます。
- IT系の開発
- デザインなどのクリエイティブ制作
- コンサルティング
- 事務
- 運営代行
- 財務顧問
- 訴訟代理人
ただし、依頼する業務内容によって契約形態が異なるため、注意しましょう。契約形態の詳細は当記事の「業務委託の種類」で解説しています。
どんな行為をしたら法律違反になり得る?
発注事業者が優越的な地位を利用し、フリーランスに不当な不利益を与えることは優越的地位の濫用とみなされ、独占禁止法によって規制されます。規制対象となる行為は、以下の通りです。
- 報酬の減額
- 報酬の支払遅延
- 一方的な発注の取り消し
- やり直しの要請
また、偽装請負(業務委託契約であるのにも関わらず実態は労働者派遣と同様の扱いをすること)を行うと法律違反による罰則を受ける恐れがあるため注意しましょう。
まとめ
業務委託は、自社の人材不足を解消したり、繁忙期のみ依頼できたり、さまざまな面で利点があります。ただし、成果物の質にばらつきが出る、情報漏洩のリスクがあるといった懸念点も存在するため、事前に発注者のスキルや信頼性を確認することが大切です。
委任者と受任者の双方が気持ち良く業務に専念できるよう、必要な知識を備えた上で業務委託契約を結びましょう。