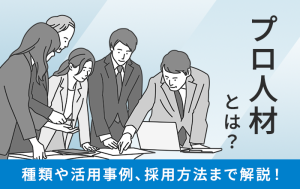「契約社員と業務委託の違いがわからない」「契約社員と業務委託のどちらを採用すべきかわからない」こんなお悩みはありませんか?
業務委託と契約社員は契約形態が異なり、必要となる費用や業務指示の可否などが変わります。コストを抑えながら必要な労働力を確保するには、それぞれの違いを正しく理解することが重要です。
本記事では、契約社員と業務委託の違いをわかりやすく簡単に解説します。ぜひ、外部に業務を委託する際の参考にしてください。
【こんな人におすすめ】
- 契約社員や業務委託の雇用形態を導入しようとしている企業の採用担当者
- それぞれの雇用形態のメリットや注意点、コストを理解して、最適な形で人材を確保したい経営者
■目次
契約社員と業務委託の違いは?
.png)
契約社員と業務委託は、契約形態や雇用関係などに違いがあります。主な違いについて、表にまとめました。
| 契約社員 | 業務委託 | |||
|---|---|---|---|---|
| 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | ||
| 概要 | 雇用期間を定めた有期雇用契約を結んでいる社員 | 依頼された仕事を完成させることを約束し、その成果に対して発注者が報酬を支払う契約 | 委任者が代理人または委任人に特定の業務や権限を委託する契約。業務内容の対象は法律行為に限る。 | 特定の業務を委託する契約。法律行為に限られず、書類作業や開発業務などさまざまな業務が対象。 |
| 契約形態 | 雇用契約 | 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 |
| 雇用関係 | 雇雇用関係あり | 雇用関係なし | 雇用関係なし | 雇用関係なし |
| 労働条件 | 原則として最長3年(専門職など特定の条件がある場合は5年)の雇用期間が定められている。 一定の条件を満たせば正社員と同様の社会保険への加入が可能。 休日・休暇・有給休暇の取得も正社員と同じ扱いとなる。 退職金や扶養手当、住宅手当といった福利厚生は企業によって方針が異なる。 |
雇用保険や厚生年金、労災保険といった企業の社会保険には加入できず、福利厚生も対象外。 | 雇用保険や厚生年金、労災保険といった企業の社会保険には加入できず、福利厚生も対象外。 | 雇用保険や厚生年金、労災保険といった企業の社会保険には加入できず、福利厚生も対象外。 |
| 報酬の対象 | 業務の遂行 | 業務の遂行 | 業務の遂行 | |
| 使用従属性 | あり | なし | なし | なし |
業務委託には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」と呼ばれる3つの契約形態があり、依頼主との雇用関係はありません。一方で、契約社員と企業の間には雇用関係があります。それぞれの違いについてさらに詳しく解説しますので、参考にしてください。
契約社員とは
契約社員とは、雇用期間を定めた有期雇用契約を結んでいる社員のことです。雇用期間は「原則として最長3年(専門職など特定の条件がある場合は5年)」と労働基準法で定められています。一般的には1年契約を結び、年度ごとに契約の更新、終了を決めるケースが多いです。
また、一定の条件を満たす契約社員に対しては、正社員と同じく各種社会保険に加入させる必要があります。休日や休暇も正社員と同様に認められており、有給休暇の許諾も必須です。退職金や扶養手当、住宅手当といった福利厚生は企業によって方針が異なり「正社員のみ対象」とすることもできます。
なお、契約社員の立場は労働基準法によって保護されています。「契約期間中の解雇制限(やむを得ない事由がある場合でなければ契約期間の途中で解雇できない)」「同一労働同一賃金(正社員とそれ以外の労働者の間で不合理な待遇差を設けることを禁ずるルール)」などの規定が設けられているため、雇用契約を結ぶ際には注意が必要です。
業務委託とは
業務委託契約とは、自社で行なっている業務の一部を企業または個人に委託する契約のことです。具体的には、以下の契約を指します。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
各契約について詳しく確認しましょう。
請負契約とは
請負契約とは、委託者は依頼された仕事を完成させることを約束し、その成果に対して発注者が報酬を支払う契約のことです。請負契約を結ぶ具体的な職種としては、ライターやデザイナー、プログラマーなどが挙げられるでしょう。
請負契約を採用する場合は雇用関係が生じないため、雇用保険や厚生年金、労災保険といった社会保険は必要ありません。また、休暇制度などの福利厚生も対象外です。
委任契約とは
委任契約とは、委任者が代理人または委任人に特定の業務や権限を委託する契約のことです。業務内容の対象は法律行為に限られます。
法律行為とは、当事者の意思表示によって法的な効力が生じる行為のことです。委任契約を結ぶ職種は、弁護士や司法書士、税理士などが挙げられ、たとえば「自分の訴訟行為の代理を弁護士に依頼する」といった場合は委任契約に当たります。
委任契約も企業側との雇用関係が生じないため、社会保険や福利厚生は対象外です。
準委任契約とは
準委任契約とは、特定の業務を委託する契約のことを指します。法律行為に限らず、書類作業や開発業務といったさまざまな業務が対象です。そのため、医師や事務、コンサルタント、ドライバー、美容師など、多様な職種で準委任契約が結ばれます。準委任契約も企業側との雇用関係が生じないため、社会保険や福利厚生は対象外です。
派遣社員との違い
派遣社員とは、派遣会社と派遣契約を締結した上で、派遣会社が雇用契約を結んだ労働者を受け入れることを指します。
契約社員との違いは、労働者との雇用関係が異なる点です。派遣社員の場合、雇用主は派遣会社になるため、給与の支払いや社会保険の加入などは自社ではなく派遣会社が行います。
業務委託との違いは、業務指示の可否です。派遣社員の場合、派遣先企業(自社)に指揮命令権があるため、業務のやり方や勤務時間などを指定したり、社内ルールの遵守を求めたりできます。一方で、業務委託では発注者と受注者は対等な関係にあり、仕事のやり方や進め方を指示できないのが原則です。
契約社員と業務委託の違いは「使用従属性」で見分けられる
使用従属性とは、労働基準法で定められた「労働者」に該当するために必要な条件のことです。使用従属性があれば、雇用主と労働者という関係が成り立ちます。
契約社員は使用従属性があり、雇用主の指揮命令に従って働いてもらえる一方、労働基準法をはじめとした労働法の保護を適用する必要があるのが原則です。
業務委託には使用従属性がなく、独立した個人または企業間での契約になります。発注者は指揮監督権がないものの、労働法で保護する必要がありません。
なお、使用従属性が認められる条件は、以下の通りです。
| 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 | 自由がない場合は使用従属性がある |
| 業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 | 業務遂行上の指揮命令関係が強い場合は使用従属性がある |
| 勤務場所・勤務時間の拘束性の有無 | 拘束性がある場合は使用従属性がある |
| 通常予定される業務以外の業務の有無 | 業務がある場合は使用従属性がある |
| 労務提供の代替性の有無 | 代替性がある場合は使用従属性がある |
| 報酬の基準が時間基準か成果基準か | 時間基準の場合は使用従属性がある |
| 欠勤時に賃金が控除されるか | 控除される場合は使用従属性がある |
| 残業手当がつくか否か | つく場合は使用従属性がある |
| 機械、器具、原材料の負担関係 | 会社負担である場合は使用従属性がある |
| 就業規則・服務規律の適用がされるかどうか | 適用される場合は使用従属性がある |
| 退職金制度、福利厚生制度が適用されるかどうか | 適用される場合は使用従属性がある |
| 給与所得として源泉徴収されるかどうか | 源泉徴収される場合は使用従属性がある |
参考:厚生労働省「労働基準法の『労働者性』の判断基準について」
契約社員のメリットとデメリット
契約社員のメリットとデメリットは以下の通りです。
- メリット①企業が指示を出して業務を進められる
- メリット②人員の数を調整しやすい
- デメリット①原則契約期間は3年間
- デメリット②労働者の希望に応じて正規雇用する必要がある
ここからは、各メリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット①企業が指示を出して業務を進められる
企業と契約社員は雇用関係にあるため、企業側が直接指示を出して業務を進められます。仕事の進め方や労働時間などの指示、管理ができれば、企業の意向に沿った業務の遂行が可能です。想定通りの成果が期待できるため、スケジュールに遅れが出にくく、品質も担保しやすい特徴があります。
また、作業を進めていく中で想定外のトラブルが発生した際にも対応しやすく、柔軟に動きやすい点もメリットです。
メリット②人員の数を調整しやすい
契約社員には労働契約期間の定めがあるため、正社員と比べて人員の数を調整しやすいのもメリットです。
たとえば、新規事業の立ち上げや繁忙期などで人員確保が必要な時期に契約社員を採用し、閑散期には新規採用や契約更新を行わない、といったやり方で調整ができるでしょう。正社員採用よりも柔軟に動きやすい点がポイントです。
デメリット①原則契約期間は3年間
労働基準法において、契約社員の契約期間は最長3年と定められています。契約の更新がない場合は3年ごとに新しい人材を確保し、最初から業務指導を行わなければなりません。長期間にわたる育成が難しいため、責任の大きな仕事を任せづらい状況も発生するでしょう。
デメリット②労働者の希望に応じて正規雇用する必要がある
労働契約法では、無期転換ルール(同じ企業で雇用契約が更新され、契約期間が通算5年を超えた場合、労働者の希望に応じて無期雇用契約に転換できる)が定められています。
条件を満たした労働者が無期転換を申し込んだ場合、企業側は拒否できません。能力不足の労働者から無期転換を申し込まれたり、余剰人員が生じた場合の調整が難しくなったりといったリスクがあるため、注意が必要です。
業務委託のメリットとデメリット
業務委託のメリットとデメリットは以下の通りです。
- メリット①専門性のある人材を確保できる
- メリット②コストを抑えられる
- デメリット①依頼内容によってはコストが高くなる
- デメリット②偽装請負には注意が必要
各メリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット①専門性のある人材を確保できる
業務委託のメリットは、特定のスキルやノウハウを備えた専門性のある人材を確保できることです。たとえば自社のWebサイトをリニューアルする場合、社内にWeb関係の知識を持つ人材がいなければ、Web制作会社や個人のWebディレクターなどに業務委託で依頼できます。専門性の高い人材に業務を依頼することによって社員の教育コストを抑えられるうえ、クオリティの高い成果物が期待できるでしょう。
このように社内に人材のリソースがなく、業務に専門性が求められる場合に業務委託が役立ちます。
メリット②コストを抑えられる
新しく社員を採用したり、育成したりといったコストをかけずに業務を任せられるのも業務委託のメリットです。社員の採用や育成には、さまざまな面で時間や費用がかかります。業務委託なら、採用や育成にかかるコストを抑えながら即戦力となる人材に業務を任せられるでしょう。
また、専門分野に特化した人材であればスキルや作業環境も最新のものを取り入れているため、余計な予算を割かなくて良い点もメリットです。
デメリット①依頼内容によってはコストが高くなる
業務委託は、専門性の高い仕事ほど費用が高くなる傾向があります。依頼内容や頻度によっては、コストが割高になる可能性もあるでしょう。たとえば、自社では対応できないほどハイレベルなコーディングを外注する場合、しっかりとコミュニケーションを取らないと社内の人材が育ちにくく、似たような案件が発生した際には再度外注する必要が出てきます。また、後から自社の都合で修正が必要になった際に追加費用が発生するなど、コストが膨れ上がる可能性もあるでしょう。
上記を踏まえ、業務委託は費用対効果を加味した上で依頼するかどうかを決める必要があります。
デメリット②偽装請負には注意が必要
偽装請負とは、業務委託契約であるのにも関わらず実態は労働者派遣と同様の扱いをしていることを指します。たとえば、発注側が受注側に細かく業務の指示を出したり、勤務時間を管理したりした場合は偽装請負とみなされるでしょう。
偽装請負を行うと法律違反による罰則を受けるリスクがあるため、注意してください。
契約社員と業務委託に必要な費用
契約社員と業務委託には、それぞれに必要な費用があります。どのような費用があるのか、詳しく確認しましょう。
- 契約社員にかかる費用
- 業務委託にかかる費用
契約社員にかかる費用
契約社員には、以下の費用がかかります。
- 有期雇用契約に従った月給
- 残業や夜勤の各種手当
- 社会保険料
- 交通費補助
- 業務上必要な備品の購入補助
このほか、社内規定に従って昇給に対応する必要もあるでしょう。柔軟に社員を動かしやすい反面、固定コストが大きいというデメリットがあります。
業務委託にかかる費用
業務委託にかかる費用は、業務委託費のみです。業務委託費は業務の量や範囲、専門性の高さなどを考慮して決められるため、必要な業務に絞り込んで依頼することでコストを削減できるでしょう。
なお、契約書には支払額と支払基準を明記する必要があります。報酬周りはトラブルが発生しやすい箇所でもあるため、事前に定めておくことが重要です。
契約社員や業務委託を活用する際の注意点
契約社員や業務委託を活用する場合には、気をつけたいことがいくつかあります。
- 契約社員を雇う際の注意点
- 業務委託を行う際の注意点
主な注意点について解説しますので、参考にしてください。
契約社員を雇う際の注意点
契約社員と契約を結ぶ際は、業務範囲や責任の度合いなどを詳細に決めておく必要があります。曖昧な契約内容だと、後からトラブルが生じやすくなるため注意しましょう。
また、解雇への対応にも注意が必要です。労働契約法において、契約期間中における解雇は「やむを得ない事由」があるケース以外は認められていません。よほどのことがなければ契約期間中の解雇はできないため、契約社員の人選は慎重に行ってください。
業務委託を行う際の注意点
業務委託では、信頼できる相手であるかきちんと精査してから契約を交わすことが大切です。ポートフォリオや過去の実績を確認し、業務に必要なスキルを備えていると判断できた場合に契約を結びましょう。
契約書には、具体的な契約内容を明記するのはもちろん、機密情報の適切な保護と管理に関する項目も含めておくと安心です。万が一契約書の内容に不安がある場合は、専門家のチェックを受けることで重要事項の漏れが無くトラブルや無駄な支出を減らすことができます。
契約社員と業務委託のどちらを採用すれば良い?
契約社員と業務委託で迷った場合は、ジョブディスクリプションを作成するのがおすすめです。ジョブディスクリプションとは、業務の内容や範囲、求めるスキル、経験、難易度などを記載した書類のことを指します。どのような人材が必要なのか明確にすることで、契約社員と業務委託のどちらを採用すべきか判断しやすくなるでしょう。
なお、プロジェクトリーダーなど正社員と同等の役割や仕事を任せる場合は、雇用関係を結べる契約社員を採用するのが一般的です。業務委託は、専門知識を備えた即戦力の人材をすぐに確保したい場合に重宝します。また、案件ごとに契約を結ぶことになるため、小規模の案件を一時的に任せたいときにも業務委託が最適です。
フリーコンサルタント.jpでは、フリーランスのプロフェッショナル人材を24,000人以上保有しています。貴社のご要望に合わせてマッチした人材を柔軟に紹介いたしますので、業務委託を考えている方は、お気軽にご相談ください。
一般的にコストを削減できるのは業務委託
コスト削減を優先する場合は、業務委託を選ぶのも1つの方法です。業務委託に必要な費用は業務委託料のみであり、社会保険や交通費などの福利厚生のコストはかかりません。一方で契約社員は福利厚生のコストに加え、年末調整をはじめとした労務管理の手間もかかります。
ただし、専門性の高い業務を依頼する場合は、業務委託費が高額になりやすい点には注意しましょう。任せたい業務内容を検討した上で、契約社員と業務委託を比較検討してください。
雇用契約と業務委託契約は同時に締結できる
雇用契約と業務委託契約は、同時に締結することが可能です。たとえば契約社員の場合、収入アップを目的に業務外の時間を利用して会社の仕事を請け負うケースが考えられるでしょう。
ただし、雇用契約と業務委託契約を同時に締結する際に注意しておきたいのが、業務範囲です。雇用契約の業務範囲と業務委託契約の業務範囲が重複すると、別契約を結んだ意味がなくなります。それぞれの業務範囲を明確に区別し、重ならないようにしてください。
業務委託の場合はフリーランス人材の活用がおすすめ
フリーランスとは、企業に所属せず個人で仕事を請け負う仕事のスタイルです。仕事を受注する際に業務委託契約を結ぶため、フリーランスも業務委託に分類されます。
経済産業省の調査によると、約5割の企業が「個人事業主、フリーランスを活用している」「個人事業主、フリーランスの活用を検討している」との結果が出ました。特に情報、通信業はフリーランスを活用している割合が高く、活用が進んでいます。

参考:経済産業省「労働市場の構造変化の現状と課題について」
昨今では、少子高齢化や働き方改革などの理由から各企業の労働力不足が深刻になっています。労働力を確保しようと個人事業主やフリーランスを確保している企業が主流になっており、これからも外部人材を活用する企業は増えていくと予想できるでしょう。
フリーランスでプロフェッショナル人材を活用するメリット
フリーランス活用のメリットは、スキルのある人材をすぐに採用できることです。人材を1から育成する手間やコストをかけず、高い成果を期待できます。また、社会保険や福利厚生のコストがかからないのもメリットです。
即戦力となるフリーランスをお探しの際は、プロフェッショナル人材紹介サービス「フリーコンサルタント.jp」がおすすめです。登録人材数24,000人以上と国内最大級の規模を誇り、質の高い人材のみを紹介しているため、企業のさまざまな課題に対応できます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
契約社員や業務委託契約を結ぶフリーランスを探す方法3つ
契約社員やフリーランスを探す方法は、以下の通りです。
- エージェントサービスを活用する
- 人脈を活用する
- プロフェッショナル人材のマッチングサービスを活用する
それぞれの方法について、詳しく解説します。
エージェントサービスを活用する
エージェントサービスとは、フリーランスの人材と企業の間に立って案件の紹介や契約のサポートを行うサービスのことです。エージェントに登録しておけば、自社で採用活動をすることなく適切な人材を紹介してくれます。
エージェントサービスを活用する際は、求めている人物像をエージェント側にしっかりと伝えておくのがポイントです。「経験年数〇年以上」「××のスキルを保有している」など具体的にしておくことで、ミスマッチが起こりづらくなります。
人脈を活用する
知り合いの人脈からフリーランス人材を探す方法もあります。知り合いの紹介であれば、実績やスキルにも信頼性があり、安心して仕事を任せられるでしょう。
ただし、人脈のみだと選択の幅が狭くなるため、適切な人材が見つからない可能性もあります。
プロフェッショナル人材のマッチングサービスを活用する
プロフェッショナル人材のマッチングサービスとは、企業と人材をつなぎ合わせるサービスのことです。詳細な募集項目を伝えるだけでプロがマッチした人材を紹介してくれるため、採用活動の手間をかけることなくスキルの高い人材と出会えるでしょう。また、サービスによっては業務委託を経てから正社員として人材を雇用することもできるため、採用コストも削減できます。
優秀な人材をお求めの場合は、プロフェッショナル人材マッチングサービス「フリーコンサルタント.jp」を利用してみてはいかがでしょうか。登録人材の実績やスキル、人柄などを把握している専門コーディネーターが貴社の課題にマッチした人材をご提案します。最短即日~3日以内に即戦力人材と出会えるため、すぐに業務を任せたい場合もお気軽にご相談ください。
まとめ
契約社員と業務委託は契約形態が異なり、メリット、デメリットにも違いがあります。
【契約社員のメリットとデメリット】
【業務委託のメリットとデメリット】
正社員と同等の責任ある仕事を任せるなら契約社員、即戦力となる人材をすぐに欲しい場合は業務委託、といったようにシーンに合わせて選ぶことが大切です。
自社の状況と合致する契約形態を検討した上で、最適な人材を見つけましょう。