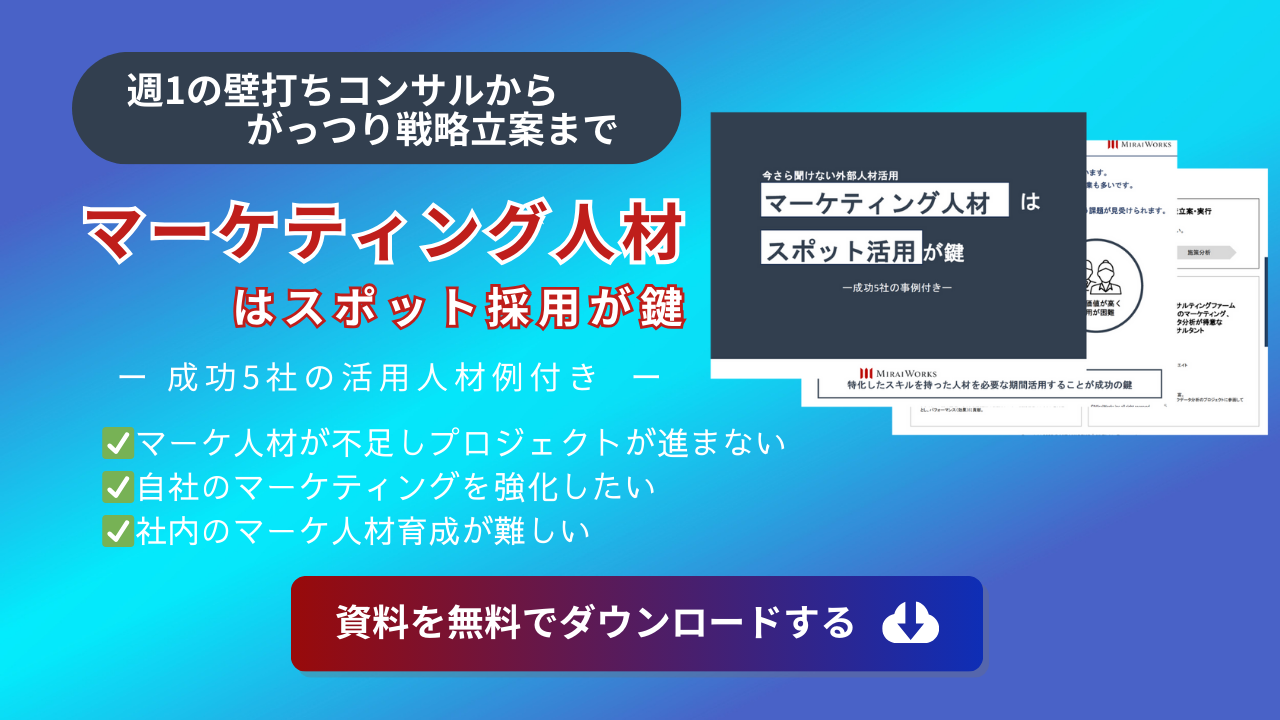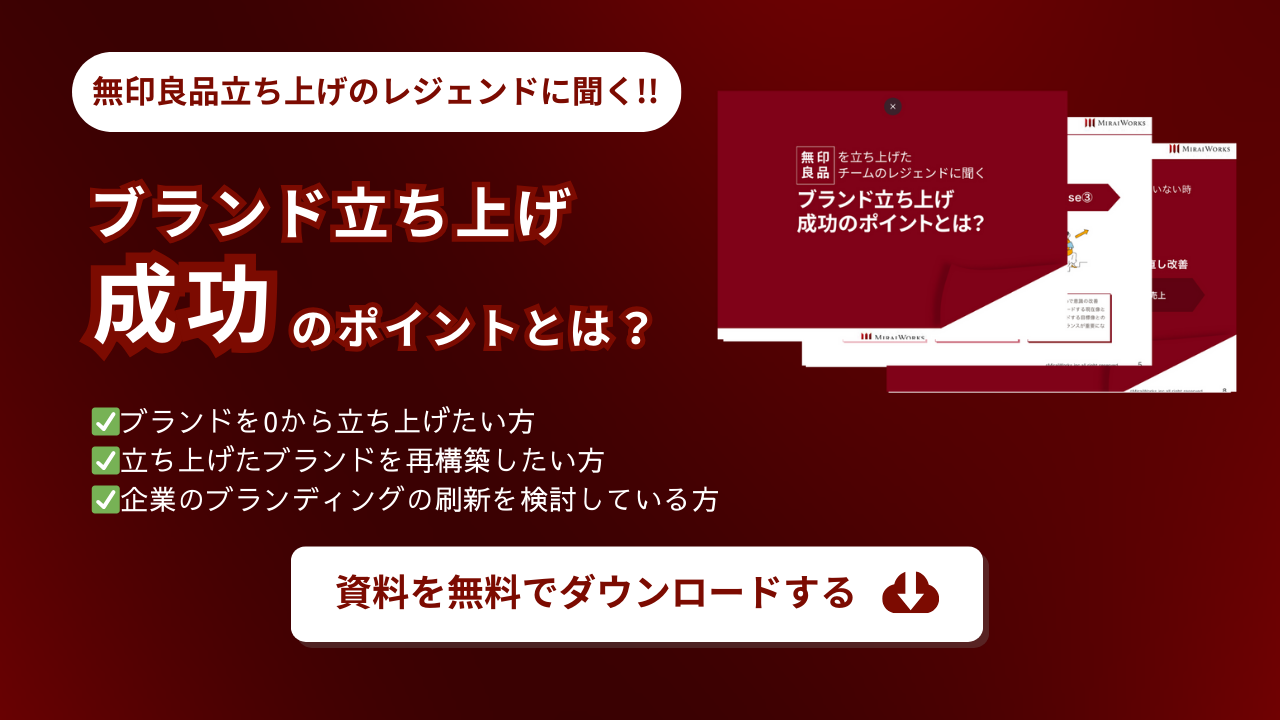プロダクトアウト、マーケットイン、なんとなく理解したような気になっていませんか?
プロダクトアウトとマーケットインの考え方は、商品開発にとって非常に重要です。しっかり理解しておかないと、失敗に終わり多大な損失につながる可能性もあるでしょう。
本記事では、下記についてご紹介します。
自社に適している戦略がどちらなのか理解できる内容となっているため、商品開発の経験が浅い方はぜひ最後までご覧ください。
■目次
1.プロダクトアウトとマーケットインの違い

プロダクトアウトとマーケットインでは、戦略の方向性に違いがあります。
簡単にまとめると、以下の通りです。
商品開発の出発点が企業側にあるか、消費者側にあるかで訴求ポイントが大きく変わるため、戦略の方向性を決定する上で重要な要因と言えます。ただし、商品を投下するマーケットやターゲット層、自社を取り巻く環境などによっては一概にどちらの戦略が正しいかは判断できません。
重要なことは「消費者に需要のある価値が提供できるかどうか」です。そのため、場合によっては、両方の考え方を取り入れた戦略も必要になるでしょう。ここからは、プロダクトアウト、マーケットインの特徴をご紹介します。
プロダクトアウトとは
プロダクトアウトとは、自社の強みやノウハウを活かした「企業が作りたい、売りたい商品を販売する戦略」を指します。企業側の考え方や独自性が色濃く反映されるため、他社との差別化を図るには最適な手法です。
また、未開発の市場に価値を提供することで、潜在的なニーズを掘り起こすこともできます。言い換えれば「良い商品であれば売れる」時代にマッチした戦略と言えるでしょう。
成功した事例としては、iPhone、ウォークマン、ポケモンGOなど、発売当初は今までに無い商品性やサービスとして好評を得ました。
マーケットインとは
マーケットインとは「消費者ニーズを重視した商品を開発し販売する戦略」を指し、現代における主流のマーケティング手法です。アンケート調査やSNSの口コミなどを通じ、消費者が求めているものを開発し提供することで、リピーターの獲得を目指します。
言い換えれば「売れるものを作る」ことに商品開発の軸を置いており、プロダクトアウトとは真逆の考え方と言えるでしょう。
成功事例としては、ライザップ、USJ、ロボット掃除機など、消費者の日頃から困っている課題を解決する商品性やサービスという共通点があります。
2.プロダクトアウトのメリットとデメリット
プロダクトアウトは企業の独自性を発揮できるため、成功すれば市場を独占するような利益を生み出せる一方で、上手くいかなければ大きな損失を抱えるリスクもあります。
自社にとって最適な選択をするためには、良い面だけでなく、リスクについても正しく理解しておくことが重要です。この章では、プロダクトアウトを取り入れることで得られる3つのメリットと、注意すべき2つのデメリットについて解説します。
プロダクトアウトのメリット
プロダクトアウトは「企業が作りたいもの、自信のあるものを売る」という企業主体の戦略です。実施するメリットには次の3つがあります。
- 自社の強みを活かし、他社との差別化ができる
- 爆発的な売り上げをもたらす可能性がある
- 既存リソースを活用し、低コストで開発できる
プロダクトアウトは、独自性が高いほど競合のいない市場(ブルーオーシャン)を独占できる可能性が高くなります。

そのため、ブランドイメージの定着による安定した収益が見込めるでしょう。
また、顧客ニーズの枠にとらわれない自由な発想により、消費者の潜在的な欲求を満たすことで、爆発的な売り上げに繋がる可能性もあります。
プロダクトアウトのデメリット
プロダクトアウトの導入前に把握しておくべき主なデメリットは以下の2つです。
- 消費者ニーズに合わないため、売れない場合がある
- 製品の改善に大きなコストが必要となる
企業側の「売りたい」という思いが先行し、実際の消費者ニーズと乖離することで、製品が受け入れられないリスクがあります。たとえ、革新的な技術やアイデアの商品でも、ニーズにマッチしないと独りよがりな商品だと市場に判断されてしまうのです。
また、需要がないと判明すれば、開発、販売にかかったコストは無駄になり、製品改善、戦略の見直しに追加のコストと時間が必要になってしまいます。軌道修正を図るには多くの労力がかかり、改善が難しいと判断されれば、事業撤退の検討が必要になってしまうのがプロダクトアウトの大きなデメリットといえるでしょう。
3.マーケットインのメリットとデメリット
マーケットインは顧客ニーズを起点にするため、ビジネスの成功確率を高められる一方で、他社との差別化が課題となることもあります。
メリットとデメリットの双方を把握し、自社の目的に合致するか見極めることが大切です。この章では、マーケットインを採用する3つのメリットと、事前に知っておくべき2つのデメリットについて解説します。
マーケットインのメリット
マーケットインは「顧客が求めているものを作る」という顧客主体の戦略です。マーケットインには、ビジネスの確実性を高め、効率的な経営を実現できる3つのメリットがあります。
【マーケットインのメリット】
- 売れる可能性の高い製品を生み出せる
- 売上の予測が立てやすい
- 開発目標が設定しやすい
事前調査により顧客ニーズを把握できるため、市場に受け入れられる確率が高まり、企業側の思い込みによる失敗を防ぐことが可能です。また、市場データに基づいて一定の売上見込みを立てられることから、過剰在庫のリスクを減らし、予算や人員の限られたリソースを無駄なく配分できます。
ターゲットや解決すべき課題もハッキリしているため、機能や価格の設定がスムーズに進められるのもマーケットインの特徴です。

社内の合意形成も簡単になり、開発から販売までのスケジュールが設定しやすいでしょう。
マーケットインのデメリット
反対に、顧客の声を重視しすぎるマーケットインには、企業の独自性が失われるリスクも潜んでいます。導入前に把握しておくべき主なデメリットは、以下の2つです。
- 他社と製品の特徴が似通ってしまう場合がある
- 自社の強みを活かせない場合がある
マーケットインは、多くの企業が同じ顧客ニーズに応えようとするため、差別化が難しくなってしまうのが大きなデメリットです。価格競争に陥り、収益性が圧迫されるリスクが高まります。また、顧客ニーズを優先すると、市場で求められる標準的な仕様を選択せざるを得ず、企業の個性が薄れてブランド力の低下に繋がってしまうのもマーケットインのデメリットといえるでしょう。
4.プロダクトアウトはなぜ時代遅れといわれるのか
「プロダクトアウトが時代遅れ」といわれるようになったのは、企業が売りたい商品と消費者が求める商品との間にズレが生じやすくなったためです。
モノが不足していた時代とは異なり、現代は製品が市場に溢れ、消費者の選択肢が大幅に増加しました。現代の消費者は高性能な製品を求めているわけではなく「自分の悩みを解決できるか」を基準に選ぶ傾向が強いです。そのため、企業の技術やこだわりを優先しすぎると、市場に受け入れられないリスクが高まってしまいます。よって、顧客の声を起点とするマーケットインの考え方が、現代のビジネスに適していると評価されているのです。
しかし、プロダクトアウトそのものが時代遅れになったわけではありません。顧客自身の気づいていない潜在ニーズを掘り起こして、顧客が将来抱える課題を想定した商品作りはプロダクトアウトの価値を最大限に引き出してくれるでしょう。
5.プロダクトアウト、マーケットインはどっちがいいの?
どちらが良いかという考えは、現代の製品開発において適切ではありません。自社の置かれている状況や、取り扱う商材の特性によって適切な戦略を選択する必要があります。
判断に迷う場合は、以下の基準を参考に使い分けると良いでしょう。
■プロダクトアウトが向いているケース
- 他社に真似できない圧倒的な技術力や独自性がある
- まだ世の中にない市場でイノベーションを起こしたい
- 失敗リスクを吸収できる資本力と長期的視点がある
■マーケットインが向いているケース
- 競合が多い成熟した市場でシェアを拡大したい
- 顧客の不満や解決すべき課題が明確に把握できている
- 限られた予算で成果を求めたい
たとえば、独自技術で新市場を作りたい場合はプロダクトアウトが適しており、既存市場で顧客の明確な不満を解決したい場合はマーケットインが有効です。
また、現代では両者を明確に区別せず、柔軟に組み合わせる「ハイブリッド型」の考え方が主流とされています。市場の声を聴きながら、自社の強みを掛け合わせることで、リスクを抑えつつ競争力のある商品を生み出すことが可能です。
6.プロダクトアウト、マーケットインの具体的な進め方
プロダクトアウトとマーケットイン、どちらのアプローチを採用する場合でも、自社の状況に合わせた適切なプロセスが重要になります。
たとえば「他社にはない圧倒的な技術力や独自性がある」「未開拓の市場でイノベーションを起こしたい」と考えているなら、自社の強みを起点にするプロダクトアウトが最適です。逆に、確実性を重視するなら顧客の声を起点にするマーケットインが有効といえるでしょう。
次項より、それぞれのアプローチにおける具体的な進め方を解説します。自社がどちらの戦略をとるべきか迷っている場合や、プロジェクトの進行に悩んでいる場合は、以下の進め方を参考にしてください。
マーケットインの進め方
マーケットインは「顧客が欲しいもの」を起点とするため、リサーチからスタートします。失敗のリスクを抑え、確実な需要を狙うための具体的な進め方は、以下のとおりです。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| ①市場調査とターゲットの選定 |
|
| ②顧客ヒアリングと仮設の構築 |
|
| ③プロトタイプの作成とテスト販売 |
|
| ④改善と本格リリース |
|
マーケットインの進め方のポイントは、開発の初期段階から顧客を巻き込むことです。「作ってから売る」のではなく「売れるとわかってから作る」という意識で取り組むことが重要です。
プロダクトアウトの進め方
プロダクトアウトは「自社の強み」を起点とするため、技術の棚卸しから始めます。市場に新しい価値を提案するための具体的な進め方は、以下のとおりです。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| ①技術、リソースの棚卸し |
|
| ②提供価値の仮説を立てる |
|
| ③製品開発とアプローチの選択 |
|
| ④アーリーアダプターへのアプローチ |
|
| ⑤市場教育とストーリーテリング |
|
プロダクトアウトの成功には、熱狂的なファンの存在が必要です。最初から万人に受け入れられようとするのではなく、特定の層に刺さるコンセプトを追求することが、結果として大きな市場を切り開くきっかけになります。
7.プロダクトアウトもマーケットインも『消費者ニーズ』が重要
現代においてプロダクトアウトは古いとされており、マーケットインの戦略を重視する傾向にあるものの、一概にどちらが良くてどちらが悪いとは言い切れません。実際にマーケットインの戦略を採用した失敗例も多数あります。
たとえば、導入直後は大きな反響を呼んだセグウェイ(立ち乗り式自動2輪車)や次世代規格として期待されたHD DVDなど、今となっては見る影もありません。戦略自体に優劣はなく、市場環境や消費者のニーズにより選択すべき戦略は変わります。
また、これからの時代はプロダクトアウトとマーケットインをミックスした戦略が鍵を握ります。両方の戦略の良いとこ取りをすることで、ユーザーの満足度を満たしつつ、リスクを最小限に抑える方法が主流になる可能性もあるでしょう。
どの戦略を選択するにせよ、共通して言えるのは「消費者ニーズ」が重要ということです。各戦略のメリットを理解し、消費者、企業にとってベストな選択をしましょう。
8.プロダクトアウトの成功事例3つ
過去の成功事例を見てみると、プロダクトアウトに基づいた考え方により、後世に残るような大ヒット商品が生まれています。
ここからは、プロダクトアウトの成功事例を3つご紹介します。
いずれも皆さんが一度は目にしたことのある商品やサービスばかりなため、ぜひ一度チェックしてみてください。
1.iPhone
プロダクトアウトの成功例として最も有名なのがiPhoneです。iPhoneが誕生する前の携帯電話市場は、ボタンを操作して電話やメール、アプリなどを利用する旧型の携帯電話が主流でした。
しかし、それを覆したのが、2007年当時AppleのCEOを務めていたスティーブ・ジョブズです。これまでの携帯電話と違い、直接画面を指で触ることで操作するタッチパネルを採用しました。
その結果、操作性は格段に上昇し、携帯電話市場をあっという間に席巻し、2023年には世界のスマホ市場で世界No1※の市場シェアを獲得しています。
また、Appleが行うプロモーションにおいても、これまでの常識とは異なる戦略が行われています。それは、新製品のリリースまでは外部に情報が漏れないよう情報管理を徹底し、リリース時のイベントでは企業のトップが、メディアを通じてトップセールス(宣伝販売活動)を行うというものです。あえて情報管理を徹底することで情報に対する興味をひき、そのうえで世界敵に有名な経営者が大々的に宣伝する、これによりAppleは多くの消費者やメディアの関心を集めています。
その結果、現在までに多くのユーザーを抱える人気商品へと成長しています。
※Appleは2023年のスマートフォン市場で過去最高の市場シェアを獲得しトップの座を獲得
2.ウォークマン
1970年代は、ステレオ型のテープレコーダーを家庭で使用するのが普通とされていました。誰もがテープレコーダーを持ち運んで音楽を聞くなど考えもしない時代に、SONYが発表した「ウォークマン」は革新的な製品として一大ブームを起こします。
商品のコンセプトは「音楽を携帯し気軽に楽しむ」という新しいもので、手のひらサイズで歩きながら音楽を聞けることに、当時の若者は熱狂し、瞬く間に売上を伸ばしました。
また、販売戦略でも当初は「ウォークマン」の呼び名が、国外では悪い印象を与える意味ととらえられるため「Free Style(フリー スタイル)」の商品名で発売されていました。
しかし、国内、国外ともにウォークマンに統一する戦略へ転換することで、全世界的なヒット商品へと駆け上がりました。製品のコンセプトや販売戦略で、プロダクトアウトを採用した成功事例と言えます。
3.ポケモンGO
ポケモンGOとは、2016年にリリースされた位置情報アプリゲームです。GPS情報を活用して現実世界と仮想現実を融合させ、実際に歩きながらポケモンをゲットできるゲームです。
これまでのゲームは、家でしか行えないことで「健康に悪い」というイメージがありました。しかし、ポケモンGOは歩きながらゲームができるため、運動不足の解消にもつながると、多くの世代にヒットしたのです。
また、操作性が簡単でゲーム初心者でも楽しむことができる点や、地域限定のポケモンが全国各地に出現するイベントなどにより、これまでゲームに親しんで来なかった層からも人気を集めています。今までにない斬新なコンセプトがヒットした事例です。
9.マーケットインの成功事例
マーケットインは、消費者ニーズに対応した商品開発が特徴と言えます。これからご紹介する3つの事例は、消費者が一度は悩んだことのある悩みやこんなものが欲しかったと言えるサービスになっています。
いずれのサービスも各業界のトップランナーとして定着しているものですので、ぜひ参考にしてください。
1.ライザップ
ダイエットに挑戦して、挫折した経験がある人も多いのではないでしょうか。ライザップは、ダイエットを失敗した方のニーズを追求し「体を作る運動と食事」を徹底的に管理する戦略をとっています。
特筆すべき点は2つです。1つ目は、従来の有酸素運動は行わず無酸素運動により筋力量を増し、基礎代謝力を向上させて体重を落とすことです。
そして2つ目は、糖質制限した食事内容を毎日トレーナーに提出する食事管理です。以上を徹底することで、2ヶ月という短期間で結果にコミットすることを目指しています。
マーケットインの戦略は大きな反響を呼び、事業を開始して3年で売上100億円を突破、名実ともに「ダイエット=ライザップ」と言えるほどに成長しました。
2.USJ
USJ(ユニバーサルスタジオジャパン)は、ハリウッド映画の作品をもとにテーマパーク化したアミューズメントテーマパークです。オープン当初は、多くのお客さんを集めましたが、翌年以降は集客が伸び悩み、2004年には経営破綻状態となっていました。
そこで、USJのV字回復を導いた森岡毅氏が改革を行うために重視したのが「消費者視点」です。改革を行う中で、森岡氏は「来場者が喜ぶもの」と「提供者の視点で来場者が喜ぶと想定しているもの」が違うことに気づいたのです。
森岡氏は、その間違いが起こった原因が、クリエイティブ部が主導で企画や制作を行う仕組みにあると考え、主導権をマーケティング部へ移譲する形へと変更しました。
まず初めにマーケティング部による消費者ニーズの汲み取りや、プロジェクト内容の作成を行う流れにし、制作フェーズにもマーケティングが介入することで、消費者ニーズと制作側の意図に相違がないか確認する導線を作ったのです。
その結果打ち出されたのが、国内のアニメ作品とのコラボやハリーポッターエリアなどの導入です。この施策は見事に功を成し、2010年には750万人だった来場者数が、2015年には1400万人を達成するというV字回復を遂げています。
3.ロボット掃除機
消費者ニーズをうまくキャッチし、大ヒットしたのが「ロボット掃除機」です。その背景には、時代の移り変わりにより共働きの世帯が増え、掃除できる時間帯が限られている点にあります。
販売当初は評価が低く売れ行きが良くありませんでしたが、誰もいない時間帯に自動で掃除してくれる機能性が少しずつ評価され、2020年の掃除機市場のロボット掃除機のシェアは約14.2%にも成長しました。
価格が高く良いものだけが売れるのではなく、時間短縮を目的とした便利なものに焦点をあてたマーケットインの戦略がハマった成功事例と言えるでしょう。
10.プロダクトアウトの戦略策定にお困りなら、フリーコンサルタント.jpにお問い合わせください!
プロダクトアウトで新規事業を成功させるには、高度な専門知識と客観的な視点が必要です。しかし「専門家がいない」「プロジェクトを進める人手が足りない」などの課題を抱える企業様も多いのではないでしょうか。
そのような悩みの解決には、即戦力のプロ人材をご紹介する「フリーコンサルタント.jp」のご利用をご検討ください。
フリーコンサルタント.jpを活用するメリット
- 25,500名以上の登録者から最適な人材を選定してくれる
- 最短即日でのスピーディーなマッチングを実現できる
- 必要な期間と人数だけを契約が可能
国内最大級のデータベースには、新規事業の立ち上げや経営戦略に精通したハイクラスな人材が多数登録しています。貴社の技術やノウハウを客観的に評価し、市場に受け入れられるように伴走型の支援が可能です。
コンサルティング会社に依頼するほどの予算がない場合でも、必要な分だけスポットで依頼できるため、コストを抑えながら成果を追求できます。戦略策定や実行にお困りの際は、お気軽に「フリーコンサルタント.jp」にお問い合わせください。
11.まとめ
本記事では、プロダクトアウトとマーケットインの概要やメリット、デメリットについてご紹介しました。
どちらの戦略も市場環境や消費者のニーズを的確に把握できなければ、高い効果を期待することは難しいかもしれません。場合によっては、戦略をミックスして活用することも選択肢のひとつです。重要なことはどちらの戦略にするかではなく「消費者が望む価値提供ができるか」にかかっています。商品開発に関わる方は、自社に適した戦略を探してみて下さい。
もし、なかなか戦略が見つからない場合、外部のプロにアドバイスをもらうことも必要になります。
なお、みらいワークスは日本最大級のプロフェッショナル人材データベースを運営している企業です。外部人材の力が必要な企業様はお気軽にご相談くださいませ。
(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)