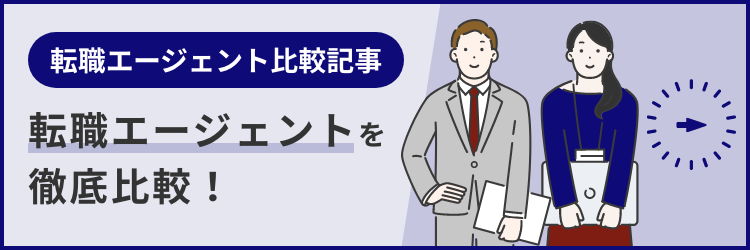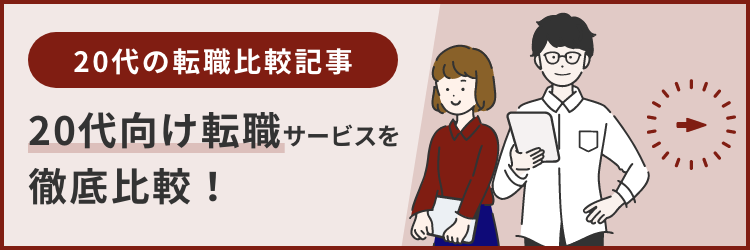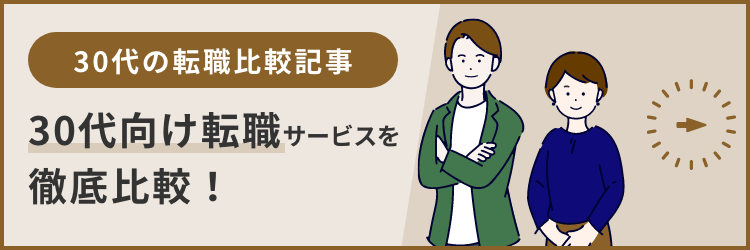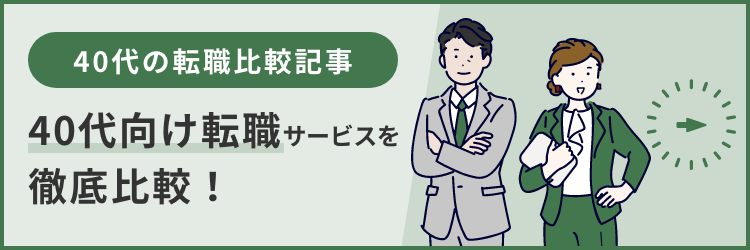「オフィス不要論」に答えが出た! 働き方が変わると働く場も変わる「みらいの仕事空間」の正解
2025.9.2 Interview
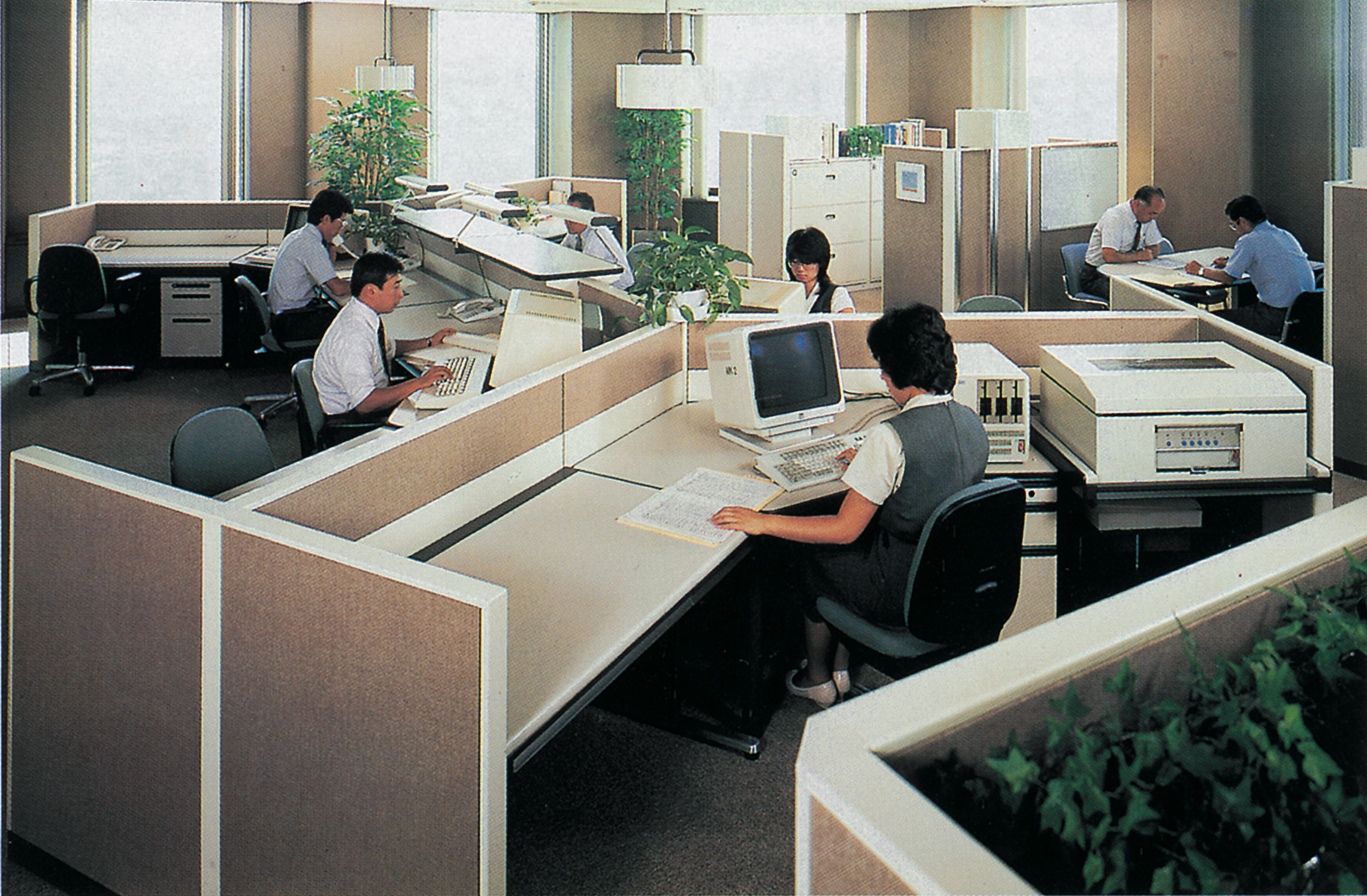
リモートワークが一気にひろがったコロナ禍において、「オフィスは本当に必要か?」といった問いかけが多くの人の頭に一度は浮かんだことでしょう。ですが2025年のいま、現場ではふたたび出社への回帰が起こっているようです。
「週5日以上のフル出社しているのは全体の約6割」という調査結果を示すのは、オフィス家具のリーディングカンパニー、オカムラの社内研究機関「ワークデザイン研究所」所長の森田舞さん。現在の働き方や働く場のトレンド、仕事空間はどのように変わっていくかーー展望してもらいました。
週5日以上のフル出社が6割

オカムラでは年に1度、企業の従業員3000人、経営層500人を対象に働き方やオフィスの実態、意識についてアンケート調査を実施している。直近2025年の調査結果を見ると、働き方やオフィスの意識に関する最新の傾向がわかる。
「現状、週5日以上のフル出社の人が約6割で、これは昨年も同程度でした。出社したい人、リモートワークがいい人、出社でもリモートワークでもいい人の割合は、興味深いことに3分の1ずつ。絶対にリモートワークがいい! という人ばかりでもないし、実際には、出社したい人、している人がこれだけ多いんですね。
オフィスの価値をどこに感じているのかという問いに、従業員は『オフィスでしかできない仕事ができる』と答えています。これは、オフィスにしか置いておけない書類やシステムがあるといった理由が考えられます。加えて、従業員も経営層も『コミュニケーションが取りやすい』ことを価値だと考えている人が多くいます。これらは納得の回答です。ただこの回答には、『離れていることへの不安がなくなる』『対面の方が安心してコミュニケーションできる』といった心理的な要素も加わっている気がします。オフィスに行くことで、同じ場所にいることによる一体感や帰属感、エンゲージメントが生み出されていることを、従業員自身が体感した可能性があります」(森田さん)
コミュニケーションの再定義
「仕事に集中しやすい」こともオフィスの価値として挙げられている。「コミュニケーションが取りやすい」ことと「仕事に集中しやすい」ことは、一見すると同時に成立しない気がするが、「これは個人的に思うことなんですが……」と前置きをしたうえで、森田さんは次のように話す。
「仕事に集中すると行っても、たとえば朝9時から夕方5時までの8時間ずっと机にかじりついて集中している人は少数だと思います。私自身、誰にも話しかけられず、ひとりで集中したいときには専用のブースに移るようにしています。ただ、今日はこのテーマについて考えたいと思ったとき、周囲にいる人に壁打ちのように考えをぶつけていると、頭が整理されていくということもありますよね。これは、コミュニケーションをとりながら仕事に集中している状態だと私は考えます。
コミュニケーションとひとことで言うと概念が大きすぎるので、「会話」と「対話」それぞれに考えて見るといいかもしれません。人と人との関係は、目的が明確でない日常的な雑談や情報交換などの会話ができるようになり、会話を繰り返すことで人となりを知って、次に相互理解を深めることを目的としたより深いレベルでの意見交換や価値観の共有といった対話ができるようになります。オフィスの価値は、数値化できるような効率化や生産性の向上といった単純な成果としてあらわすことが難しい。ただ雑談から、最終的には仕事への理解や相互理解が深まっていき、仕事の糧になっている部分もあるのだと感じます」(森田さん)
「集中」と「つながり」を両立する空間設計

オカムラでは働き方の調査だけでなく、オフィス空間のレイアウトに関する調査も行っている。レイアウト調査によると、自由に席を選べるフリーアドレスは近年のトレンドのひとつだ。ただ、働き方の調査での座席運用についてのアンケートでは、100名以上の規模のオフィスの約7割が依然として固定席を選んでいる。フリーアドレスは約2割、グループアドレスが約1割だ。CADのオペレーションや1カ所に集まっていたほうがいい経理など、職種によっては固定席のほうがいいこともある。固定席に安心感や居心地のよさを感じる人もいるし、固定席なら自分好みにカスタマイズできるメリットもある。一方で、チーム以外の人とコミュニケーションを取りづらいなどのデメリットを挙げる人もいる。
「調査結果を見ると、オフィス空間を見直すことで経営課題の改善を期待する経営層もいます。従業員の生産性の向上、働きがいの向上、採用率アップや離職率の低下など、各社それぞれの課題に対応するために、これまでの固定席だけのオフィスレイアウトではなく、固定席を設けず、業務内容に合わせてさまざまなワークスペースを選んで利用するABW(Activity Based Working)やフリーアドレスを取り入れる事例が広がっています」(森田さん)

集中にも種類がある。ひとりで没頭したいと思えば専用のブースや個室で仕事をしたり、誰かと対話しながらの思考をまとめたいと思えば、コミュニケーションがとりやすいオープンなミーティングエリアで仕事をする。人それぞれの好み、その日の体調も影響するだろう。太陽の日差しが感じられる明るいところ、間接照明のところ、空調の温度も個々人の感覚を大事にするのであれば、多様な場所をオフィスにつくる必要がある。「このように、個人の働き方の柔軟性に重点を置いたABWとあわせて注目されているのが、TBW(Team Based Working)です」と森田さんは説明する。TBWは、チーム単位での一体感や共同作業に重点を置いた働き方だ。たとえばデスク単位で予約できるエリアをつくり、プロジェクトの期間や、毎週定めた曜日にエリアを決めて集まって仕事をすることで密な連携を図る。
「人手不足の影響もあるのでしょうが、同時多発的なプロジェクトの進捗管理を行うなど仕事が複雑化している企業も多いようです。たとえば複数のプロジェクトに関わり、会議と企画と資料作成などを1日なかで並行して行うとき、固定席だけのオフィスが適しているのかどうか。状況や業務に応じて柔軟に働く場所を使い分けることができるような、オフィス空間の見直しによって、組織の生産性や効率性の向上を期待する経営層は増えつつあります」(森田さん)
「リフレッシュと共創」空間の価値
もうひとつ、近年注目されているのが「リフレッシュスペース」の存在だ。
「経営層も従業員も、オフィスにリフレッシュスペースを求める傾向にあります。いまや、働く=がむしゃらに机に向かうだけではない。休憩ができる場所があることで、従業員のウェルビーイングが向上し、それが生産性の向上につながるという考え方が浸透し始めている印象です」(森田さん)
また、バーカウンターやカフェスペース、社内イベント用のオープンエリアなど、かつてなかった空間が続々と導入され始めている。実際、みらいワークスの東京本社オフィス内にも、イベントスペースとバーカウンター「ルイーダ」(下画像)がある。

バーカウンターでは「社内の共創」が生まれ、イベントを開催したあとそのまま懇親会ができるオープンエリアでは「偶発的な出会い」が生まれている。
こういった空間は、企業の理念やビジョンを従業員と共有し浸透させ、共感を育みエンゲージメントやモチベーションを高めるインナーブランディングとなる。「会社のありたい姿を伝える空間設計ができているオフィスでは、就職活動中の学生に採用前にオフィスを見せることで採用活動への効果も期待できるでしょう」と森田さんはその価値を説明する。
オフィスは「不要」ではなく「進化」する

「働くうえで何を大切にするか」の価値観も変化している。
「今年の調査では、『働くうえで大切にしたいこと』のトップが健康でした。例年上位にくる報酬(給与)や成長をおさえ、心身の健康がもっとも重視されているという結果でした。WHO(世界保健機関)が定めたウェルビーイングの定義には、肉体的・精神的・社会的に満たされた状態とあります。従業員のこの価値観の変化は、健康経営や人的資本経営の一環としてオフィス空間設計をあらためて考えるタイミングがきたことを示しているように思います」(森田さん)
今後のオフィスは、さらに「人間らしさ」を大切にする空間になっていくとオカムラのワークデザイン研究所はみている。テクノロジーが進化する一方で、求められるのは「感覚」や「気持ちよさ」を尊重する設計だ。
「AIがいくら進化しても、感情や感性は人間の領域です。2030年以降は、人間性がより問われる時代になる。そう考えて、私たちは次の10年を見据えた研究を進めています。その日の気分や状態にあわせて、空調や光、音、香りなどが変わる未来のオフィス。平均的な環境ではなく、ひとりひとりの感覚に応じた場をどう設計するか。人に寄り添う空間設計が、これからのオフィスづくりの鍵になると考えています」(森田さん)
Ranking ランキング
-

「おカネをもらう=プロフェッショナル」と考える人が見落としている重要な視点
2024.6.17 Interview
-

さすがにもう変わらないと、日本はまずい。世界の高度技能者から見て日本は「アジアで最も働きたくない国」。
2018.4.25 Interview
-

評価は時間ではなくジョブ・ディスクリプション+インパクト。働き方改革を本気で実践する為に変えるべき事。
2018.4.23 Interview
-

時代は刻々と変化している。世の中の力が“個人”へ移りつつある今、昨日の正解が今日は不正解かもしれない。
2018.4.2 Interview
-

働き方改革の本質は、杓子定規の残業減ではなく、個人に合わせて雇用側も変化し選択できる社会になる事。
2018.3.30 Interview