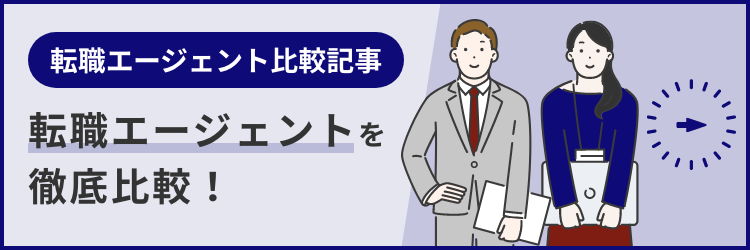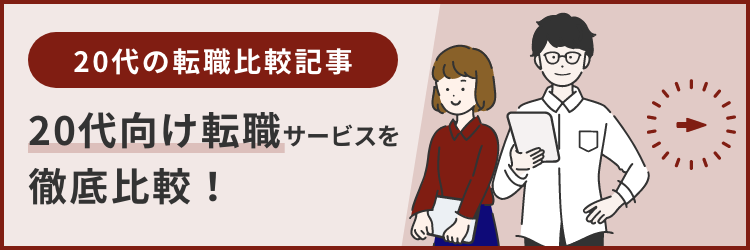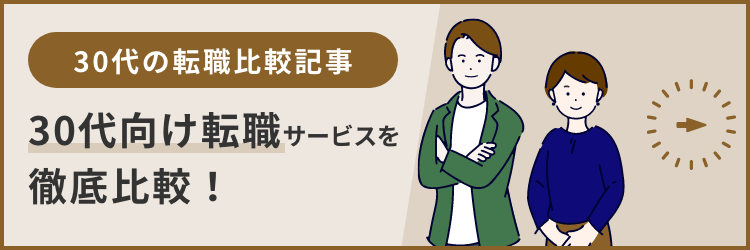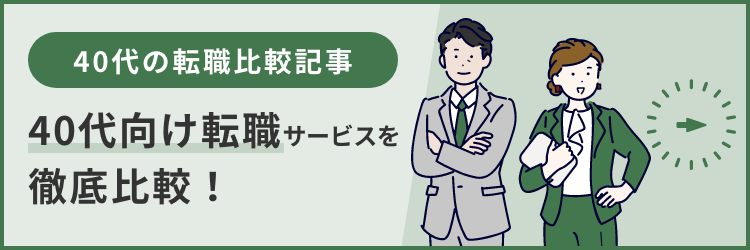「風を待つまち」気仙沼をセカンドキャリアの聖地にーーマーケティングのプロが考える地域の関係人口創出法
2025.10.7 Interview

宮城県気仙沼湾の最奥部にあたる内湾地区は、15世紀半ばから19世紀半ばにかけての帆船時代、港を出る帆船が船出に適した風を待っていたことから「風待ち地区」と呼ばれています。波の影響を受けにくい内湾は、かつて台風が来れば避難のために船がワッと押し寄せ、良い風が吹くその時まで錨をおろし、船人は岸に上がり、町の人々と交わっていました。待つことは停滞ではなく、次の航海に備えるための静かな助走ーー。「この地名の由来を聞いたとき、“セカンドキャリアの聖地”という言葉が浮かんできた」と、気仙沼ビジネスサポートセンター長の栗山麗子さんは話します。
大手食品メーカーで商品開発やマーケティングに携わったあと、神戸市の首都圏プロモーションに取り組み2024年に家族で気仙沼に移住した栗山さん。気仙沼で地域企業の伴走をしながら、地域活性化を軸としたプロジェクトを次々と生み出す栗山さんに、ご自身のキャリアについて、地域活性化に必要な視点、関係人口創出について話を聞きました。
セカンドキャリア「45歳の線引き」

「就職氷河期に大変な思いをして入社したので、転職とは無縁のキャリアを思い描いていた」と、栗山さんは話す。新卒で入社した大手食品メーカーで約20年、商品開発や営業企画、マーケティング、事業開発など幅広い業務に従事。データを活用したマーケティング部門は立ち上げから携わり、売れないとあきらめられていた素材に光を当て、国内市場形成のきっかけをつくるとともに、その素材を使った製品を国内最大級のテレビ通販番組に自ら企画出演し部門1位を獲得するヒット商材に押し上げたこともある。
「新規商材をヒットさせて次に何をやろうかと考えたときに、やりたいと思う新しい取り組み、キャリアアップの道筋が見えなかったんです。上からダメだと言われたらあきらめざるをえない環境を変えたいと思っても、40代半ばで今すぐ組織変革に関わるのは難しい。その時点では転職をする気はなかったけれど、まずは市場価値を測ってみようと転職エージェントに登録しました。そこで目にとまったのが、神戸市のエバンジェリスト募集でした」(栗山さん)
神戸市の施策やまちづくりの取り組みを広く伝え、共感や理解を広げる役割を担うエバンジェリスト2人の募集には800人弱の応募があったという。栗山さんは採用が決まって初めて、このまま働き続ける未来、この先のキャリアについて考えた。
「仕事が好きで、生涯現場で自分の能力が活かせるやりがいのある仕事をしたい。経営層を目指すのか、現場中心で50歳で役職定年を迎えるのか……。当時の私には、そのまま会社に残った先の姿を描くことができませんでした。転職するのであれば、50歳では時間が足りない。45歳までに新しいことを始めたい。神戸市の仕事は3年という期限付きだったので、それをリスクだとアドバイスをくれる方もいましたが、縁とタイミングに背中を押されました」(栗山さん)
「もともとは冒険するタイプではない」という栗山さんに、“良い風”が吹いた瞬間だった。
不安で挑戦できないなら、ものごとの二面性を見る
2019年に転職を決め、2020年に神戸市職員となった。まさに、コロナ禍突入のタイミングだった。「転職しなければよかったと思ったことはありませんでしたか?」と聞くと、「世の中の事象には、つねに二面性があります。キャリアのことだけでなく人生のなかで、しなければよかったと思ったことはないんですよね」と栗山さんほほえむ。
本来であれば、神戸市と東京都の拠点を行き来しながらプロジェクトを進めていく予定だったが、遠距離の移動が制限され、思うように神戸市に行くことができない期間があった。一方で、オンラインミーティングが標準化されたおかげで、距離の制約はむしろ減ったといえる。
「神戸市役所の人より市内の事業者に詳しいと言われるほど、東京にいながら現場とつながることができました。悪いできごとと思うようなことも、視点を変えると良かったなと思える。よく、戻れるとしたら何歳に遡って生き直してみたいですか? といった問いかけがありますよね。私は、どの時点にも戻りたいとは思いません。思い残すのがいやなので、今に全力を尽くす。つねにいい側面に光を当てるのが、私の思考のクセです」(栗山さん)
神戸市も気仙沼市の人々も「同じような思考のクセがありそうだ」と栗山さんは感じています。どちらの都市も震災を経て、これまでの歴史は大切にしながらも今を見て、未来に向けていい方向を探ってきた。「外から来た人を排除しがちな地域もありますが、神戸市も気仙沼市も外の人を受け止め、協働して未来を作る力があるように感じています。これが、復活力につながっているのではないでしょうか」(栗山さん)
神戸市で学んだ「三方よし」の副業・兼業モデル
神戸市では、本格的な副業・兼業人材活用を推進した。デジタル、マーケティング、プロジェクトマネージャーといった地域の企業に不足している人材の補填、関係人口の獲得、人材側のやりがいと新しい居場所の発見という、企業と自治体と人材「三方よし」の副業・兼業モデル。これは、「外部人材がタスクをこなすだけでなく、地域の企業で働く人々の行動様式も変えた」と栗山さんは振り返る。
たとえば、ある老舗コーヒー企業では不足しているデジタルスキルを補うため、副業人材に入ってもらった。EC改善を担当した副業人材の成果は売り上げ拡大だけでは終わらなかった。副業人材と社内のEC改善チームのやりとりを通じてPDCAの回し方が定着し、他部署へ横展開された。結果、社内の意思決定と検証の速度が上がった。
また、あるテクノロジー企業では高いPRスキルを持った兼業人材が加わり、若い女性中心のチームを発足させた。PR戦略の立案から繰り返しのミーティングによる柔軟な方向転換から運用、検証まで「できる」自信がチーム内に醸成されたという。
さまざまな企業での副業・兼業人材活用をみてきて、「うまくいくには3つのことが必要」だと栗山さんは感じている。1つは、格好つけないこと。わかったフリをせず「助けてください」と言える企業のほうが信頼関係の立ち上がりが早い。もう1つが、目標設定を「動的」にすることだ。地域の企業と副業・兼業人材のやりとりは、オンライン中心になることが多い。その場合、ズレの調整がうまくいくための肝となる。やってみてズレていたら、その場で目標を柔軟に更新していく。最後の1つは、初動を間違えないこと。企業側が「やらなければならない」と思っていることでも、そもそもの課題の設定が間違っていたらやっても意味がない。課題と依頼内容の設計次第でうまくいくかいかないかが決まるケースがあるのだ。これら3つを意識するだけで、副業・兼業人材を活用した際の進捗の質が変わる。
「副業や兼業で働く外部人材は、特効薬と考えず触媒だと考えたほうがいいと感じます。外部人材が入ることで、社内で化学反応が起きて広がっていく。だからこそ、外部人材の役割やKPIは多角的に見ることが必要です。外部人材側も、報酬をおカネの多寡のみで考えないほうがうまくいく。成果、学び、仲間、居場所……など、さまざまな視点でとらえると、関係は自然と長くなっていくようです」(栗山さん)
地方の「余白」をおすそわけする

栗山さんが気仙沼市で今、力を入れていることの1つが「セカンドキャリアの聖地化」だ。
「気仙沼市に来て風待ち地区の地名の由来を聞いたとき、セカンドキャリアに興味がある人にPRするのにぴったりの地名だなと思いました。人生には、二度三度と風を待ち、また漕ぎ出すタイミングがあります。都市部の働き方はスピード感が大事で、今すぐやらなければと考えがちですが、風待ちという言葉には、そういった焦りを鎮める効果があると思うんです。キャリアの舵取りは、前のめりに進むより、待ちの時間が重要になる。自然の呼吸に歩調を合わせる風待ちの感覚を、セカンドキャリアの象徴として私は受け止めています」(栗山さん)
セカンドキャリアの聖地化を進めるうえで、栗山さんが大事にしている価値観がある。それは、「都市が地方を助ける」ではなく、「都市と地方で交換する」という発想だ。地方は、人材は不足しているが自然、ゆるやかな時間、1次産業から6次産業まで多様な仕事との接点がある。加えて、「都市が過密になるほど、地方の余白は資源化する」と栗山さんは考える。
「地方には、場所、時間、役割の余白があります。いつも予約で取りづらい会議室、混雑した電車での移動、分刻みのミーティングがない状態は、地方の多くの人にとっては当たり前でも、都市部の人にとっては貴重です。地方はそれらの余白をおすそわけして、都市部は人材や情報、販路、設計力を提供する。たとえば都市部の企業で働く人であれば、自身の職能を小さく試す場として地域を活用する。気仙沼市で何かできることはないでしょうかと聞いてくれた大学生の方々には、調査や卒業論文のフィールドとして気仙沼市を使ってほしいと伝えました。副業も兼業も移住も、その地域と自分にとっての価値が重なる接点を見つけることが大切です。お互いに得があるから、関係が長続きするんですよね」(栗山さん)
小さな成功体験が地域の力を押し上げる

栗山さんは、気仙沼ビジネスサポートセンター長に就任して2025年9月で1年を迎えた。センター長として1年間で対応したビジネス相談件数は850件超、来訪者数は1300人弱となった。コロナが明けても客足が戻らないと話す飲食店は、クリスマス時期のオードブルのテイクアウトで販売数量を前年の200%以上に伸ばした。気仙沼市にかつお漁が伝来して350周年という節目の今年、市内の飲食店では記念メニューの提供や冊子の制作や配布、テレビ放映などで客数が前年比150%となった店舗もあった。
釘や接着剤を使わずに幾何学模様を生み出す伝統的な木工技術「組子細工」の承継が課題の企業では、ギフトやインテリアとして商品化し、国内外へ販売する新規プロジェクトをスタート。集客動線の設計や価格の再定義、販路の切り替えや新規事業創出など、多岐にわたる取り組みで課題解決につなげている。地元の「できる」を抽出し、都市部の「売れる」と接続するのが仕事。「小さな成功体験の積み重ねが、地域の力を押し上げる」と栗山さんは話す。
「市内企業が望む人材獲得につなげるため、セカンドキャリアの入口としての現地フィールドツアーの実施も進めています。ここで重要なのが、自然や海の幸を楽しむだけに終わらせないこと。今現在の気仙沼の姿を知っていただきながら地元企業と出会い、課題を知っていただき、その後も関係性を持っていただく。ツアーに参加した方のなかには、その場で地元企業のプロボノやりますと手を挙げてくださった方々もいらっしゃいます」(栗山さん)
「仕事でやりたいことがない」「仕事で楽しいことはない」と考える人も、余白がある地域でなら、おもしろいとスキルを結び直すことができるかもしれない。人生の多くを費やす営みが苦痛の代償でしかないのは、あまりにももったいない。まずは小さく関わり、できることが増えていけば仲間も自然と増える。この循環が、地域活性化、関係人口創出につながっていく。
Ranking ランキング
-

「おカネをもらう=プロフェッショナル」と考える人が見落としている重要な視点
2024.6.17 Interview
-

さすがにもう変わらないと、日本はまずい。世界の高度技能者から見て日本は「アジアで最も働きたくない国」。
2018.4.25 Interview
-

評価は時間ではなくジョブ・ディスクリプション+インパクト。働き方改革を本気で実践する為に変えるべき事。
2018.4.23 Interview
-

時代は刻々と変化している。世の中の力が“個人”へ移りつつある今、昨日の正解が今日は不正解かもしれない。
2018.4.2 Interview
-

働き方改革の本質は、杓子定規の残業減ではなく、個人に合わせて雇用側も変化し選択できる社会になる事。
2018.3.30 Interview