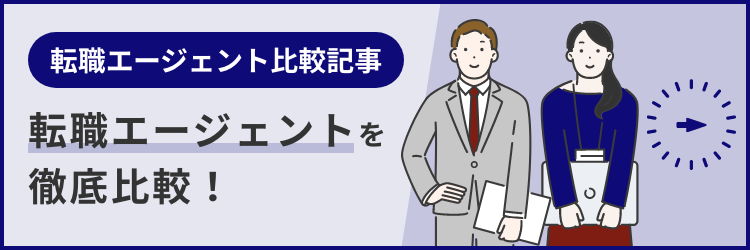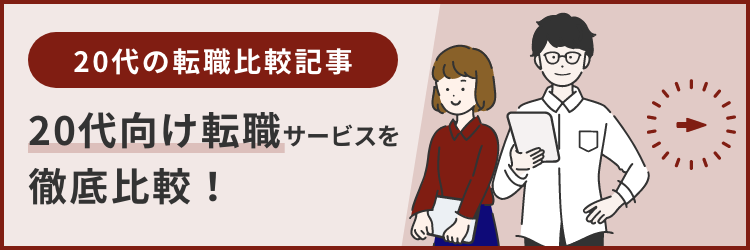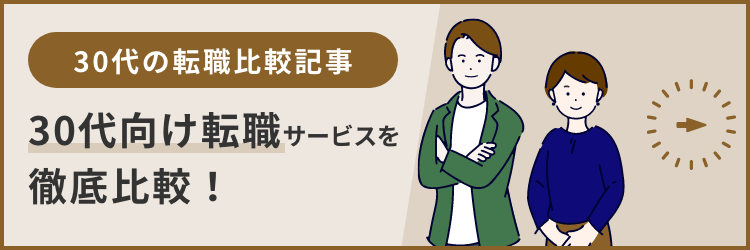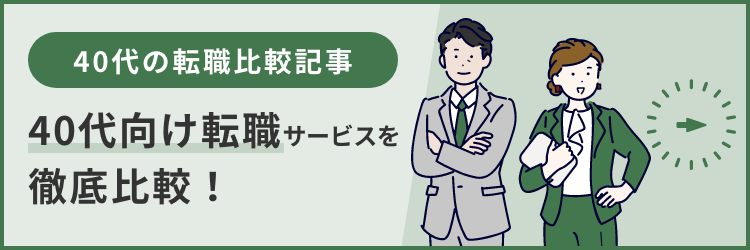「ワークライフバランスなんてない。あるのは、ライフだけ」——『弁当箱思考』で描く、自分らしい人生設計
2025.7.14 Interview
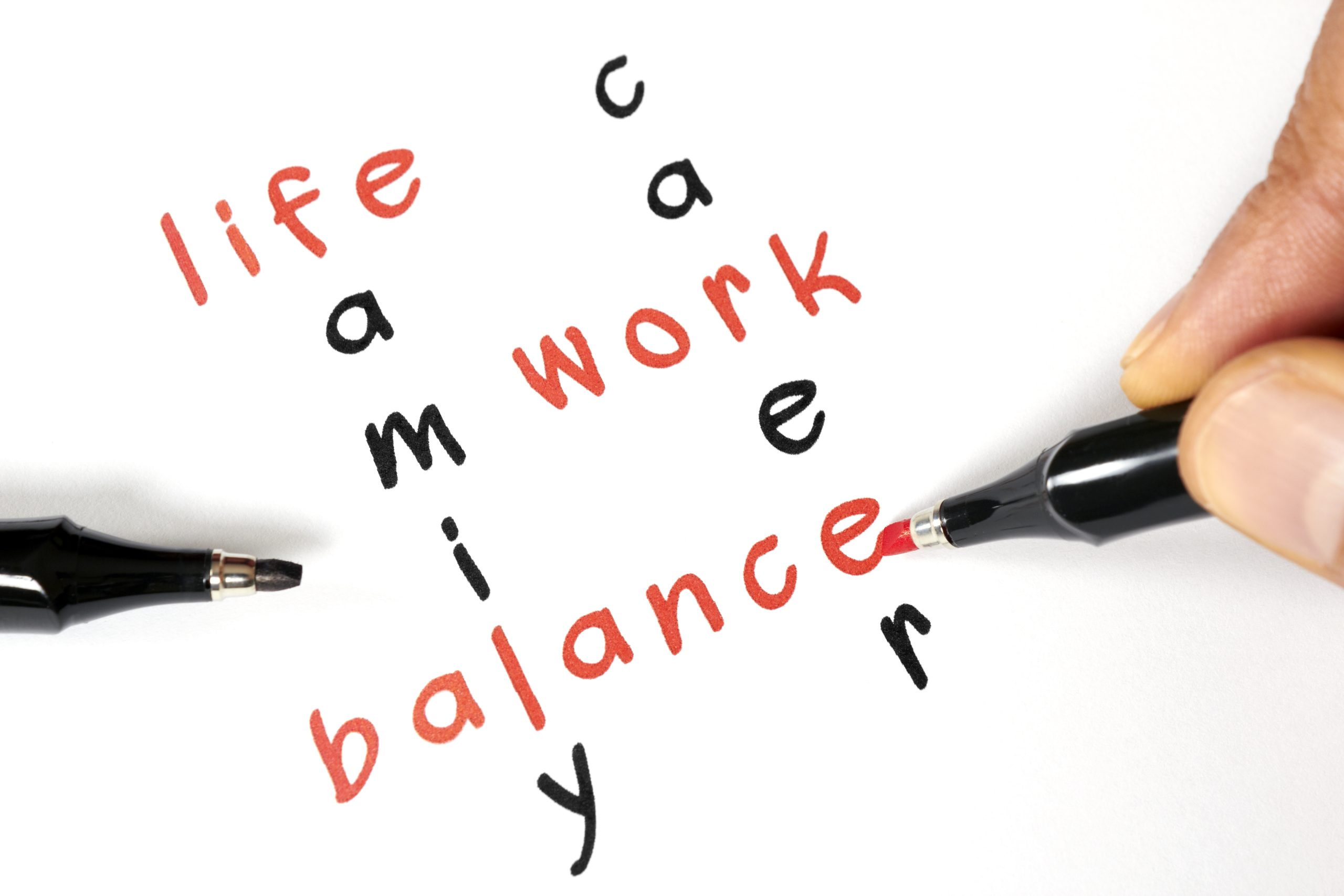
「副業に興味はあるけれど、今の仕事が忙しくて……」「会社の業務を離れたら、自分にできることが何かわからない」ーー。そんな迷いや不安を抱える会社員に向けて、自分らしい働き方と暮らし方のヒントを示すのが、『弁当箱思考 働き方も暮らし方も、自由に盛り替えるライフデザイン術』の著者、石森宏茂さんだ。
石森さんが提唱する「弁当箱思考」とは、自分の人生をひとつの弁当箱に見立てて、主食(本業)や主菜(副業・投資・ボランティア・プロボノ)、副菜(趣味・健康・学び)を自由に詰め合わせるというライフデザイン術。1社専属・1職種専業の“日の丸弁当”から脱却し、複数の収入源と関心領域を持つ「ポートフォリオ型」の人生を目指すものだ。石森さんへのインタビューを通して、「何を幸せと思うのか」あらためて自分自身に問いかけてみよう。
自分のモノサシで人生を考える
石森さんが自分の働き方や暮らし方を見直したのは、新卒で入社したベネッセコーポレーションでの会社員11年目の冬。胃潰瘍寸前で救急車で運ばれたのが転機だった。「ずっと張り詰めていた糸がプツンと切れて限界だと悟った」と石森さんは振り返る。背景には、営業を経て経営企画部門で忙しく働きづめの毎日から一転、コロナ禍でリモートワークとなり、電車での行き帰りの時間が余白として生まれたことがある。常々不安に感じていた、自分の将来が「宙ぶらりん」のような感覚。このままでいいのか、このまま何十年もやっていけるのか、だからといって外の世界では通用しないのではないか……。自問自答しながら、答えを出すのを先延ばしした結果、石森さんは体調不良によって“強制退場”することになった。
「私のように突然の強制退場になる前に、早めに自分のモノサシで自分の人生を考えることは将来のリスクを減らします。どこまで稼ぎたいのか、それはなぜなのか、何を幸せと思うのかを問い続けるような時間はない、そのうち考えようと思っている方も多いでしょう。私もそうでした。実際にスキルも肩書きも失ってから、その大変さに気づくケースが多いんですよね。暮らしのコストを意識しないまま、もっと稼ぐ、たくさん稼ぐことが幸福といったことだけを幸せのモノサシにしてしまうと、限られた時間や体力が過剰に消耗されて、本来の幸せから遠ざかるリスクもある。人のモノサシで生きるのをやめ、新たな可能性を拓くための考え方として私が提案するのが、弁当箱思考です」(石森さん)
自分にとって必要な出費を考える「弁当箱思考」
「弁当箱思考」とは、人生をひとつの弁当箱に見立て、そのなかに自分が求める暮らし方、生き方、働き方、学び、趣味などをバランスよく詰め合わせ、自分にとって「ちょうど良い人生」にバランスしていく思考法だ。弁当箱の大きさ(=暮らしのコスト)をどのくらいに設定し、主食(本業)や主菜(副業・投資・ボランティア・プロボノ)、そして副菜(趣味・健康・学び)をどのくらいで盛り込むかを可視化。自分が満足できるラインがわかれば、余計な出費や働きすぎを防ぎ、本当に大切だと思える活動へ、時間や意識を回せる。

このとき大事なのは、1度決めた弁当箱の構成(=ライフデザイン)に縛られることなく、最低でも年に1度、あるいは数カ月ごとに見直す柔軟性だ。「自分の手で定期的につめなおせる自由は、安心につながる」と石森さんは説明する。
「会社の文句をいいながら働いている人がたくさんいます。ですが、限られた人生のなかで不平不満を言う時間、がまんする時間は短いほうがいいと思いませんか。時間は命そのものだと思うと、命を削って嫌なことをしている人はどれだけ自虐的なんだ、と(笑)もちろん、がまんが必要なときもありますが、本当にそこに縛られていないといけないのか立ち止まって考えることが大切です」(石森さん)
働き方の危険信号に気づくためのセルフチェック
弁当箱思考の構成要素ごとの考え方や運用方法の説明は石森さんの著書に譲ることにして、ここではまず、「漠然とした不安」や「もし⚪︎⚪︎になったらどうしよう」という懸念を整理するためのセルフチェックリストを伝えたい。現状、自身のお弁当箱にどのような偏りがあるか、ないか、どういったリスクを抱えやすいか、心当たりを探りながら以下の10項目のチェックリストにYesかNoで答えてみよう。
【10項目のチェックリスト】
1.会社や組織にさえしっかり属していれば、将来も安泰だろうと思う【塩おにぎり症】
2.手軽に早く稼げるノウハウを見ると、つい飛びつきがち【インスタント食品味覚症】
3.かつて身につけたスキルや資格を、そのまま更新せず使い続けている【冷めきったおかず症】
4.土日や夜間まで仕事漬けで、自分をほとんど休ませていない【味覚過敏症弁当箱症】
5.コミュニケーションが社内・家族内だけに留まり、社外との交流が少ない【味オンチ孤食症】
6.定年退職後や老後に向けた具体的プランは、まだ先と先延ばしにしている【隠し味忘れ症】
7.1つのスキルや資格を武器にし、それだけで十分だと考えている【単一調味料依存症】
8.過去の成功体験に固執して、「今後も同じやり方で通用する」と思っている【保存食中毒】
9.勉強や副業など複数を同時並行し、いつも時間に追われている【詰め込みすぎ盛り弁当症】
10.興味があるものを手当たり次第に始めるが、目的やゴールが曖昧になる【盛り付けバラバラ症】
「Yesがたくさんあるから重症、リスクが大きいというわけではありません。ここでは、自分はどの症状に陥りがちかがポイントです。チェックを通して、自分の傾向や思考のクセを客観的にとらえることができれば、これからのライフデザインのヒントが自然と見えてきます。
かつて私は、塩おにぎり症でした。手にしていた会社という“握り飯”を離すことがこわくて、しがみつくように働いていた。でも身体は正直で、ある日突然もうムリだという状況になりました。塩おにぎり症の特徴は、会社に過度に依存していること、想定されるリスクはリストラや部署異動で大打撃を受けたり、社外人脈がゼロなこと、対策としては社外コミュニティーを持つ、副業の小さな体験をスタートさせる……というようにとらえることができます。
自分に当てはまる症状が何を意味するのか、輪郭を事前に把握しておくことで想定外が減れば、新しいことを始めるときにも必要以上にビクビクせずにすみますよね」(石森さん)
「主食=本業」を補完する「主菜=副業」
終身雇用制度が見直されている今になっても、新卒就職後に企業の社員として数十年勤め上げるスタイルは根強い。「雇用されて働く以外の働き方は、特別な人がするものだ」「1つの企業で営業しか経験がないのに自由度の高いライフデザインなどできるはずがない」と考える人も多いだろう。この漠然とした不安を払拭するためにも、複業・副業によるスモールステップで感触をつかむことを石森さんは推奨する。

「週末だけ副業で仕事を受注してみる、月1回だけボランティアやプロボノに参加してみる、社内副業や部署横断プロジェクトで新しい働き方を体験してみる……。こういった小さな行動を続けると、自分のスキルは意外とほかの市場で通用するな、ストレスになるから本業に専念したほうがいいなといった気づきを得られるでしょう。活躍できる場所、行き先が複数あることに気づけると、不思議と不安はやわらぎます。
副業の経験によって、たとえば営業しかできないと考える人が営業ほど強い能力はないと考えをあらためるかもしれません。実際、営業やマーケティングはどこにいっても重宝される職種です。実際やっている本人からすれば、顧客と適切なコミュニケーションをとり、困りごとを見つけて、必要な提案をするだけだと思われる人もいるかもしれませんが、営業をやったことがない人からすると、どうやって困りごとを引き出していくのかわからないからです。
私はベネッセコーポレーションで営業を経験したあと、ベンチャー企業でSaaS型クラウドサービスを企業に提案、販売する営業職に転職しました。ベネッセでもその転職先企業でも商品を売ったら終わり、ではありません。ベネッセの模擬試験は去年のデータをもとに今年はこうするといいといった提案をしますし、SaaS営業はサブスクリプションモデルのため顧客のニーズに合わせた提案によって長期的な関係構築が求められます。どちらもカスタマーサクセスという共通点がありました。ここに気づけると、営業ができます、ではなくカスタマーサクセスに強いという売り込みができるんですね。経営企画部門しか経験がないといった人の場合、M&A、投資、財務のどの事業領域に強いのかを把握したうえで、本業では財務担当だから副業ではM&Aに挑戦してみようといった考え方もできます。使える武器を増やすには、営業や経営企画というひとつの職種の中でも専門性の幅を広げる視点が大事です」(石森さん)
理想のライフを実現するためのワーク
昨年夏から夫婦でマレーシアに住む石森さんだが、3年後にはポルトガル移住を計画中だ。ポルトガルと日本の時差は8時間。そのため、現在の新規事業開発に関わるコンサルタント業や副業・複業の情報提供といった仕事ではなく、世界を舞台にした小売りや卸業へのシフトも考えている。
「ワークライフバランスなんて存在しないと私は考えます。ライフしかないんです。人生をどう生きたいか。そのうえで、理想のライフを実現するための、あくまでもひとつの手段がワークでしかない。だからこそ、働き方はもっと柔軟であっていいと思うんです。副業も、転職も、起業も、すべては自分のライフに合わせた選択でいい。ライフファーストの考え方で、ポルトガルでは、日本時間にしばられない自分たちのリズムに合う働き方を模索したいですね」(石森さん)
仕事をベースに生き方を変えるのではなく、生き方に合わせて仕事を変える。この柔軟性こそが、今を生き抜くための最大の武器になる。

『弁当箱思考 働き方も暮らし方も、自由に盛り替えるライフデザイン術』(セルバ出版)
「会社に縛られずに働きたい」「副業を始めてみたいけど、一歩が踏み出せない」——そんな悩みに寄り添いながら、自分らしい人生設計のヒントを与えてくれる一冊。著者のリアルな体験と、収入源や働き方を多層的に組み立てる「弁当箱思考」の実践法を通じて、現代を生きるすべてのビジネスパーソンに向けて、キャリアと人生のリスクを“自分ごと”として考える視点を提供してくれる
Ranking ランキング
-

「おカネをもらう=プロフェッショナル」と考える人が見落としている重要な視点
2024.6.17 Interview
-

さすがにもう変わらないと、日本はまずい。世界の高度技能者から見て日本は「アジアで最も働きたくない国」。
2018.4.25 Interview
-

評価は時間ではなくジョブ・ディスクリプション+インパクト。働き方改革を本気で実践する為に変えるべき事。
2018.4.23 Interview
-

時代は刻々と変化している。世の中の力が“個人”へ移りつつある今、昨日の正解が今日は不正解かもしれない。
2018.4.2 Interview
-

働き方改革の本質は、杓子定規の残業減ではなく、個人に合わせて雇用側も変化し選択できる社会になる事。
2018.3.30 Interview