「SDGs」は、2015年に国連で採択された持続可能な社会のための目標です。一方、「ESG」は環境・社会・ガバナンスに配慮した経営を行うことです。どちらもより良い社会を実現するための取り組みであり、互いに深く関わっています。
また、SDGsやESGへの取り組みは、企業価値の向上や投資家へのアピールにもなります。ただし、現在の事業内容などを考慮しながら取り入れることが重要です。
本記事では、SDGsとESGの違いや関係性を説明しつつ、企業が取り組む際のポイントや導入事例を紹介します。
SDGsとESGとは?
「持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals」を意味する「SDGs」と、「環境・社会・ガバナンス」を意味する「ESG」は、どちらも世界をより良くするための行動指針です。
それぞれの言葉の由来や違いについて説明します。
SDGsは「持続可能な開発目標」
SDGsは、2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際的な目標です。「持続可能な開発目標」を意味する「Sustainable Development Goals」の頭文字から、SDGsと呼ばれています。
SDGsは、2000年に行われた国連ミレニアム・サミットでの宣言をまとめたMDGs(Millennium Development Goals:ミレニアム開発目標)の後継にあたります。MDGsでは、2015年を期限として、極度の貧困や飢餓の撲滅、HIVやエイズのまん延防止などについて8つの目標が掲げられていました。
SDGsでは「誰一人取り残さない」を原則とし、持続可能な社会の実現のため、2030年を期限とする社会・経済・環境に関する17の国際目標を定めています。
ESGは「環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)」
ESGは、「環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)」の頭文字を取った言葉で、これらの要素を考慮した企業経営を行う考え方のことです。
アメリカではESGをめぐる議論のなかで、「Transition(移行)」という表現が用いられるケースも増えています。
近年、企業が長期的に成長し続けるためには、利益だけでなく、環境や社会への貢献、そして透明性の高い経営が重要であるという認識が広まりつつあります。
具体的には、「環境(Environment)」では温室効果ガスの排出量削減や廃棄物削減、「社会(Social)」では多様性の尊重や安全な職場環境づくり、「ガバナンス(Governance)」ではコンプライアンスの順守や財務情報の公開などが当てはまります。
SDGsとESGの違いは「対象」
SDGsとESGの大きな違いは、「対象」となる範囲です。
まず、SDGsは、持続可能な社会を実現するための国際的な目標であり、「すべての国と地域」が対象です。国連や国・地域が働きかけることで、自治体や企業、消費者に行動を促します。
一方、ESGは持続可能な企業の成長を目指しており、主な対象は「企業」になります。
なお、環境や社会への配慮はSDGsとESGの両方に共通していますが、ガバナンスへの配慮はESG特有の特徴といえるでしょう。

SDGsとESGの関係性
政府や国際機関の取り組みにより、SDGsを経営に取り入れる企業が増えています。SDGsとESGには共通点が多く、企業がESGに配慮して経営を行うことで、結果的にSDGsへの取り組みにつながる場合もあります。
このような理由から、企業はSDGsとESGの両面から経営を進めるケースが多い傾向です。
また、企業のSDGsへの取り組みを評価する際に、投資家はESGスコアを参考にする場合もあります。ESGスコアとは、企業の業績を環境・社会・ガバナンスの三方面から評価する際に使用される指標です。
国内外の企業が注目するESG投資・ESG経営
ESGという言葉よりも、「ESG投資」や「ESG経営」という表現を耳にすることのほうが多いかもしれません。
そもそもESGは、投資活動から始まった考え方です。これまで投資家が企業を選ぶ際には、主に評価基準として財務情報が使用されてきました。しかし、2006年に国連が投資家に対し、投資プロセスにESGを組み入れるよう推進する「責任投資原則」(PRI)を提唱しました。これにより国内外でESG投資が注目されるようになったのです。
一方、ESG経営とは、環境・社会・ガバナンスに考慮した経営手法です。ESG投資は投資家目線での取り組みですが、ESG経営は企業主体であり、投資家のみならずクライアントや消費者などからの企業イメージの向上にもつながります。
参考:【基本から解説】ESG経営とは?|メリットやデメリット、事例、企業価値を高めるポイントも紹介!
企業がSDGsやESGに取り組むメリット
企業がSDGsやESGに取り組むことには、さまざまなメリットがあります。ここでは、企業がこれらの活動に力を入れることで得られる利点について解説します。
企業イメージの向上
企業がSDGsやESGに取り組むことは、企業イメージの向上につながります。
近年、環境問題や社会問題の認知とともに、投資家や消費者は社会課題に取り組む企業を高く評価するようになってきました。そのため、SDGsやESGへの取り組みは、社会課題に関心のある人々へのアピールとなり、競合他社との差別化にも有効です。
また、社会や環境に配慮する活動を行うことで、社員は社会的責任を果たす組織のメンバーであることを実感できます。その結果、仕事のモチベーションアップや優秀な人材の流出防止にもつながります。
ESG投資による資金調達の可能性
ESG投資を活用することで、企業は資金調達を有利に進められる可能性があります。
「責任投資原則」(PRI)に署名する機関は、2006年の提唱以降、年々増加傾向です。2025年7月時点では、世界で5,100以上の機関が署名しており、日本でも145の機関が署名しています。今後さらに、投資家によるESG投資は増えていくでしょう。
ESG投資によって長期的な資金調達が可能になれば、新事業の展開やビジネスの拡大も可能になります。
参考:SDGsを事業に取り入れるべき理由とは? 導入のメリットや導入方法などを解説

企業がSDGsやESGに取り組む時のポイント
企業が持続的に成長していくためには、SDGsやESGへの取り組みが欠かせません。ここではこれらを実践する際に意識したいポイントを紹介します。
基礎知識や世界情勢、規制を把握する
そもそもSDGsやESGがどういうものなのかを理解していなければ、自社の方針や事業にブレが生じる可能性があります。そのため、SDGsの目標や理想、現状をしっかり把握しましょう。その上で、自社が取り組む内容を決めていきます。
取り組む内容を決める際は、ESGよりもSDGsの目標から考えるとイメージしやすくなります。
また、具体的な取り組み方法は、他社や他国の取り組み事例を参考にしつつ、自社では何にどのように取り組むのかを検討するとよいでしょう。
ステークホルダーに十分な説明を行う
SDGsやESGを事業に組み込むなら、ステークホルダー(利害関係者)の理解は欠かせません。なぜ自社がこの取り組みを行うのか、その背景や理由を、具体的な計画や数値目標とともに説明することが大切です。
また、従業員からの理解や協力は非常に重要です。そのためには、説明会や学習ツールなどを活用し、社会問題への認識を深めてもらいましょう。学習ツールには、経済産業省が提供する「SDGs経営ガイド」や環境省の「SDGs活用ガイド」などがあります。
「SDGsウォッシュ」に注意する
企業がSDGsへの取り組みを紹介する際は「SDGsウォッシュ」にならないよう注意しましょう。
SDGsウォッシュとは、企業がSDGsに取り組んでいるように見せかけているものの、実際には十分な活動が行われていない状態です。また、実態がともなっていないだけでなく、成果を誇張したり、事業内容やSDGsの目標に矛盾したりしている場合も、SDGsウォッシュとみなされる場合があります。
SDGsウォッシュが起こると、投資家や顧客からの信頼の損失や企業のイメージダウンなど、さまざまなリスクが生じます。こうした事態を防ぐためには、検証に基づく具体的な数値や達成度など、取り組みの進捗を定期的に公表しましょう。
参考:【プロフェッショナルインタビュー】ESG戦略を実現するための成功ポイントとは?ESG戦略の課題や推進に必要な要素も紹介
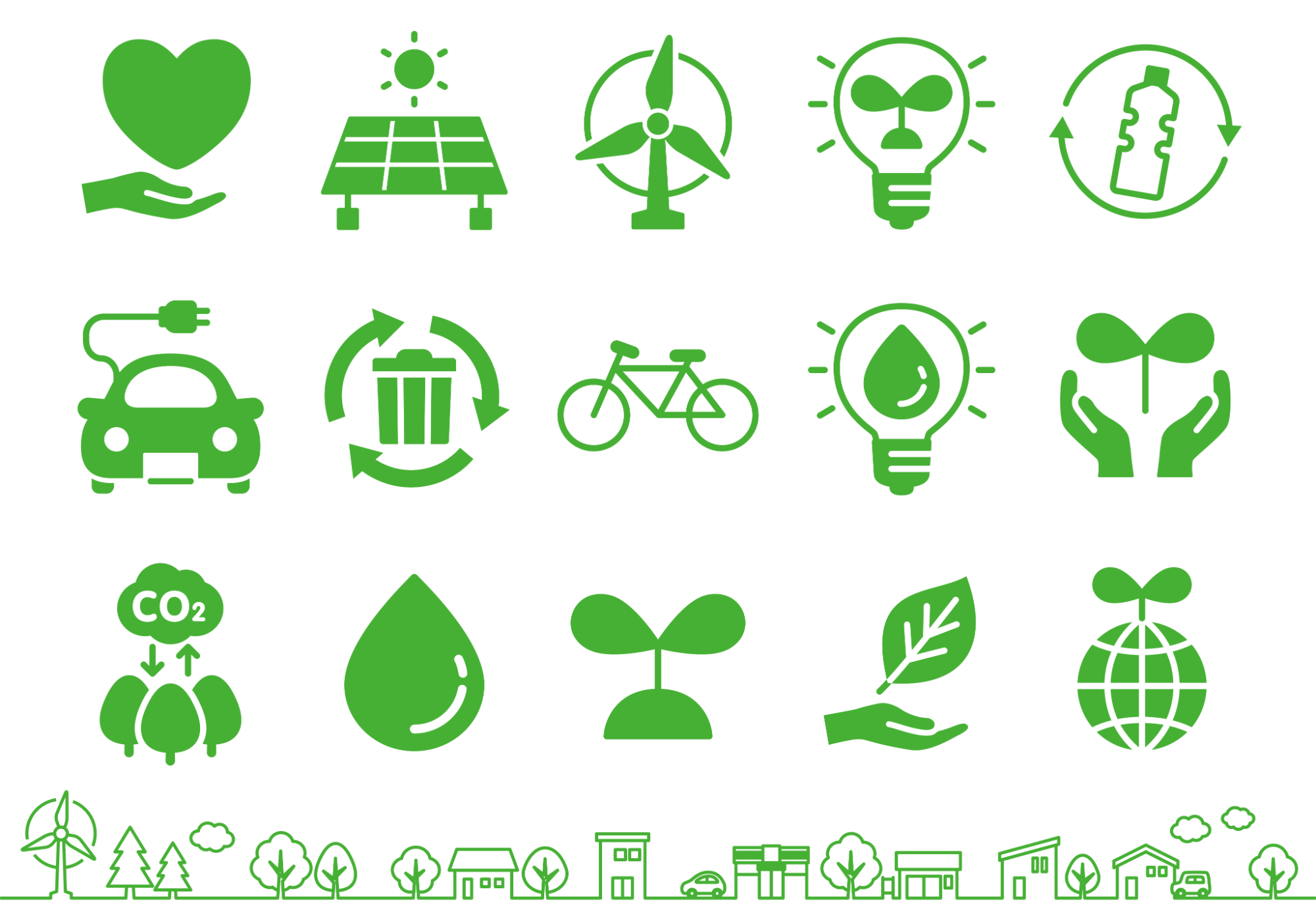
SDGsやESGへの企業の取り組み事例
最後に、SDGsやESGに対して、企業がどのように取り組んでいるかの事例を紹介します。
- 花王株式会社
- 日本マクドナルド株式会社
- イオン株式会社
花王株式会社
花王株式会社が推進する「Kirei Lifestyle Plan」は、19の具体的なアクションプランをまとめたESG戦略です。これらのアクションプランは「環境への配慮」「人々の健康」「社会的責任」の3つのカテゴリから構成されています。
また、花王株式会社では、衛生習慣化プログラム「みんなで手あらい」を実施。衛生状態の維持の習慣化を目的とし、小学校低学年や、ろう学校、盲学校、養護学校などに学習教材を提供しています。
環境分野では、2040年までにカーボンゼロ、2050年にはカーボンネガティブを達成する計画です。具体的には、製品のコンパクト化やつめかえ商品の拡充、容器の再生可能原料への変更などの取り組みを通して、プラスチックごみの削減につなげています。
参考:花王のESG戦略 – Kirei Lifestyle Plan|花王株式会社
日本マクドナルド株式会社
日本マクドナルド株式会社は「安全な食」「気候変動対策」「地域貢献」「労働環境」の4つの領域で、SDGsなどに取り組んでいます。
例えば、MSC認証を取得した魚を使った商品やレインフォレスト・アライアンス認証100%のコーヒーの提供など、責任のある調達を行っています。また、性別や年齢、国籍を問わず、多様な人材を採用し、ダイバーシティの推進にも積極的です。
さらに、毎年3月には「サステナビリティレポート」を公開し、目標に対する進捗や根拠となるデータ、年度ごとの取り組みなどを分かりやすく説明しています。
イオン株式会社
イオン株式会社は、2024年10月に日経BPが発表した「第5回ESGブランド調査」で第1位を獲得した企業です。
同社は、環境に配慮したオリジナルブランド「トップバリュ グリーンアイオーガニック/グリーンアイナチュラル」を展開したり、MSC認証やASC認証などの持続可能な水産物の販売を長期的に行ったりしています。
また、毎月11日に行われる「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」では、レシートの合計額の1%分の品物がボランティア団体に寄付される仕組みになっています。利用者は、レジで受け取ったレシートを自分が応援したい団体を選んで専用のBOXに投函可能です。
そして、2025年7月には「2040年までにグループ全店舗での冷凍・冷蔵機器の自然冷媒(ノンフロン)化を完了する」という目標を発表しました。2009年から始まったこの取り組みは、日本の小売業では初めての試みです。
まとめ
企業がSDGsやESGに取り組むことは、持続可能な企業経営を実現するために欠かせません。こうした積極的な姿勢を見せることで、企業イメージの向上やESG投資の獲得など、さまざまなメリットが期待できます。
また、ステークホルダーに対して十分な説明を行い、SDGsウォッシュにならないよう注意することも重要です。これらのポイントを押さえることで、取り組みをスムーズに進められます。





