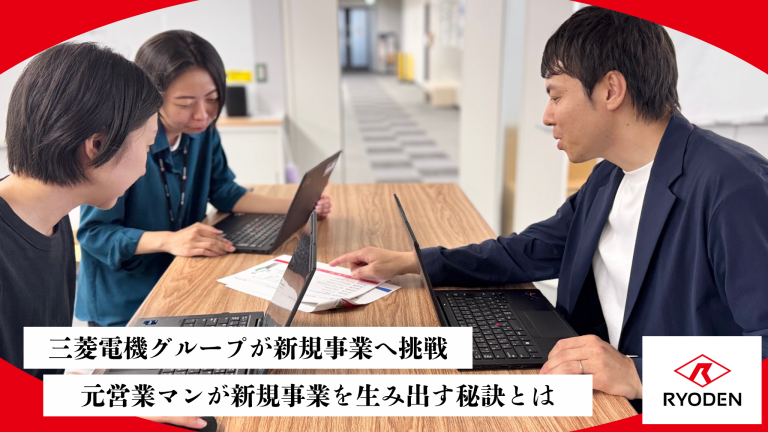株式会社RYODEN
新事業推進室 事業開発部 部長 甲斐 達也 氏
2001年RYODEN入社。三菱電機本社出向を経て、RYODEN本社で車載向けの半導体の営業やマーケティングに長く従事。2016年頃から主に海外の技術や製品を活かして法人向けのAIカメラやキャッシュレスに関する新事業への取組をはじめ、2020年から自社ブランドのAIoTサービス”Pescle”を立上げ主導。
新事業推進室 事業開発部 手島 大介 氏
約16年間にわたり車載機器を中心とした製造業のお客様を担当。
生産・設計・調達・品質管理など、さまざまな現場での課題解決を経験し現場視点を大切にしたものづくり支援を実践。その後、新規事業開発プロジェクトリーダーとして、製造業に特化したプロ人材紹介サービス『ウィズプロ』を企画・立案。
業界初、商社によるサービスとして運営中。
株式会社RYODEN
1947年設立。75年以上の歴史を持ち、社員数約1,500名を誇る国内大手の技術商社。東証プライム上場。三菱電機グループ国内最大の商社として、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、などの事業を手掛ける。
2023年4月、菱電商事株式会社から株式会社RYODENに社名を変更。近年は「物を売るだけの商社」から「事業を創出する会社」への変革を目指し、新規事業にも取り組む。
デジタル技術の進化で企業間の直接取引が増える今、変革を迫られる業種のひとつが商社です。こうした中、新規事業に取り組む商社として注目されているのが、三菱電機グループの技術商社である株式会社RYODENです。
同社ではエレクトロニクスやシステム関連事業に加え、ICTやヘルスケア、スマートアグリ(デジタル技術を使った農業)といった分野に進出しています。
「物を売る商社」から「事業を創出する会社」への変革を目指す同社では、さらに新規事業を推進するため専門部署を立ち上げたと言います。今回はこの専門部署で新規事業に携わっている、甲斐達也さんと手島大介さんにお話を伺いました。かつて商社で営業をされてきたお2人がどう新規事業に取り組んでいるのか、その秘訣を探ります。
ゼロから新規事業を立ち上げるため、専門部署を設立

甲斐さん(以下敬称略):当社が新規事業へ本格的に取り組み始めたのは、リーマンショック後の2010年頃であったと記憶しています。専門商社というビジネスモデルは安定性が高い一方で、時代の変化に対応するためには新しい事業への挑戦が不可欠だという機運が社内で高まりました。
ただ、当時は既存の事業部内で新規事業開発を行っていたため、スマートアグリやヘルスケアといった領域で事業化は実現したものの、既存事業の延長線上に留まる傾向がありました。そこで、ゼロから新たな事業を立ち上げることを目的に、2019年に専門組織として「新事業推進室」が設立されました。当初は既存事業の持続的なイノベーション創出が主なミッションでしたが、2022年からは、事業モデルそのものを変革する本格的な事業開発へと舵を切りました。
甲斐:当室のミッションは、RYODENの未来を担う事業の種を創出する戦略部門と位置づけられています。事業化の目処が立ったものは既存の事業部へ移管するか、あるいは新たな事業部として独立させるというスキームです。
まだ歴史が浅く、当室から事業化に至った実績はございませんが、現在まさに複数のプロジェクトが進行しています。
甲斐:例えばリクルート様であれば、情報プラットフォームという強力な事業基盤があります。その上でアプリケーションを変化させることで、多様なビジネスを展開しやすい構造です。しかし、当社には卸売事業以外にそうした共通基盤がなかったため、当初はその点に難しさを感じていました。
そこで私たちは、まず「プラットフォームとなり得る事業を創出する」というミッションを掲げました。その第一弾としてスタートしたのが、プロ人材のマッチングサービス『ウィズプロ』です。そして、この事業基盤を土台に、企業のサステナビリティ担当者様向けのマッチングサービス『サステク』の開発へと繋がりました。
常にゼロからイチを生み出し続けるのは、やはり困難を伴います。ですから、まずは強固な事業基盤を構築し、その上で様々なアプリケーションやサービスを展開していくという発想に至りました。
手島さん(以下敬称略):一見すると大きく異なるようですが、実は共通点もございます。商社の基本的な機能は、お客様のニーズに合わせて最適な商材を仕入れ、ご提供することです。その意味で、企業や人と人とを「つなぐ」マッチング事業は、これまでの商社ビジネスと本質的な構造は共通していると考えています。私自身、長年この会社で営業としてお客様と向き合ってきた経験を、現在の事業開発にも活かせると確信しています。
手堅いアイデアとチャレンジングなアイデアの両方を持つ

甲斐:私は現在、マネジメントと並行してプレイヤーとしての役割も担っています。そのため、最前線で多くのお客様と接する中で、常に新しい事業のシーズ(種)を探索しており、比較的アイデアを着想しやすい環境にあります。ただ、そこから事業性や市場規模、そして我々がやり切れるかという実現可能性を多角的に検証し、事業として立ち上げるまでのプロセスに、この仕事の難しさと面白さがありますね。
手島:私の場合は、固定観念に縛られず、あらゆる可能性をフラットに検証することを心がけています。従来の考え方では実現不可能に思えるアイデアでも、まずは「できるかもしれない」という前提で検証に着手します。積極的に外部へヒアリングを行うことで、当初は想定していなかった実現の可能性が見えてくることも少なくありません。
手島:おっしゃる通り、事業部門として収益への貢献を期待される側面はございます。ですから、私たちは常に複数の事業シーズをポートフォリオとして持つことを意識しています。
その中には、既存事業との親和性が高く、短期的な収益化が見込める、いわば「安定」志向のシーズもあれば、既存の枠組みを大きく超えた、収益が未知数の「挑戦」的なシーズもあります。「挑戦」的なプロジェクトばかりでは、短期的な成果が見えにくく、周囲の理解を得るのが難しい場面も出てきます。
そこで、短期的に成果が期待できる事業を手がけることで、プロジェクトの進捗を社内外に示しやすくなります。この「安定」と「挑戦」の両者をバランス良くポートフォリオに組み込むことが、持続的な事業開発には不可欠だと考えています。
会社が新規事業の重要性を明確にしていることが重要

手島:新規事業の担当者というと、革新的なアイデアを次々と生み出すタイプを想像されるかもしれません。しかし、私自身はむしろ、託されたミッションを着実に遂行していくことを得意としています。ですから、日々の業務には比較的、淡々と取り組んでいるかもしれません。厳しいフィードバックを受けても冷静に状況を分析し、目標数値に届かなければ、淡々と達成に向けた計画を再構築する。新規事業は、小さな実績を粘り強く積み重ねていくことが求められるため、こうした姿勢もまた重要だと考えています。
このように着実に業務を進められる背景には、会社としての方針が明確に示されていることが大きく影響しています。従来の商社ビジネスに留まらず、新たな事業を創造していくことの重要性が、会社のビジョンやパーパスの中で明確に言語化されています。だからこそ、私たちも納得感を持って自身の役割を理解し、ミッション達成に邁進できるのです。社内からの協力が得やすいのも、このおかげです。
もし会社が「新規事業は担当者の裁量に任せる」というスタンスであれば、これほど着実な推進は困難だったでしょう。
代表のメッセージも私たちの大きな支えとなっています。代表は「RYODENは失敗ができる会社だ」と明言し、失敗から学び、次なる進化につなげることの重要性を社内に向けて継続的に発信しています。その結果、社内には失敗を恐れずに挑戦できる文化が醸成されていると感じます。
手島:ええ。加えて、チームメンバーの存在も不可欠です。私が苦手とする領域を、甲斐をはじめとする他のメンバーがカバーしてくれる。互いの得意分野で補完し合える関係性が構築できている点は、私たちの大きな強みです。
甲斐:それに加えて、私たちは外部人材の活用も積極的に行っています。社内リソースのみでは、事業をスケールさせるための経験やスキルが不足するケースもあるためです。
手島:おっしゃる通りです。以前、みらいワークス様のセミナーで伺った「無知の知」、つまり自分が何を知らないかを自覚することの重要性を痛感しています。自社の弱みや不足している点を正確に把握できれば、それを補うための最適なピースを見つけ出し、組み合わせることで、自ずと事業の成功へと近づけるはずです。
商社のビジネスで培ったアセットを最大限に活かす


手島:既存事業部では大学や海外スタートアップとの提携事例も多いですが、新事業推進室としては、ネズミ・害虫の遠隔監視ソリューション『Pescle』でAI技術を持つスタートアップと連携した実績があるものの、まだこれからという状況です。イノベーションを創出する上で、他社との協業は不可欠だと考えています。
その際、全く接点のない企業にアプローチするのではなく、まずは既存事業で培ったネットワークを通じて情報を得たり、企業を紹介いただいたりといった形を想定しています。これは、ゼロからスタートするのではなく、既存事業のアセットを最大限に活用するという当社の基本方針に基づいています。
手島 :はい。当社には国内・海外合わせて5,000社以上のお取引先様とのリレーションシップがあり、その中には優れた技術を持つ企業も数多く含まれます。こうしたアセットは、私たちの大きな財産です。
一方で、企業の規模が大きくなるほど、部門間の連携が複雑になり、アセットが活用しにくくなるという側面もございます。例えば、他部門のアセットを活用しようとしても調整に時間がかかったり、新規事業への理解が得られず協力体制が築けなかったりするケースは、大企業では珍しくありません。
その点、当社は組織が比較的コンパクトであるため部門間の意思疎通が図りやすく、アセットを柔軟に活用しやすい環境にあると感じています。また、私自身が新卒で入社したため、多くの社員と面識があることも円滑な業務推進に繋がっています。
手島:当社の中長期計画では、「事業創出会社への変革から成長へ」というテーマを掲げています。つまり、新たな事業を継続的に創出し続けること、それが当社の目指す姿です。
ただ、これまでは既存事業で得た知見やリソースを組み合わせる形での事業化が多く、純粋なアイデアの種から事業を育て上げる、真のゼロイチには至っていませんでした。今後は、このゼロイチのプロセスにこそ挑戦したいと考えています。
もちろん、アイデアを創出するだけで終わってしまっては意味がありません。創出した事業の種を、次の成長ステージへと着実に引き継いでいく仕組みづくりが不可欠です。私自身、ゼロからイチを生み出すフェーズと、その後のイチをジュウに成長させるフェーズ、その両方を経験したい。そして、この一連のプロセスを成功の「型」として確立することで、再現性を持たせ、他のメンバーにも展開できると考えています。
当室はまだ発足から6年ほどの若い組織です。だからこそ、私たち自身がキャリアパスを切り拓いていく必要があると感じています。
手島:そうですね。組織を構築しながら事業を立ち上げ、運営していくという点では、共通する部分があるかもしれません。新事業推進室のメンバー一人ひとりが、ベンチャー企業の経営者であるという気概を持って取り組む。そんな組織を目指しています。これが実現すれば、新たな人材を採用する際にも、良い影響をもたらすと考えています。
「RYODENに入社すれば、若いうちからベンチャー経営に近い経験を積み、市場価値の高いスキルを習得できる」。将来的には、RYODENをそのような企業へと成長させていきたいです。