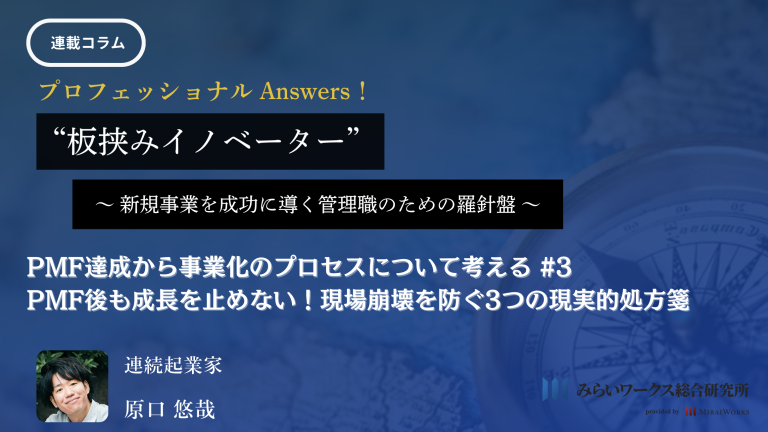Professional Answers!シリーズ第1弾 – 大企業における新規事業開発編 –
“板挟みイノベーター” 〜 新規事業を成功に導く管理職のための羅針盤
2025年7月のテーマは「PMF達成から事業化のプロセスについて考える」です。新規事業を成功に導く管理職“板挟みイノベーター”からの質問に対して、4名の新規事業のプロフェッショナルに解決策を教えていただきました。
#1 PMF達成から事業化のプロセスについて考える ー石森 宏茂プロ編
#2 PMF達成から事業化のプロセスについて考える ー岩本 晴彦プロ編
#3 PMF達成から事業化のプロセスについて考える ー原口 悠哉プロ編 本記事
#4 PMF達成から事業化のプロセスについて考える ー村松 龍仁プロ編
今月の”板挟みイノベーター”からの質問
社内で名実ともにPMFを達成したと実感し、毎日業務が追いつかない状況です。嬉しい悲鳴とも言えますが、この成長スピードに組織の成長が追いついていないことに不安を感じています。上層部は更なる成長を求めていますが、現場は既に限界に近い状態です。かといって、慎重すぎる対応では機会を逃すかもしれません。
人材調達や人材育成など体制強化が急務だと感じていますが、大規模な組織変更を提案する立場でもなく、どこまで踏み込んでいいものか悩んでいます。既存の人事制度や予算の制約の中で、どうすれば効果的に対応できるでしょうか。
また、社内外の調整も増えていますが、他部門も既存業務で手一杯のようで、協力を求めるのをためらってしまいます。でも、このままでは品質管理や顧客対応に支障が出かねません。
何とかこの状況を打開したいのですが、急激な変化は避けたいという気持ちもあります。これまでの会社の伝統や価値観を尊重しつつ、どのようにして人材育成、体制強化、社内外の調整を同時に、そして段階的に進めていけばよいでしょうか?過去に似たような急成長を経験した部署があれば、そのやり方を参考にできないかとも考えていますが…。
第3回目は、原口 悠哉プロの回答です。
まずはPMFを達成したとのことでおめでとうございます!
この記事では、事業の急成長によりリソースがひっ迫している中で、どのように対応していくべきかを書いていきます。
今の状況の整理とリソース調整について
相談者さまの”急激な変化は避けたい”というお気持ちはよく分かりますが、既に変化は始まっており、どう対応するかが重要な段階に来ています。いわば現在は隣家で火事が発生しているにも関わらず、どうすべきか家の中でゆったり考えているような状況です。
LinkedInの創業者であるリード・ホフマンは、「スタートアップとは、崖の上から飛び降りながら飛行機をつくるようなものだ」と語りました。この言葉は常に走りながら事業を作り上げていく必要があるということを示しており、急成長している事業運営には常在戦場の覚悟で取り組んでいく必要があります。
このまま手を打たないと何が起こるのか
現在の状況で手を打たなかった場合に何が起こるのか、について書いていきます。
まず発生するのはサービスやカスタマーサービス品質の低下です。例えばWebサービスであれば過負荷による処理速度の低下やエラーの発生、店舗営業であれば接客品質の低下などの状況が発生し得ます。また、それまで以上に多様なユーザーによる利用が行われることになり、お問い合わせやクレームなども増加します。その結果、ユーザーの不満がたまり悪評が広がりかねません。
それに加え、現場は既に限界に近いということですが、さらなる成長に伴いその負荷はさらに増していきます。その結果、各メンバーの方が限界を迎え退職・離脱し、社内リソースがさらにひっ迫してしまう未来も容易に想像できます。今はギリギリ回っていたとしても、人間は限界を超えた状態で長期間働き続けられません。
さらに、貴社がその市場における課題と解決策の仮説証明を行ったことによって、それに追随する企業が大きく成長していく可能性も十分に考えられます。情報が共有される速度が加速度的に高まっている現代において、魅力的なビジネスモデルはすぐに模倣されます。その例は枚挙にいとまがなく、AIプロダクトは無数に生まれていますし、スポットワーク、フリマアプリ、フードデリバリーなど、ここ最近でも多くの激しい競争が行われています。もちろん先行者優位は存在しますが、後発企業が勝者となるケースも多くあります。
上記のように、サービスがせっかく急成長していたとしてもそれは将来の成功が確約されたわけではなく、それに対応できなければ失敗に終わる可能性も大いに有り得るわけです。
行うべき3つの対応
順を追って行うべきは「提供範囲の制限」「業務効率化」「採用」であり、それぞれに詳しく触れていきます。
まず行うべきはサービスの提供範囲を絞ることです。
例としてはWebサービスであれば新規のユーザー登録を絞る、店舗であれば営業時間を短縮する、実際のモノであれば販売の停止などです。そうしたことで営業機会の損失が発生してしまいますがそれでも不十分なサービスの提供によって評価が下がってしまうよりも良いケースがほとんどです。また、制限によってある種のプレミア感が生まれ、逆に人気が加熱するという可能性もあります。
次になる対応策は現業務の効率化です。
基本的に事業立ち上げ時点から自動化を進めるのはあまり推奨されません。なぜなら、不適切なオペレーションを自動化してしまう可能性があり、無駄なコストが発生してしまうからです。しかし、PMFを達成した現時点においては、自動化を始めとした業務の効率化は事業拡大において非常に有用な手段です。具体的にはまずは業務内容の細分化を行い、プロセスの改善、AIなどによる自動化や、外部への発注などが想定されますが、業務に追われている状況ではそういった効率化を行うリソースがない、ということも多いです。また、そもそも業務をいくら効率化したとしてもその効果には限界があります。基本的に事業立ち上げ時点から自動化を進めるのはあまり推奨されません。
3つ目の対応は採用による人員補強です。
大規模な組織変更を提案できる立場ではないとのことですが、現状においてはどういうリソースが足りず、採用が必要なのかはある程度明確であると考えます。そのため、組織変更は必要なく、現状の組織体制のままで人員を増やしていく、という進め方で良いのではないでしょうか。もちろん、多数の人数を増やす場合はマネジメント階層を増やすなども必要ではありますが、まずは当面の状況への対応が重要です。採用を行えば問題がすぐに解決するというわけではありません。教育コストの発生・参画に時間を要する・衝突や早期退職の発生リスクなどがあり、採用はすべてを解決してくれる銀の弾丸ではないのです。しかし、長期的な成長を望むのであれば真剣に取り組む必要があります。
筆者自身も経験がありますが、事業運営においてリソースが常に適切という状況を作ることは非常に困難であり、ひずみを抱えながら成長していくしかありません。なぜなら、サービスが成長するであろうと見込んで採用を進めたとしても、サービスが伸び悩んだ場合に人件費が無駄になるというリスクを抱えることになります。また、良い人材を雇用するためには数ヶ月程度の時間を要することも多く、成長に合わせて即時リソース補充するということは難しいのです。もちろん、予備人材を抱えたり、素早く調達可能なアルバイト人材で回すという方法も可能ですが、その効果は限定的です。
どのような人材を採用すべきか
「人材育成」と書かれていますが、現場にそれにコストをかける余裕はあるのでしょうか。現場のメンバーからすれば、ただでさえリソースが不足しているにも関わらずさらに教育まで行わなくてはいけない、という状況を押し付けるべきではありません。仮に採用費用がかさんだとしても、今のような状態であれば即戦力となりうる、経験を持つプロフェッショナル人材を雇用すべきです。もちろん、人材育成が不要なわけではなく重要ではありますが、優先順位を設けて緊急度の高い問題に対応すべき、ということです。
サービスのさらなる拡大のために
この記事では、PMFによって現場のリソースがひっ迫しているという状況をどう考えるべきかをまず説明し、その後に業務の効率化や外部発注、そして採用を行うことを勧め、最後にどのような人材を採用すべきかについても触れました。
PMFにまでたどり着けないサービスが多い中、現在抱えていらっしゃる苦しみはそれを成し遂げたゆえのものです。大変な局面だからこそ、いま打つ一手が未来のスケールを決めます。
貴社が提供する価値を、より多くのお客さまへ届けられるために、この記事がご参考になれば幸いです。
<関連記事>
2024年11月 学びながら進める新規事業開発の全体像とは#1 -石森 宏茂
2024年11月 学びながら進める新規事業開発の全体像とは#2 -石森 宏茂
2024年12月 新規事業開発戦略を考える#1 -石森 宏茂
2024年12月 新規事業開発戦略を考える#2 -岩本 晴彦
2024年12月 新規事業開発戦略を考える#3 -小林 舞
2024年12月 新規事業開発戦略を考える#4 -原口 悠哉
2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える #1 -石森 宏茂
2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える#2 -岩本 晴彦
2025年01月 新規事業開発実現のための組織人事制度を考える#3 -原口 悠哉
2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #1 -石森 宏茂
2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #2 -岩本 晴彦
2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #3 -原口 悠哉
2025年02月 “アイデア創出”と“手段としての市場調査”について考える #4 -村松 龍仁
2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #1 -石森 宏茂
2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #2 -岩本 晴彦
2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #3 -原口 悠哉
2025年03月 “MVP検証”という手法について考える #4 -村松 龍仁
2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #1 -石森 宏茂
2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #2 -岩本 晴彦
2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #3 -原口 悠哉
2025年04月 “MVP検証”からPMFまでのプロセスについて考える #4 -村松 龍仁
2025年05月 説得力ある事業計画について考える#1 -石森 宏茂
2025年05月 説得力ある事業計画について考える#2 -岩本 晴彦
2025年05月 説得力ある事業計画について考える#3 -原口 悠哉
2025年05月 説得力ある事業計画について考える#4 -村松 龍仁
2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#1 -石森 宏茂
2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#2 -岩本 晴彦
2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#3 -原口 悠哉
2025年06月 プロジェクト進行中の経営陣への想定外の相談について考える#4 -村松 龍仁